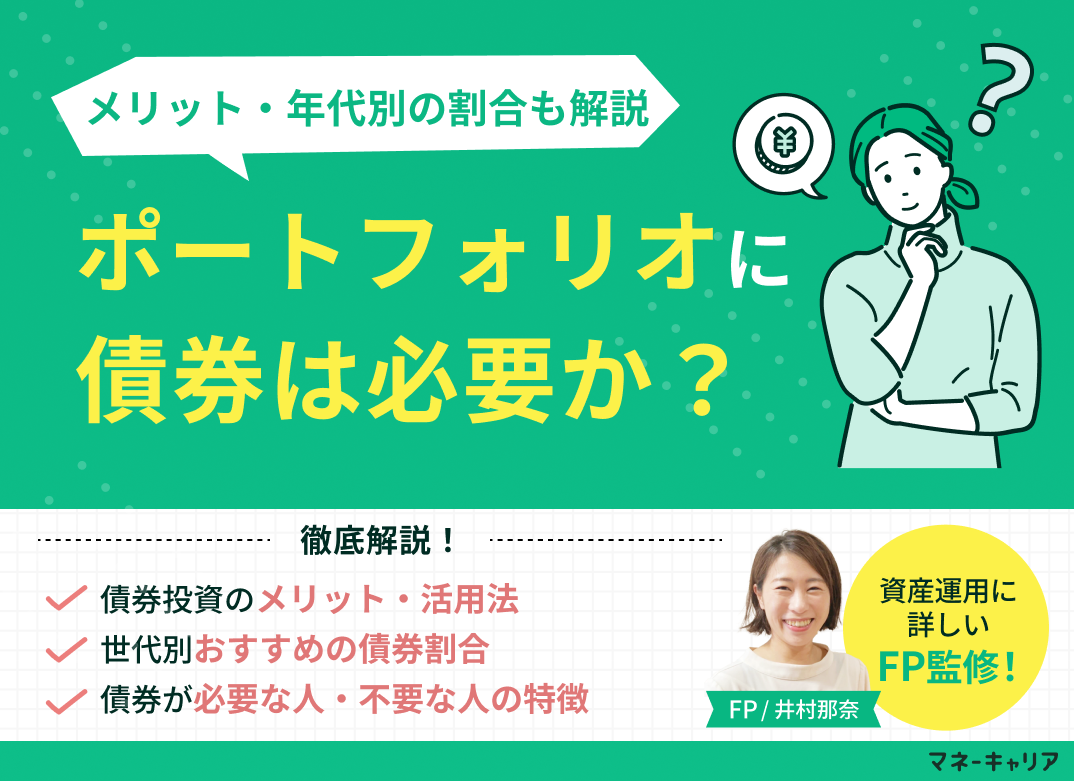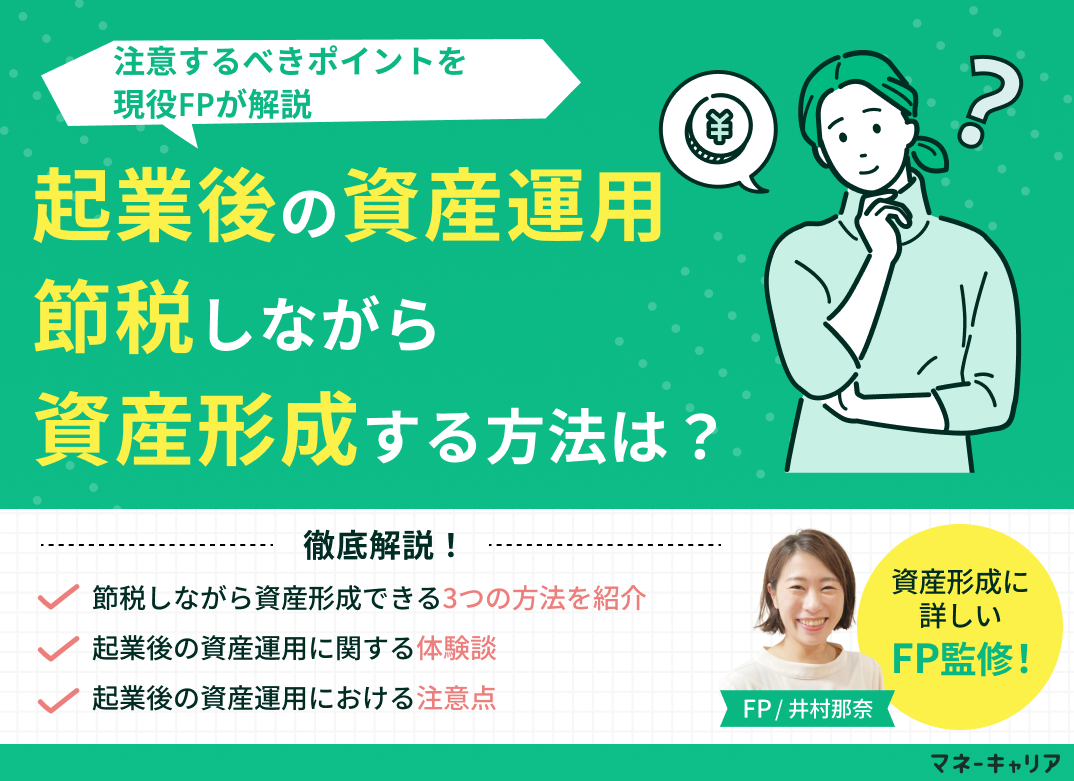・将来のために資産運用を始めたいけど、夜勤や不規則なシフトで時間がない...
・貯金はしているけど、インフレで価値が目減りするのが心配
このような悩みを抱える看護師は多いのではないでしょうか?
実は、忙しい看護師でも無理なく始められる資産運用方法があります。この記事では、看護師におすすめの4つの資産運用方法と、資産運用を始めるべき3つの理由を徹底解説します。
とくに「つみたてNISA」や「iDeCo」は少額から始められ、自動積立で運用できるため、時間に余裕のない看護師にぴったりです。退職金や年金だけでは不足しがちな老後資金の目安や、将来のライフプランを実現するための資産形成について、わかりやすくご紹介します。
マネーキャリアのファイナンシャルプランナーによる無料相談を活用すれば、あなたのライフプランに合わせた最適な運用プランが見つかりますよ。将来への不安を解消し、充実した看護師ライフを送りましょう。

この記事の監修者
谷川 昌平
フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
続きを見る
▼
閉じる
▲
看護師におすすめの資産運用の方法4選
看護師という仕事は、不規則な勤務形態やシフト制で働くことが多く、時間的余裕が限られています。忙しい看護師でも、将来の経済的安定のために資産運用を始めることは重要です。
とくに「ほったらかし」でも運用できる方法は、時間に制約のある看護師にとって理想的な選択肢になります。
ここでは、忙しい看護師でも無理なく始められる4つの資産運用方法をご紹介します。少額から始められ長期的に資産を増やしていけるので、将来に不安を感じている方にもおすすめ方法です。
| 資産運用方法 | 特徴 | こんな人におすすめ | リスク度 |
|---|
| 新NISA | 非課税投資枠で
長期投資可能 | 長期資産形成を目指す人 | ★★☆☆☆ |
| iDeCo | 税制優遇あり
老後資金に最適 | 将来の年金を増やしたい人 | ★★☆☆☆ |
| ETF | 低コストで
分散投資可能 | 効率的に市場に投資したい人 | ★★★☆☆ |
| REIT | 不動産収入を
少額から得られる | 安定した配当を求める人 | ★★★★☆ |
新NISA(つみたて投資枠)
新NISA制度は2024年から始まった制度で、投資で得た利益(配当金や分配金、売却益)が非課税になる大きなメリットがあります。通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座ではこの税金が一切かかりません。
新NISAの概要を確認しましょう。
| ポイント | 内容 |
|---|
| 非課税期間が無期限 | 一度買った商品は、いつ売っても非課税
長期運用にぴったり |
| 投資枠が拡充 | 年間360万円
(つみたて120万円+成長投資240万円)まで非課税 |
| 売却分は再利用可能 | 売った分の投資枠を
翌年以降にまた使える柔軟な制度 |
新NISAには2つの投資枠(つみたて投資枠・成長投資枠)があり、それぞれに特徴があります。投資枠の概要は以下のとおりです。
| 投資枠の種類 | 年間投資上限額 | 特徴 |
|---|
| つみたて投資枠 | 120万円 | 手数料が低く
長期・積立向きの投資信託に投資可能 |
| 成長投資枠 | 240万円 | 国内外の株式・ETF・投資信託など
幅広い商品に投資可能 |
看護師のような忙しい方には「つみたて投資枠」がおすすめです。毎月一定額を自動的につみたてるドルコスト平均法を利用すれば、価格変動に一喜一憂することなく、長期的な資産形成が可能です。
たとえば、月1万円からインデックスファンド(日経平均やS&P500などの指数に連動する投資信託)に積立投資することで、市場全体の成長を取り込めます。忙しい看護師でも、つみたて投資枠なら1度設定すれば、ほったらかしで大丈夫です。時間をかけて資産を育てていきましょう。
iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、公的年金とは別に自分で資金をつみたてて運用する私的年金制度です。最大の特徴は、掛金が全額所得控除になるという税制優遇です。
iDeCoの概要を見てみましょう。
| ポイント | 内容 |
|---|
| 節税メリットが大きい | 掛金は全額所得控除
住民税・所得税が軽減される
将来受け取るときにも税制優遇あり |
| 月5,000円から始められる | 自営業(上限掛金額:68,000円)
会社員(上限掛金額:23,000円)
公務員(上限掛金額:20,000円)
専業主婦・主夫(上限掛金額:23,000円)
職業ごとに上限は異なるが、少額からでもスタート可能 |
| 自分で運用商品を選べる | 定期預金・保険・投資信託など
自分のリスク許容度に応じて選択できる |
看護師として勤務されている方(国民年金第2号被保険者)の掛金限度額は、勤め先の企業年金制度によって異なります。企業年金がない場合は月額23,000円(年間276万円)まで、企業年金がある場合は月額20,000円(年間240万円)までを上限として拠出可能です。
年収450万円の看護師が月額2万円(年間24万円)をiDeCoに拠出した場合、所得税・住民税合わせて約72,000円の節税効果が期待できます。
iDeCoのもう一つの特徴は60歳まで引き出せないことです。一見デメリットに思えますが、長期的な資産形成を考える上では、強制的に貯蓄できるというメリットに変わります。将来のライフイベント(子どもの結婚・出産など)に備えて、計画的に資金を確保する手段としても活用できます。
iDeCoを始める際には金融機関選びや商品選択に迷うことがあるかもしれません。この場合は、無料のファイナンシャルプランナー(FP)への相談を活用して、自分に合った運用プランを立てることをおすすめします。
>>当編集部のおすすめ!無料のFP相談ならこちら
ETF(上場投資信託)
ETF(上場投資信託)は、取引所に上場している投資信託で、株式と同じように売買できる金融商品です。通常の投資信託とは異なり、リアルタイムで価格が変動し、自分の希望する価格で取引ができます。
ETF(上場投資信託)の概要は以下のとおりです。
| ポイント | 内容 |
|---|
| 少額で分散投資ができる | 1つのETFで複数の銘柄に投資できる
リスクを抑えながら資産運用が可能 |
| 株と同じように売買できる | 証券取引所でリアルタイムに売買できるため
流動性が高く、タイミングを見て取引可能 |
| 信託報酬が安い | 一般的な投資信託よりも運用コストが低いため
長期運用に有利 |
忙しい看護師にとってETFの最大のメリットは、1つの商品を購入するだけで自動的に分散投資ができる点です。日経平均株価に連動するETFを購入すれば、225銘柄の日本企業に一度に投資できます。S&P500などの米国株式に連動するETFを購入すれば、アメリカの主要企業500社に投資が可能です。
ETFは新NISAの成長投資枠で購入できるため、運用益が非課税になるメリットを受けられます。将来を見据えて資産を増やしたい看護師にとって、複利で増えたお金に税金がかからないのは、非常に有利なポイントです。
国内ETFだけでなく、米国市場のETFという選択肢もあります。米国ETFは種類が豊富で、テクノロジーや医療など特定のセクターに特化したものから、配当利回りの高いものまでさまざまです。ただし、米国ETFを購入する場合は為替リスクがあるため、注意しましょう。
REIT(不動産投資信託)
REIT(不動産投資信託)は、投資家から集めた資金で不動産を購入・運用し、賃貸収入や売却益を投資家に分配する金融商品です。日本のREITはJ-REITと呼ばれ、オフィスビル・商業施設・マンションなどさまざまな不動産に投資されています。
REIT(不動産投資信託)の概要を確認しましょう。
| ポイント | 内容 |
|---|
| 少額から不動産投資ができる | 数万円からでも投資可能
高額な資金やローンは不要 |
| 管理の手間がかからない | 賃貸管理や修繕対応などは
すべて運用会社にお任せ |
| 株と同じように売買できる | 上場しているため
証券口座からいつでも売買可能で流動性が高い |
看護師がREITに投資するメリットは、実物不動産投資と比較した場合の手軽さにあります。実物不動産は物件選びや管理に手間がかかりますが、REITなら証券会社で手軽に購入できます。
REITの大きな魅力は比較的高い分配金利回りです。過去のデータを見ると、J-REITの平均予想分配金利回りは3〜6%程度で推移しており、魅力的な水準となっています。
REITも新NISAの成長投資枠で購入できるため、分配金や売却益が非課税になるというメリットがあります。定期的な収入源として分配金を活用したい看護師には、ポートフォリオの一部としてREITを組み込むことも検討する価値があるでしょう。
REITには単一の不動産タイプに投資する商品と、複数のタイプに分散投資する「複合型」の商品があります。リスク分散の観点からは、複合型のREITが初心者には向いているといえるでしょう。
無料FP相談を賢く活用して、効率的に運用プランを立てよう!
資産運用を始めたいけれど、どの方法が自分に合っているのかわからない…。このような看護師には、無料のファイナンシャルプランナー(FP)相談がおすすめです。マネーキャリアでは、
忙しい医療従事者のライフスタイルを合わせた運用プランを提案してくれます。
無料FP相談では、NISAやiDeCoといった制度の活用法はもちろん、あなたの年収や将来設計に基づいた具体的な資金計画まで相談可能です。看護師特有の退職金制度や年金制度を考慮した長期的な資産形成プランを立てる際には、プロのアドバイスが非常に役立ちますよ。
相談時には「資産運用の目的は何か」「どのくらいのリスクなら許容できるか」などを事前に考えておくと、より具体的なアドバイスが得られるでしょう。無料でもしっかり提案してもらえるので、最初の方向性を決めるのにぴったりです。
自分に合った運用プランを効率的に見つけ出し、忙しい看護師生活のなかでも着実に資産を育てていきましょう。
>>資産運用に精通!マネーキャリアで無料相談する
看護師が資産運用を始めるべきなのはなぜ?3つの理由を紹介
看護師の皆さんは日々、患者さんのケアに忙しく、自分の将来のお金について考える時間が取りにくいかもしれません。
しかし、安定した収入があるからこそ、一部を効率的に運用して将来に備えることが大切です。調査によれば、看護師の34%が「老後の生活に不安を持った」ことをきっかけに資産運用を始めています。始めた後には「もっと早く始めればよかった」と感じる方が多いのも特徴です。
ここでは、看護師が資産運用を始めるべき理由を3つご紹介します。将来の経済的自由を手に入れるための第一歩を踏み出しましょう。
- 退職金や年金だけでは老後資金が足りないため
- 貯金だけではお金が増えないため
- 理想のライフプランを実現させるため
退職金や年金だけでは老後資金が足りないため
公的年金だけでは、将来の生活を十分に支えることが難しいです。総務省の調査によると、65歳以上の無職の夫婦世帯は、
毎月約25万円の支出に対して、年金などの収入は約21万円です。毎月約4万円の赤字が生じています。
赤字を20年間で計算すると、約960万円の貯蓄が必要となるのです。ゆとりある老後生活を送るためには、より多くの資金が必要です。生命文化センターの調査では、夫婦でゆとりある生活を送るには月に約38万円、20年間で約9,120万円が必要とされています。
看護師の場合、病院の退職金制度は比較的充実していることもありますが、老後30年以上を安心して暮らすには十分とはいえません。
持ち家がなく賃貸暮らしの場合、都市部では月10万円、20年間で2,400万円の家賃が追加で必要です。地方でも家賃が月5万円程度としても、20年で1,200万円の追加支出が見込まれます。
医療現場の肉体的・精神的負担を考えると、70歳まで看護師として現場で働き続けることは現実的ではありません。今から計画的に資産形成を始めることで、将来の経済的不安を大きく軽減できるのです。
忙しい看護師の皆さんでも、将来の安心のために資産運用を始めることは決して難しくありません。下記の記事では、看護師におすすめの資産運用方法として、新NISA(つみたて投資枠)・iDeCo・ETF・REITの4つをご紹介しています。
とくに「つみたてNISA」は少額から始められ、ほったらかしでも運用できるため、時間に余裕のない看護師にぴったりです。
貯金だけではお金が増えないため
日本の銀行預金金利は2024年に上昇し、現在は大手銀行の普通預金で0.2%程度になっています。以前の0.001〜0.002%という超低金利状態からは改善されましたが、まだ十分とはいえません。
1,000万円を1年間預けても、得られる利息はわずか2万円程度です。これでは貯金だけで資産を増やすことは難しいです。貯金だけではお金はほとんど増えないといってよいでしょう。
厄介なのが、インフレによるお金の価値の目減りです。日本銀行は物価上昇率2%を目標としていますが、仮に年2%のインフレが続くと、100万円の価値は10年後には約82万円、20年後には約67万円相当まで下がってしまいます。
計算式
将来価値=元価値×(1−インフレ率)
期間
将来価値
=
100万円 ×
(
1
−
0.02
)
期間
10年後の価値
10年後の価値=100万円×(1−0.02)
10=81.7万円
20年後の価値
20年後の価値=100×(1−0.02)
20=66.8万円
つまり、銀行に預けているだけでは、実質的にお金の価値は減っていくのです。
看護師として安定した収入がある今こそ、資産運用を始める絶好のチャンスです。月々少額からでも積立投資を始めることで、長期的な資産形成が可能になります。資産運用を始める際は、特定の金融機関に所属しない「独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)」に相談するのがおすすめです。
マネーキャリアなどのIFAは、特定の金融会社に偏らない中立的な立場からアドバイスを提供し、無料相談もできます。看護師のライフスタイルや将来設計に合わせた最適な運用プランを提案してくれますよ。忙しい看護師でも手軽に相談できる点が大きな魅力です。
>>中立的な立場からアドバイスを提供!マネーキャリアのIFAに無料相談する
理想のライフプランを実現させるため
ライフプランとは、将来の人生設計です。看護師は、結婚・出産・住宅購入・子どもの教育費に加え、留学や資格取得、働き方の変更などキャリアアップも重要なライフイベントとなります。
夢や目標を実現するためには、計画的な資金準備が必要不可欠です。とくに看護師は夜勤やシフト制など、体力的・精神的に負担の大きい勤務形態が多く、40代以降はフルタイム勤務の継続が難しくなるケースも少なくありません。
資産運用をしておくと、将来「夜勤をやめる」「日勤だけで働く」「パート勤務に切り替える」など、自分に合った働き方を選べるようになり人生の選択肢が広がります。
月々の生活費を投資収益で一部カバーできれば、収入減少への不安も軽減され、心身の健康を優先した働き方を選べるようになるでしょう。ライフプラン設計は、ファイナンシャルプランナー(FP)の得意分野です。
看護師としてのキャリアパスを考慮しながら、将来の選択肢を広げるための資産形成プランを立ててくれます。資産運用は単なる「老後対策」ではなく、自分らしい人生を選択するための手段です。
あなたにぴったりの方法は?プロと一緒に最適な運用プランを立てよう
資産運用の方法は多種多様で、どれが自分に合っているのか迷ってしまうのは当然です。忙しい看護師にとって、
金融商品の選定や運用のための時間確保は大きな課題になるため、専門家のサポートを受けるのが効率的です。
マネーキャリアでは、看護師の働き方や収入事情を理解したファイナンシャルプランナーが、あなたのライフプランに合わせた最適な資産運用プランを提案してくれます。無料相談では、NISAやiDeCoの具体的な活用法はもちろん「夜勤で時間がない」「節約と投資のバランスがわからない」といった看護師特有の悩みにも対応可能です。
満足度98.6%の実績があり何度でも相談可能なので、投資初心者でも安心して利用できます。相談前に「老後の目標額」「月にいくら積立できるか」「リスクへの許容度」を考えておくと、より具体的なアドバイスが得られるでしょう。
自分だけで考え込むより、プロの視点を取り入れることで、効率的かつ安心して資産形成を始められます。経済的自由への第一歩を、専門家と一緒に踏み出しませんか。
>>資産形成はプロにおまかせ!マネーキャリアで無料相談する
看護師が資産運用を始める際によくある質問
資産運用に興味はあるけれど、さまざまな疑問を持っている看護師は多いのではないでしょうか。不規則な勤務形態や夜勤などがある看護師の場合、投資に割ける時間や精神的余裕も限られています。
ここでは、看護師が資産運用を始める際によく寄せられる3つの質問に答えていきます。疑問を解消して、あなたに合った資産運用をスタートさせましょう。
- 資産運用を始めるのに最適なタイミングは?
- 資産運用に回せる資金の目安はどれくらい?
- 資産運用を始める上での注意点は?
資産運用を始めるのに最適なタイミングは?
資産運用を始めるのに「今は時期が悪い」ことはありません。投資のプロが強調するのは、
「大切なのはタイミングではなく、時間を味方につけること」です。長期的な資産形成を目指す場合、始めるのが早ければ早いほど複利効果の恩恵を受けられます。
月1万円を年利3%で運用した場合、20年後には約320万円、30年後には約570万円になります。同じ運用でも、10年の差で資産額は約250万円も変わってくるのです。ただし、いきなり資産運用を始める前に、生活防衛資金の確保が大切です。
一般的には、突発的な出費に備えて手取り収入の3〜6か月分(看護師の場合、約100〜200万円程度)を普通預金などですぐに引き出せる状態にしておくことが推奨されています。結婚や出産、住宅購入など大きなライフイベントを控えている場合は、資金計画を立ててから投資を検討しましょう。
ファイナンシャルプランナーに相談すれば、ライフプランに合わせた資金計画と投資のバランスを適切に提案してもらえます。
「始めるなら今」が基本ですが、自分の状況に合わせた準備をしてからのスタートが大切です。
資産運用に回せる資金の目安はどれくらい?
資産運用に回せる資金の目安は、手取り収入の10〜20%程度とされています。看護師の平均年収が450万円程度とすると、月々の投資額は約5〜7万円が一つの目安となるでしょう。
ただし、絶対的な数字ではなく、ご自身の生活状況に合わせて調整が必要です。
基本的な考え方として、生活費と緊急予備資金を確保した上で、余裕資金を投資に回します。家計の支出構成として、住居費は手取りの25%以内、生活費全体は手取りの50〜60%程度に抑えられると理想的です。残りの資金から貯蓄と投資に振り分けていきましょう。
投資初心者は月々1万円などの少額から始めて、徐々に慣れていくことがおすすめです。つみたてNISAなら月々100円から始められるため、少額で投資の感覚をつかめます。
夜勤手当など、臨時収入の一部を定期的に投資に回すという方法も効果的です。投資に回せる資金がわからない場合は、ファイナンシャルプランナーで家計の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
無料FP相談では、看護師の収入特性を理解した上で、無理なく継続できる投資プランを提案してくれます。適切な投資額を知ることで、将来への不安を感じることなく資産形成が進められるでしょう。
>>家計の見直しを検討したい人必見!無料FPで相談する
資産運用を始める上での注意点は?
看護師が資産運用を始める際の注意点として、本業に支障をきたさない方法を選びましょう。不規則な勤務形態や夜勤があるなかで、
頻繁な売買が必要な投資方法は精神的・時間的負担が大きくなります。
つみたてNISAを活用した積立投資など、一度設定すれば自動的に続けられる「ほったらかし投資」が理想的です。医療従事者を狙った投資詐欺も増えているので注意しましょう。
「高利回り保証」「特別な投資機会」などと謳う誘いには要注意です。とくに「限定」「今だけ」といった言葉で焦らせる手口には警戒しましょう。迷った場合は、独立系ファイナンシャルアドバイザーなど中立的な立場のプロに相談することをおすすめします。
投資の種類によっては確定申告が必要になる場合があります。NISAやiDeCo以外の投資で分配金や売却益が発生した場合は、確定申告の必要性を把握しておきましょう。忙しい看護師にとって確定申告は負担になるので、非課税制度を上手に活用することが時間的にも効率的です。
看護師として培った「患者さんの状態を冷静に観察する力」は、実は投資にも活かせます。感情に左右されず、長期的な視点で資産運用に取り組むことが成功の鍵です。わからないことは専門家に相談しながら、無理なく継続できる投資習慣を身につけていきましょう。
【まとめ】看護師の資産運用はまずは手軽にできる方法から始めよう
忙しい看護師の皆さんでも、将来の安心のために資産運用を始めることは決して難しくありません。この記事では、看護師におすすめの資産運用方法として、新NISA(つみたて投資枠)・iDeCo・ETF・REITの4つをご紹介しました。
とくに「つみたてNISA」は少額から始められ、自動積立で運用できるため、時間に余裕のない看護師にぴったりです。資産運用を始めるべき理由としては、退職金や年金だけでは老後資金が不足すること、貯金だけではインフレで資産価値が目減りするなどが挙げられます。
まずは余裕資金の範囲内で、無理のない金額から始めることが大切です。わからないことがあれば、マネーキャリアなどの無料FP相談を活用してプロのアドバイスを受けるのがおすすめです。将来の不安を少しでも解消し、より充実した看護師ライフを送るために、今日から第一歩を踏み出してみませんか?