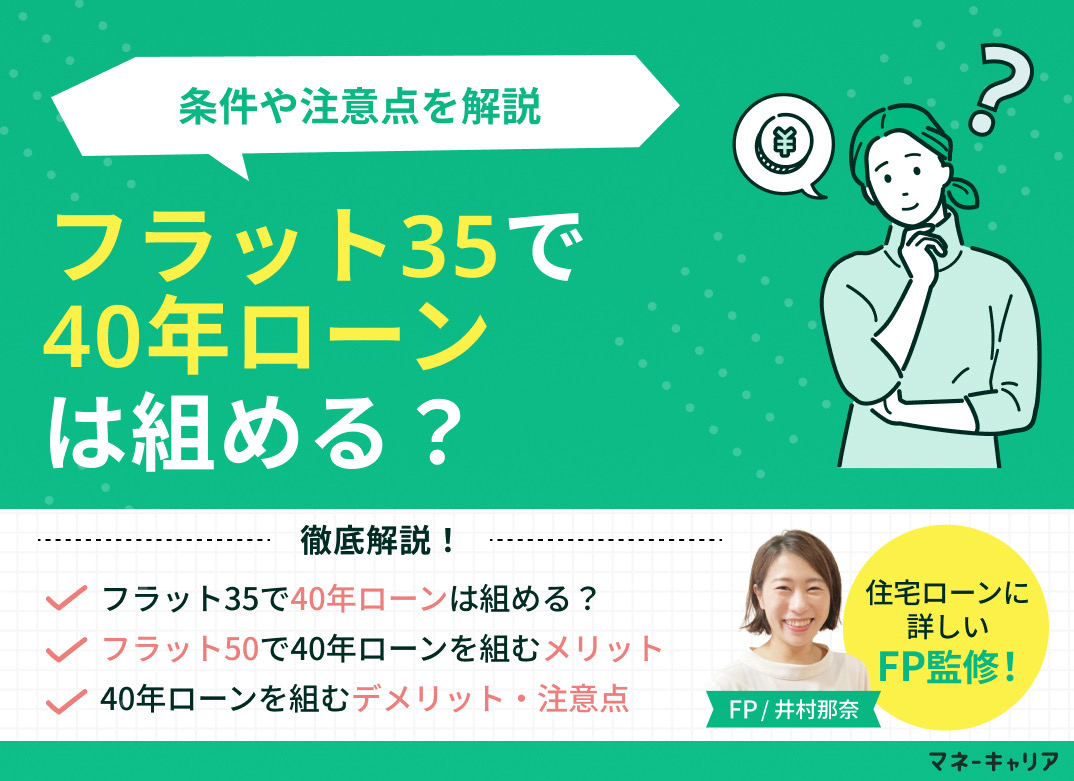

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- フラット35で40年ローンは組める?
- 前提【フラット50】で返済期間を40年に設定する
- 条件① 申込時の年齢が満44歳未満
- 条件② 長期優良住宅が対象
- 条件③ 借入額は物件価格の9割まで
- フラット35のお悩みは無料FP相談を活用しよう
- フラット50で40年ローンを組むメリット
- 住宅ローン付きで売却ができる
- 月々の返済額を抑えられる
- フラット50で40年ローンを組むデメリット・注意点
- フラット35よりも金利が高い傾向がある
- 取り扱い金融機関が少ない
- 「フラット35」や「フラット20」と併用する場合は諸費用が多くかかる
- 支払総額(利息)が増える
- フラット50の40年ローンで後悔しないためのポイント
- 完済時の年齢を把握して老後返済リスクを考える
- 計画的な繰り上げ返済を検討する
- 団信の保障内容をしっかり確認する
- 【まとめ】40年ローンを検討する際は将来を見据えて慎重な判断を
フラット35で40年ローンは組める?
住宅ローンを検討する際、「できるだけ返済期間を長くして月々の負担を軽くしたい」と考える方も多いのではないでしょうか。
そんな中で注目されるのが、フラット35の派生商品である「フラット50」です。通常のフラット35では最長35年の返済期間ですが、条件を満たせば最大40年のローンを組むことも可能です。
まずは、フラット50を利用して40年ローンを組むための前提条件を、以下の3つのポイントから解説します。
- 前提【フラット50】で返済期間を40年に設定する条件
- 条件① 申込時の年齢が満44歳未満
- 条件② 長期優良住宅が対象
- 条件③ 借入額は物件価格の9割まで
これらの条件を満たすことで、より柔軟な資金計画が可能になります。長期ローンを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
前提【フラット50】で返済期間を40年に設定する
40年ローンを組むには、実は【フラット50】という別商品を活用する必要があります。
これは住宅金融支援機構が提供する最長50年の全期間固定金利型住宅ローンで、対象となるのは「長期優良住宅」に認定された物件です。
【フラット50】では、返済期間を36年〜50年の間で自由に設定できるため、40年ローンを希望する場合はこの商品を選択することで対応可能です。
金利は【フラット35】よりやや高めに設定される傾向がありますが、返済期間が長くなる分、月々の返済額を抑えられるメリットがあります。
ただし、【フラット50】単体では物件価格の9割までしか借入できないため、残りの1割を自己資金で補うか、【フラット35】や【フラット20】との併用で全額借入する方法もあります。
条件① 申込時の年齢が満44歳未満
【フラット50】で40年ローンを組むには、申込時の年齢が満44歳未満であることが基本条件です。
これは、返済期間が最長50年に設定できる制度の特性上、完済時の年齢が80歳未満となるように設計されているためです。
ただし、例外として「親子リレー返済」を利用する場合は、申込者が44歳以上でも申し込み可能です。この制度では、親子2世代で返済を行うため、後継者の年齢を基準に返済期間を設定できます。
条件② 長期優良住宅が対象
【フラット50】で40年ローンを組むには、対象物件が長期優良住宅であることが必須条件です。長期優良住宅とは、国が定めた基準を満たし、所管行政庁から認定を受けた住宅のことを指します。
耐久性・省エネ性・維持管理のしやすさなど、長く快適に住み続けられる性能を備えているのが特徴です。
この制度は、住宅の質を高め、資産価値を維持しやすくすることを目的としており、【フラット50】のような長期ローンとの相性も抜群です。
【フラット50】の対象となる住宅基準(一例)
| 基準項目 | 内容の概要 |
|---|---|
| 耐久性 | 劣化対策等級3級相当の仕様 |
| 耐震性 | 耐震等級2級以上または免震構造 |
| 維持管理・更新の容易性 | 配管の点検・清掃・交換がしやすい設計 |
| 可変性(共同住宅) | 馬鳥変更が容易な構造 |
| バリアフリー性 | 将来的なバリアフリーに回収できる設計 |
| 省エネルギー性 | 断熱性能等級4級以上など、省エネ基準を満たす |
| 居住環境への配慮 | 地域の景観や住環境に配慮した設計 |
| 維持保全計画 | 定期点検・補修の計画が策定されていること |
条件③ 借入額は物件価格の9割まで
【フラット50】では、借入額の上限が物件価格の9割までと定められており、原則として頭金が1割以上必要です。
これは長期優良住宅を対象とした制度であり、住宅の資産価値や返済能力を重視する設計となっています。
ただし、自己資金が不足している場合でも、【フラット35】または【フラット20】を併用することで、物件価格の全額まで借入可能な組み合わせが可能です。これにより、頭金なしでの購入も選択肢に入りますが、金利や返済負担率には注意が必要です。
【フラット50】と組み合わせ可能な商品・特約一覧(概要)
| 商品・特約名 | 概要・特徴 |
|---|---|
| 【フラット35】 | 最長35年の固定金利。併用で物件価格までの借入が可能 |
| 【フラット20】 | 最長20年の固定金利。短期返済で金利を押さえたい場合に有効 |
| 【フラット35】S | 長期有料住宅など高性能住宅向け。金利引き下げあり(当初5年など) |
| 【フラット35】維持保全型 | 維持管理・保全計画がある住宅向け。金利引き下げあり |
| 【フラット35】リフォーム一体型 | 中古住宅+リフォーム費用をまとめて借入可能 |
| 【フラット35】子育てプラス | 子育て世帯・若年夫婦世帯向け。ポイント制で金利引き下げ |
| 【フラット35】地域連携型 | 地方自治体の補助制度と連携。金利引き下げ+補助金の併用が可能 |
フラット35のお悩みは無料FP相談を活用しよう

住宅ローンは人生で最も大きな借り入れのひとつです。特に【フラット35】は固定金利で安心感がある一方、金利の選び方や返済期間の設定、他ローンとの併用など、悩みや疑問が尽きません。
そんなときこそ、無料で何度でも相談できるFPサービス「マネーキャリア」の活用がおすすめです。
マネーキャリアはこんな方におすすめ!
- フラット35の金利や返済期間で迷っている
- フラット50や併用ローンの仕組みがよくわからない
- 自分に合った住宅ローンの選び方を知りたい
- 将来のライフプランとローン返済のバランスを相談したい

フラット50で40年ローンを組むメリット
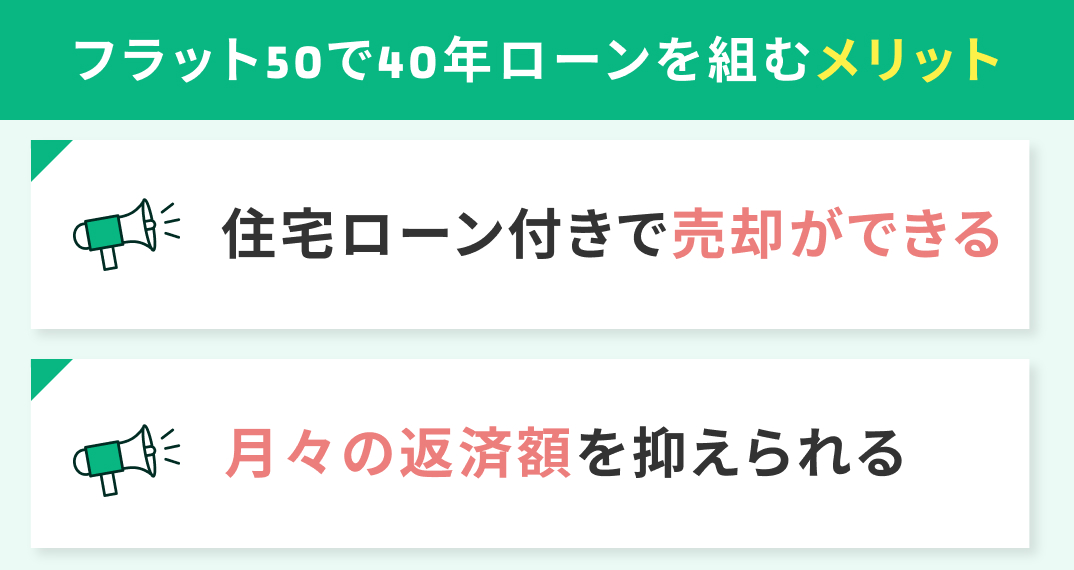
フラット50を活用して40年ローンを組むことで、住宅購入の選択肢が広がるだけでなく、資金計画にも柔軟性が生まれます。特に、長期返済による月々の負担軽減や、将来的な資産活用の面でメリットを感じる人も多いでしょう。
ここでは、フラット50で40年ローンを組むことで得られる主なメリットを、以下の2つの視点から紹介します。
- 住宅ローン付きで売却ができる
- 月々の返済額を抑えられる
長期ローンの活用は、ライフプランに合わせた住まい選びや資金管理において、非常に有効な手段となります。自分に合ったローンの組み方を考える参考にしてみてください。
住宅ローン付きで売却ができる
【フラット50】には、返済中の住宅を売却する際に、購入者がそのままローンを引き継げる「金利引継特約」が用意されています。これは、住宅ローンの残債を完済せずに売却できる仕組みで、売主・買主双方にメリットがある制度です。
金利引継特約のポイントまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 【フラット50】で借入した長期優良住宅 |
| 引き継ぎ条件 | 購入者の同意+住宅金融支援機構の審査 |
| メリット(売主) | ローン完済不要で売却可能。金利の低さが物件の魅力に |
| メリット(買主) | 市場金利より低い金利でローンを引き継げる可能性あり |
| 注意点 | 抵当権変更登記などの手続き・費用が必要 |
金利が上昇している局面では、既存の低金利ローンを引き継げることが買主にとって大きな魅力となり、売却しやすくなる可能性もあります
月々の返済額を抑えられる
【フラット50】を利用して40年ローンを組むことで、返済期間が長くなり、月々の返済額を抑えることが可能です。
以下は、借入金額6000万円・固定金利1.5%・元利均等返済・頭金なし・ボーナス返済なしという条件で、【フラット35】と【フラット50】の返済額と返済負担率を比較した例です。
| 項目 | フラット35(35年) | フラット50(40年) |
|---|---|---|
| 借入金額 | 6000万円 | 6000万円 |
| 返済期間 | 35年(420カ月) | 40年(480カ月) |
| 毎月返済額 | 約183,711円 | 約165,094円 |
| 年間返済額 | 約2,204,532円 | 約1,981,128円 |
| 総返済額 | 約77,158,479円 | 約79,245,504円 |
| 返済負担率(手取り800万) | 約27.5% | 約24.8% |
フラット50で40年ローンを組むデメリット・注意点
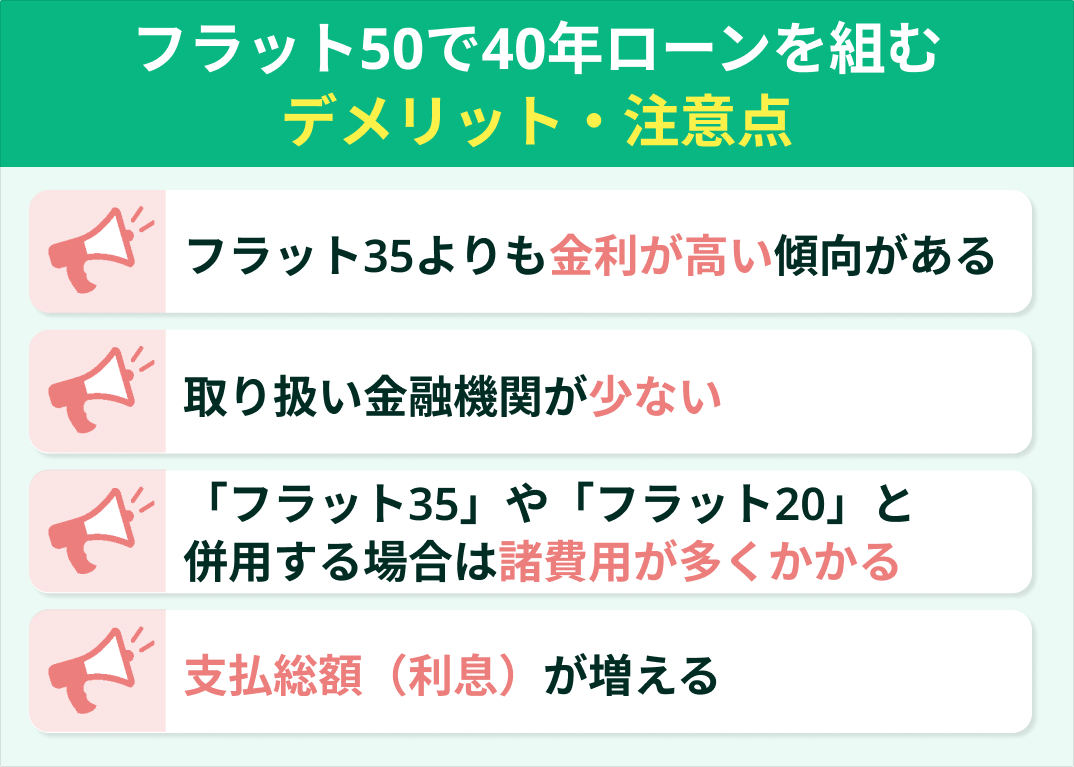
フラット50を利用して40年ローンを組むことで、月々の返済負担を軽減できる一方で、注意すべき点もいくつかあります。
特に、金利や取り扱い金融機関の少なさ、諸費用の増加など、フラット35とは異なるデメリットが存在します。長期ローンを検討する際は、こうしたポイントを事前に理解しておくことが重要です。
ここからは、フラット50で40年ローンを組む際に知っておきたいデメリットや注意点を、以下の4つの視点から解説します。
- フラット35よりも金利が高い傾向がある
- 取り扱い金融機関が少ない
- 「フラット35」や「フラット20」と併用する場合は諸費用が多くかかる
- 支払総額(利息)が増える
長期ローンのメリットだけでなく、リスクやコスト面も踏まえたうえで、納得のいく住宅購入を目指しましょう。
フラット35よりも金利が高い傾向がある
【フラット50】は返済期間が最長50年と長いため、同じ固定金利型でも【フラット35】より金利が高めに設定される傾向があります。2025年7月時点の最新金利を比較すると、以下のようになります。
フラット35・フラット50の金利比較(2025年7月)
| 項目 | フラット35(21年~35年) | フラット50(36~50年) |
|---|---|---|
| 融資率9割以下の最頻金利 | 年1.840% | 年1.940% |
| 融資率9割超の最頻金利 | 年1.950% | 年2.050% |
| 金利の範囲(9割以下) | 年1.840%~3.970% | 年1.940%~2.410% |
| 金利の範囲(9割超) | 年1.950%~4.080% | 年2.050%~2.520% |
フラット50は返済期間が長いため、月々の返済額を抑えられるメリットがありますが、その分総返済額は増加しやすく、金利も高めになります。
取り扱い金融機関が少ない
【フラット50】は【フラット35】や【フラット20】と比べて、取り扱い金融機関が限られている点に注意が必要です。これは、【フラット50】が長期優良住宅を対象とした特殊な商品であり、対応できる金融機関が少ないためです。
商品別・全国の取り扱い金融機関数(新規・融資率9割以下)
| 商品タイプ | 取扱件数(全国) |
|---|---|
| フラット35 | 約330件 |
| フラット20 | 約310件 |
| フラット50 | 約90件 |
【フラット50】は取り扱い件数がフラット35の約3割程度にとどまり、選べる金融機関が限られます。そのため、金利や手数料の比較がしづらく、選択肢の幅が狭くなる可能性があります。
また、【フラット50】を利用する場合は、【フラット35】や【フラット20】との併用が必要になるケースもあるため、同一金融機関での取り扱いがあるか事前確認が必須です。
「フラット35」や「フラット20」と併用する場合は諸費用が多くかかる
【フラット50】は物件価格の9割までしか借入できないため、残りの1割を補う目的で【フラット35】や【フラット20】との併用が可能です。ただし、契約商品が増えることで諸費用も増加する点には注意が必要です。
併用時に増える主な諸費用
| 費用項目 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 抵当権設定費用 | 各ローンに対して登記が必要。登録免許税や司法書士報酬が2契約分発生する可能性あり |
| 印紙税 | 契約書が2通になるため、印紙代も2契約分必要 |
| 物件検査手数料 | 適合証明取得のための検査費用が商品ごとに発生する場合あり |
| 火災保険料 | 保険金額や質権設定の条件が異なる場合、調整が必要 |
| 融資手数料 | 記入期間よっては商品ごとに手数料が設定されることもある |
併用することで借入額の柔軟性は高まりますが、契約が複数になることで手続きや費用が煩雑になる点は見落としがちです。特に初期費用を抑えたい方は、融資手数料のタイプや登記費用の見積もりを事前に確認しておくことが重要です。
支払総額(利息)が増える
40年ローンは月々の返済額を抑えられる一方で、支払総額(利息)が増えるというデメリットがあります。以下は、借入金額6000万円・固定金利・元利均等返済・頭金なし・ボーナス返済なしという条件で、【フラット35】(35年)と【フラット50】(40年)を比較した例です。
<支払総額・利息比較表(2025年7月時点の金利)>
| 項目 | フラット35(35年) | フラット50(40年) |
|---|---|---|
| 借入金額 | 6000万円 | 6000万円 |
| 金利 | 年1.840% | 年1.940% |
| 毎月返済額 | 約183,711円 | 約165,094円 |
| 総返済額 | 約77,158,479円 | 約79,245,504円 |
| 利息総額 | 約17,158,479円 | 約19,245,504円 |
40年ローンにすることで、月々の返済額は約1.9万円減少し、返済負担率も抑えられます。しかしその分、利息負担は約210万円増加し、総返済額も大きくなります。完済時の年齢が高くなる点も含め、長期ローンは慎重な検討が必要です。
フラット50の40年ローンで後悔しないためのポイント
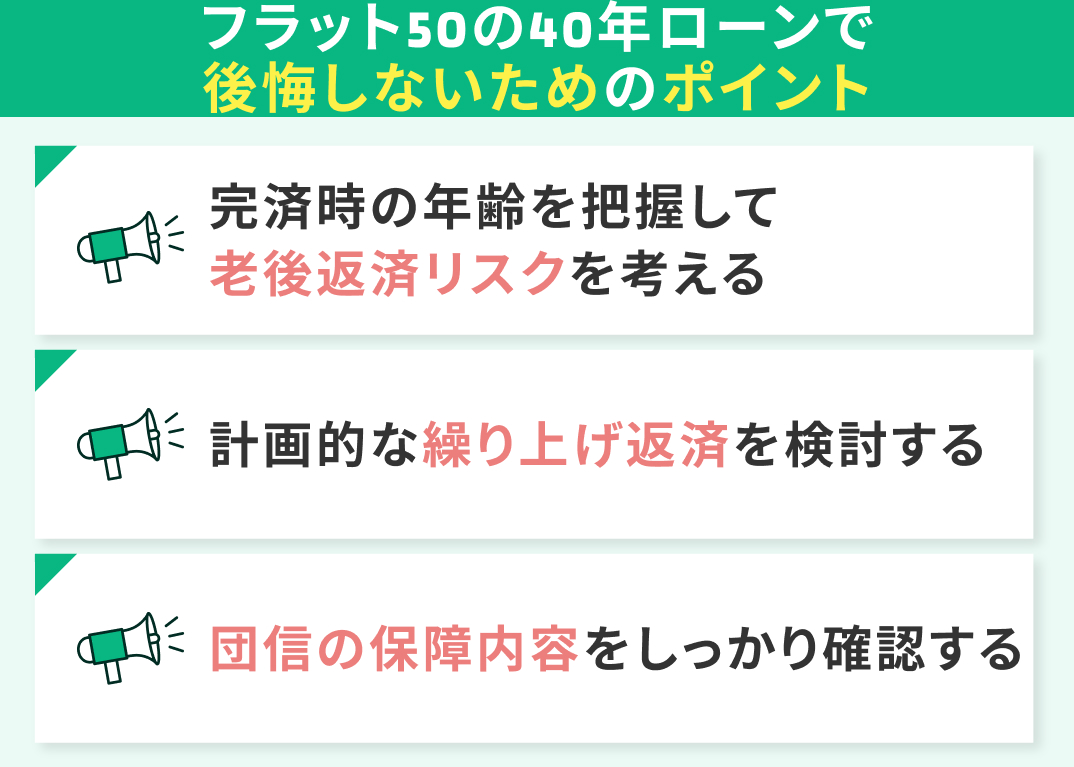
フラット50を利用して40年ローンを組むことで、月々の返済負担を軽減できる一方、長期にわたる返済には慎重な計画が欠かせません。
特に、老後の生活や予期せぬライフイベントに備えるためには、後悔しないための視点を持ってローン設計をすることが重要です。
ここでは、フラット50の40年ローンを安心して活用するために意識したいポイントを、以下の3つの視点から紹介します。
- 完済時の年齢を把握して老後返済リスクを考える
- 計画的な繰り上げ返済を検討する
- 団信の保障内容をしっかり確認する
長期ローンだからこそ、将来を見据えた備えが必要です。後悔のない住宅購入を実現するために、ぜひ参考にしてください。
完済時の年齢を把握して老後返済リスクを考える
【フラット50】で40年ローンを組む場合、完済時の年齢が高くなることによる老後返済リスクをしっかり認識しておく必要があります。仮に現在35歳でローンを開始すると、繰上げ返済をしない限り完済は75歳。これは定年退職後も返済が続く可能性が高いことを意味します。
<老後返済リスクのポイント>
・収入減少期に返済が残る
→定年後は年金収入が中心となり、現役時代よりも収入が減少するため、返済負担が重く感じられる可能性あり
・退職金の使い方が重要
→退職金で一括返済する選択肢もあるが、老後資金とのバランスを考慮する必要がある
・年金収入での返済シミュレーションが必須
→年金額や生活費を踏まえ、返済が継続可能かを事前に確認することが重要
<シミュレーション例(仮定:借入6000万円・金利1.940%・元利均等返済)>
| 年齢 | 月々返済額 | 年金収入(目安) | 生活費(目安) | 返済可能性 |
|---|---|---|---|---|
| 65歳 | 約165,094円 | 約200,000円 | 約250,000円 | △(赤字) |
| 70歳 | 約165,094円 | 約180,000円 | 約220,000円 | △(赤字) |
※年金収入は厚生年金+企業年金の平均的な目安。生活費は総務省統計を参考にした夫婦世帯の平均。
計画的な繰り上げ返済を検討する
住宅ローンの返済負担を軽減する手段として有効なのが繰り上げ返済です。特に「期間短縮型」の繰り上げ返済を選ぶことで、総支払利息を大幅に削減でき、完済時期を早めることが可能になります。
これは定年退職前の完済を目指す人にとって、老後の安心につながる重要な選択肢です。 ただし、繰り上げ返済には注意点もあります。
貯蓄とのバランスを崩すと、教育費や緊急支出に対応できなくなるリスクもあるため、無理のない範囲で計画的に進めることが大切です。
繰り上げ返済は「早く返す=得」ではなく、家計全体のキャッシュフローとライフイベントを見据えた戦略的な判断が必要です。
団信の保障内容をしっかり確認する
住宅ローンを契約する際に加入する団体信用生命保険(団信)は、万が一の際にローン残高を肩代わりしてくれる重要な保障です。
ただし、団信の保障内容は金融機関や商品によって異なり、死亡・高度障害のみを対象とする一般団信から、がん・三大疾病・就業不能までカバーする特約付き団信まで幅広く存在します。
団信は住宅ローン返済の安心材料になりますが、保障範囲が限定的な場合もあるため、内容の確認は必須です。特に、死亡保障のみの団信では、病気やケガによる就業不能時の収入減には対応できません。
そのため、保障に不安を感じる場合は、民間の生命保険や就業不能保険との併用を検討するのが現実的です。
【まとめ】40年ローンを検討する際は将来を見据えて慎重な判断を

40年ローンを組む方法、そのメリット、デメリットなどを解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
40年ローンは月々の返済負担を軽減できる一方で、総返済額の増加や老後の生活への影響といったリスクも伴います。 特に定年後も返済が続く可能性があるため、完済時期や老後資金とのバランスを慎重に見極める必要があります。
繰上返済や資産運用を前提とした計画が立てられるかどうかが、成功の分岐点となるでしょう。住宅購入は「家を持つこと」ではなく、「自分らしい老後を送るための生活設計」の一部です。焦らず、見栄に流されず、冷静な判断を心がけましょう。
マネーキャリアでは、住宅ローンに詳しいファイナンシャルプランナーが、あなたの収支やライフプランを踏まえて40年ローンの可否を中立的な立場でアドバイスしてくれます。
「借りられるか」ではなく「返せるか」を一緒に考える。 将来の安心のために、今こそプロの力を借りてみませんか?






























