

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 養老保険はおすすめしないと言われる理由は?
- 保険料が高い
- 運用利回りが低い
- 解約返戻金が少ない
- 目的が曖昧になりやすい
- 養老保険はおすすめしない?と不安な方は無料FP相談を活用しよう
- 実際どうだった?養老保険の加入者に聞いた満足度調査
- 養老保険に加入してよかったと思う点は何ですか?
- 養老保険に加入して後悔した点・不満に思った点はありますか?
- 養老保険を家族や友人におすすめしたいと思いますか?
- これから養老保険に加入する方にアドバイスがあれば教えてください
- 養老保険がおすすめな人の特徴
- 確実に満期金を受け取りたい人
- 万が一の保障と貯蓄を同時に求める人
- 計画的にお金を積み立てたい人
- 投資やリスクを取りたくない人
- 養老保険がおすすめでない人の特徴
- コストパフォーマンスを重視したい人
- 高い運用利回りを求める人
- 途中で解約する可能性がある人
- 保障と貯蓄を分けて考えたい人
- ライフプランの変化が多い人
- 【まとめ】養老保険はおすすめしないといわれる理由とは?
養老保険はおすすめしないと言われる理由は?
養老保険は死亡保障と貯蓄機能を兼ね備えた保険商品として人気がありますが、近年は「おすすめしない」という声も多く聞かれます。
おすすめしないといわれる理由は、以下のとおりです。
- 保険料が高い
- 運用利回りが低い
- 解約返戻金が少ない
- 目的が曖昧になりやすい
なぜこうした声が増えているのか、項目ごとに詳しく掘り下げてみましょう。
保険料が高い
養老保険の最大のデメリットは、他の生命保険商品と比較して保険料が非常に高額になることです。同じ死亡保障額で比較した場合、掛け捨て型の定期保険と養老保険では、以下のように保険料に大きな差が生まれます。
| 保険種類 | 月額保険料の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 定期保険 | 3,000円程度 | ・掛け捨て型 ・保障のみ |
| 養老保険 | 2~3万円程度 | ・満期金あり ・貯蓄性があるため高額 |
35歳男性が1,000万円の死亡保障を得る場合、定期保険なら月額3,000円程度で加入できます。一方で、養老保険では月額2〜3万円ほどかかるケースもあります。この価格差は、養老保険が死亡保障に加えて満期保険金の支払いも含んでいるためです。
運用利回りが低い
養老保険の貯蓄部分における運用利回りの低さは、現在の金融環境では深刻な問題です。多くの養老保険商品で設定されている予定利率は0.25%から1%程度と、銀行の定期預金とほぼ同水準か、それを下回る場合もあります。
1990年代のバブル期には5%※1を超える予定利率も設定されていましたが、長期にわたる低金利政策の影響で大幅に低下しました。低い運用利回りでは、インフレ率を考慮すると実質的にお金の価値が目減りしてしまう可能性があります。
たとえば年率2%のインフレが続く環境で、養老保険の予定利率が0.5%だった場合、実質的には年率1.5%ずつ資産価値が減少します。20年間で500万円を積み立てても、満期時の受取額は物価上昇を考慮すると、実質的に目減りしている計算です。
解約返戻金が少ない
養老保険を契約期間途中で解約した場合に受け取れる解約返戻金は、支払った保険料の総額を大幅に下回ることが一般的です。とくに契約から数年以内の早期解約では、元本の50%以下しか戻ってこないケースも珍しくありません。
早期解約で元本が戻らない理由は以下のとおりです。
- 保険会社の初期費用
- 営業職員への手数料
- 事務処理費用
これらの費用が保険料から差し引かれるため、解約後受け取れる金額が非常に少なくなります。
具体例として、月額3万円の保険料を5年間支払い続けた場合、総額180万円を拠出したことになります。しかし、5年目に解約した際の解約返戻金が90万円程度になることもあり、90万円もの損失になる計算です。さらに、解約返戻金の増加ペースは契約後期になるほど緩やかになるため、満期直前でも解約により元本割れするケースもあります。
目的が曖昧になりやすい
養老保険は保障と貯蓄の両方を兼ね備えていますが、それぞれの機能が中途半端になりがちです。死亡保障が主目的であれば、同じ保険金額でも定期保険なら月額数千円で済むところ、養老保険では数万円の保険料が必要です。
一方、貯蓄が主目的なら、銀行預金や投資信託の方が効率的に資産を増やせます。具体例として月額3万円の養老保険に加入、定期保険(月額5,000円)と投資信託の積立(月額2万5,000円)のケースを考えてみましょう。
| 比較項目 | 養老保険のみ | 定期保険+投資信託 (年率3%) | 定期保険+投資信託 (年率5%) |
|---|---|---|---|
| 保険料内訳 | 月額30,000円 (全額保険) | ・定期保険:月額5,000円
・投資信託:月額25,000円 | ・定期保険:月額5,000円
・投資信託:月額25,000円 |
| 死亡保障額 | 1,000万円(固定) | 1,000万円 (定期保険による) | 1,000万円 (定期保険による) |
| 20年後の資産価値 | 満期金:約750万円
(月額3万円×12か月×20年=720万円+利息) | 投資残高:約765万円
(月額2.5万円×240回、年3%複利) | 投資残高:約1,037万円 (月額2.5万円×240回、年5%複利) |
| 総合資産 (死亡保障除く) | 750万円 | 765万円 | 1,037万円 |
投資信託なら年率3%から5%のリターンも期待でき、20年後には養老保険の満期保険金を大幅に上回る資産形成も可能です。
養老保険はおすすめしない?と不安な方は無料FP相談を活用しよう

養老保険の加入を検討している方や、現在加入中だが本当に自分に適しているか迷っている方は、FPの無料相談を活用しましょう。
保険選びは個人の収入・家族構成・将来設計によって最適解が大きく変わるため、専門家の客観的なアドバイスが欠かせません。
FPは保険商品だけでなく、税制優遇制度や投資商品についても幅広い知識を持っています。そのため、養老保険以外の選択肢も含めて、あなたのライフプランにもっとも適した資産形成方法を提案してくれるでしょう。

実際どうだった?養老保険の加入者に聞いた満足度調査
ここでは、養老保険の加入者を対象に、以下の質問について調査しました。
- 養老保険に加入してよかったと思う点は何ですか?
- 養老保険に加入して後悔した点・不満に思った点はありますか?
- 養老保険を家族や友人におすすめしたいと思いますか?
- これから養老保険に加入する方にアドバイスがあれば教えてください
現役FPがそれぞれの回答を解説しているので、迷っている方はぜひ参考にしてください。
※2025年6月9日~2025年6月12日時点での当編集部独自調査による
※商品やサービスに関する内容は回答時点での内容のためご了承ください。
養老保険に加入してよかったと思う点は何ですか?

養老保険に加入して後悔した点・不満に思った点はありますか?

養老保険を家族や友人におすすめしたいと思いますか?

これから養老保険に加入する方にアドバイスがあれば教えてください
老後の備えや万が一の保障、さらには将来の資金づくりのために「養老保険」を検討する方が増えています。保障と貯蓄を兼ね備えている点は魅力です。
ただし、仕組みやコストを正しく理解していなければ「思っていた内容と違った」というミスマッチも起こり得ます。今回は、実際に養老保険に関心を持ち、比較検討した方々から寄せられたアドバイスをご紹介します。
加入を考えている方は、自分に合った保険を選ぶうえでのヒントにしてください。

40代男性
養老保険のメリットとデメリットを理解

30代男性
目的を明確にする
加入する前に、本当に自分の目的に合っているかをよく考えてください。貯蓄が目的なら、NISAなど他の選択肢と比較して、利回りの低さやインフレリスクを許容できるか検討すべきです。保障が目的なら、掛け捨ての保険の方が安価です。両方の機能を中途半端に併せ持つ商品だと理解したうえで、慎重に判断することをおすすめします。

40代女性
自分に合う保険を選ぶ
養老保険にはさまざまなプランが用意されており、保障内容や満期返戻金の額なども異なります。そのため、自分や家族のライフスタイルや将来設計に合った内容を選ぶことがとても重要です。保険に詳しい担当者に相談しながら、自分に最適なプランを見極めていくことをおすすめします。しっかり比較・検討すれば、納得のいく保険選びができるはずです。

50代女性
保険は分散がカギ
養老保険は保障と貯蓄の両面を兼ね備えた保険ですが、それだけに頼るのではなく、医療保険や掛け捨て保険、さらに預金や投資などと組み合わせて備えるのがおすすめです。万一に備えながら資産形成もすすめることで、安定したライフプランを築けます。リスクを分散させるという観点からも、複数の手段を上手に活用していきましょう。

50代女性
リスク許容度で選ぶ
養老保険はリスクを抑えながら貯蓄もできる点が魅力ですが、長期で運用できてリスクを取れる方には、投資信託の方が利回り面で有利な場合もあります。ただし、銀行預金よりは利率が良いため、リスクを避けたい方には選択肢として検討する価値があります。迷った場合は、FPなどの専門家に相談し、自分に合った資産形成方法を見つけましょう。
養老保険がおすすめな人の特徴
養老保険は決して万人におすすめできる商品ではありませんが、特定のニーズや価値観を持つ方には適している場合があります。
養老保険をおすすめできる人の特徴は、以下のとおりです。
- 確実に満期金を受け取りたい人
- 万が一の保障と貯蓄を同時に求める人
- 計画的にお金を積み立てたい人
- 投資やリスクを取りたくない人
ここでは、養老保険が向いている人の具体的な特徴を詳しく解説していきます。
確実に満期金を受け取りたい人
養老保険は、満期まで契約を継続すれば必ず満期保険金を受け取れるため、確実性を最重視する方に適しています。投資信託や株式のような市場変動リスクがなく、契約時に将来受け取れる金額が明確に決まっているためです。
たとえば、子どもの大学進学費用として18年後に300万円が必要な場合、養老保険なら確実に資金を準備できます。銀行預金との違いは、万が一の死亡時にも同額の保険金が支払われる点です。預金では積立途中で死亡した場合、それまでの貯蓄額しか残せませんが、養老保険なら目標額の満額を遺族に残せます。
また、保険料の自動引き落としにより強制的に積立が継続されるため、つい使ってしまいがちな方でも確実に資金を貯められます。
万が一の保障と貯蓄を同時に求める人
死亡保障と貯蓄機能を一つの契約でまとめたい方には、養老保険が適している場合があります。限られた家計予算の中で両方のニーズを満たしたい方や、保険契約の管理を簡素化したい方におすすめです。
たとえば、月3万円の予算で死亡保障500万円と将来の貯蓄を同時に準備したい場合、養老保険なら一つの契約で両方を実現できます。子育て世帯では、この特徴が活かされるでしょう。
保険期間を18年にすれば、満期時に大学進学費用として資金を受け取れます。さらに、万が一にも備えられるのが養老保険の特長です。
計画的にお金を積み立てたい人
自分ではなかなか貯蓄が続かない方や、強制的に積立をしたい方には養老保険が有効です。毎月決まった日に保険料が自動的に引き落とされるため、意志の力に頼らずに確実に資金を積み立てられます。
「お金があるとつい使ってしまう」「貯蓄口座に手をつけてしまう」という悩みを持つ方におすすめです。養老保険の積立は、途中で資金を引き出すには解約手続きが必要で、解約返戻金は元本割れするケースが多いため、心理的な抑制効果が働きます。衝動的な支出を防ぐ効果的な仕組みといえるでしょう。
投資やリスクを取りたくない人
元本割れリスクのある投資信託や株式投資に不安を感じ、堅実な資産形成を望む方には養老保険が適している場合があります。養老保険は契約時に満期保険金額が確定しており、約束された金額が受け取り可能です。
「投資は怖い」「元本は絶対に減らしたくない」という保守的な価値観を持つ方にとって、この安全性は大きな安心材料です。とくに退職金や相続財産など、損失を避けたい大切な資金の運用先として、選ばれることも少なくありません。銀行預金よりやや高い利回りに加え、死亡保障もあるため、安全性とリターンを両立したい方に適しています。
養老保険がおすすめでない人の特徴

養老保険は特定のニーズには適していますが、以下の項目に該当する場合は最適な選択肢とはいえないでしょう。
- コストパフォーマンスを重視したい人
- 高い運用利回りを求める人
- 途中で解約する可能性がある人
- 保障と貯蓄を分けて考えたい人
- ライフプランの変化が多い人
※参考:金融庁:つみたてシミュレーション
コストパフォーマンスを重視したい人
同じ金額の死亡保障を得るなら、定期保険の方が養老保険よりも保険料がずっと安く済みます。そのため、コストパフォーマンスを重視する人には養老保険はあまり向いていません。
35歳男性が1,000万円の死亡保障を得る場合、定期保険なら月額3,000円程度で済むところ、養老保険では月額3万円以上かかることも珍しくありません。差額の内容を確認しましょう。
- 月額差額の計算
30,000円(養老保険)−3,000円(定期保険)=27,000円 - 年間差額の計算
27,000円×12か月=324,000円 - 20年間での差額総額
27,000円×12か月×20年=6,480,000円
差額の2万7,000円を20年間で計算すると、総額648万円もの違いが生まれます。この差額を自分で投資信託などに積み立てた場合、年率3%で運用できれば20年後には約886万円になる計算です。
高い運用利回りを求める人
養老保険の予定利率は現在0.25%から1%程度と非常に低く、資産を積極的に増やしたい方には物足りない水準です。一方、つみたてNISAを活用した投資信託では、年率4%から8%のリターンも十分期待できるため、高い運用利回りを求める方には投資信託やNISAなどの活用が適しています。
具体的な例として、月額3万円を20年間積み立てる場合を比較してみましょう。
| 比較項目 | 養老保険 (年0.25から1%程度※) | 投資信託 (年4%) |
|---|---|---|
| 20年後の受取額 | 約732万円 | 約1,098万円 |
| 払込総額 | 720万円 | 720万円 |
| 利益額 | 12万円 | 378万円 |
※参照:金融庁:つみたてシミュレーション
※参照:低金利時代に一時払い養老保険は利用すべき?保険の必要性やおすすめ商品を解説|アドバイザーナビ株式会社
養老保険の予定利率を0.5%とすると、20年後の受取額は約732万円になります。一方、年率4%で運用できる投資信託なら、同じ期間で約1,098万円となり、366万円もの差が生まれます。
この差額は、老後生活における大きな違いとなるでしょう。また、投資信託なら運用成果によってはさらに高いリターンも期待でき、分散投資によりリスクを抑えながら効率的な資産形成が可能です。
途中で解約する可能性がある人
養老保険は途中解約時の解約返戻金が支払った保険料を大幅に下回ることが多く、解約の可能性がある方には大きなリスクとなります。
早期に解約した場合、元本の半分以下しか返金されないケースも少なくありません。こうした返戻金の少なさは、契約当初に手数料や運営コストが差し引かれることが原因です。
以下のようなライフステージの変化により、資金が必要な人は注意が必要です。
- 急な転職
- 収入減少
- 家族の病気
- 住宅購入
さらに、養老保険は契約期間が長期にわたるため、途中で保険料の支払いが困難になるリスクも考慮しましょう。
保障と貯蓄を分けて考えたい人
死亡保障と資産形成を別々に最適化したい方には、養老保険の一体型の仕組みは中途半端に感じられるでしょう。目的ごとに最適な商品を選択した方が、それぞれの機能を最大限に活用できるからです。
死亡保障は定期保険で安く確保し、資産形成は投資信託やNISAで効率的に行うという分離戦略の方が合理的です。定期保険なら同じ保険料でより大きな保障額を設定でき、投資信託なら養老保険よりも高い運用利回りが期待できます。
分離戦略では必要に応じて保障額や積立額を調整できる柔軟性もメリットです。子どもの独立により死亡保障を減額したり、収入増加に合わせて積立額を増やしたりといった調整が容易になります。
ライフプランの変化が多い人
将来のライフプランが変わりやすい方には、20年から30年という長期間にわたって同じ条件で契約を続ける養老保険は不向きです。ライフステージの変化に応じて、必要な保障額や貯蓄目標は大きく変わりますが、養老保険では途中での条件変更が困難だからです。
たとえば、独身時代に養老保険に加入したものの、結婚・出産により教育費の準備が優先課題となった場合、養老保険では対応できません。また、転職により収入が変動した場合、保険料の支払いが負担になっても、解約すれば大きな損失を被ることになります。
このような状況では、柔軟に調整できる預金や投資信託の方が適しています。キャリアアップのための転職、独立開業、海外転勤などが予想される方も同様です。
【まとめ】養老保険はおすすめしないといわれる理由とは?

養老保険がおすすめしないと言われる主な理由は、保険料の高さ・運用利回りの低さ・解約時の元本割れリスク・目的の曖昧さ・税制メリットの限定性にあります。保障重視なら定期保険、運用重視なら新NISAなどが一般的に有利とされています。そのため、両方を備える養老保険は「中途半端」と感じる人も少なくありません。
ただし、確実性を重視し、保障と貯蓄を一体化したい方や強制的な積立を望む方には適している場合もあります。重要なのは、自分の価値観やライフプランに本当に適しているかを見極めることです。



























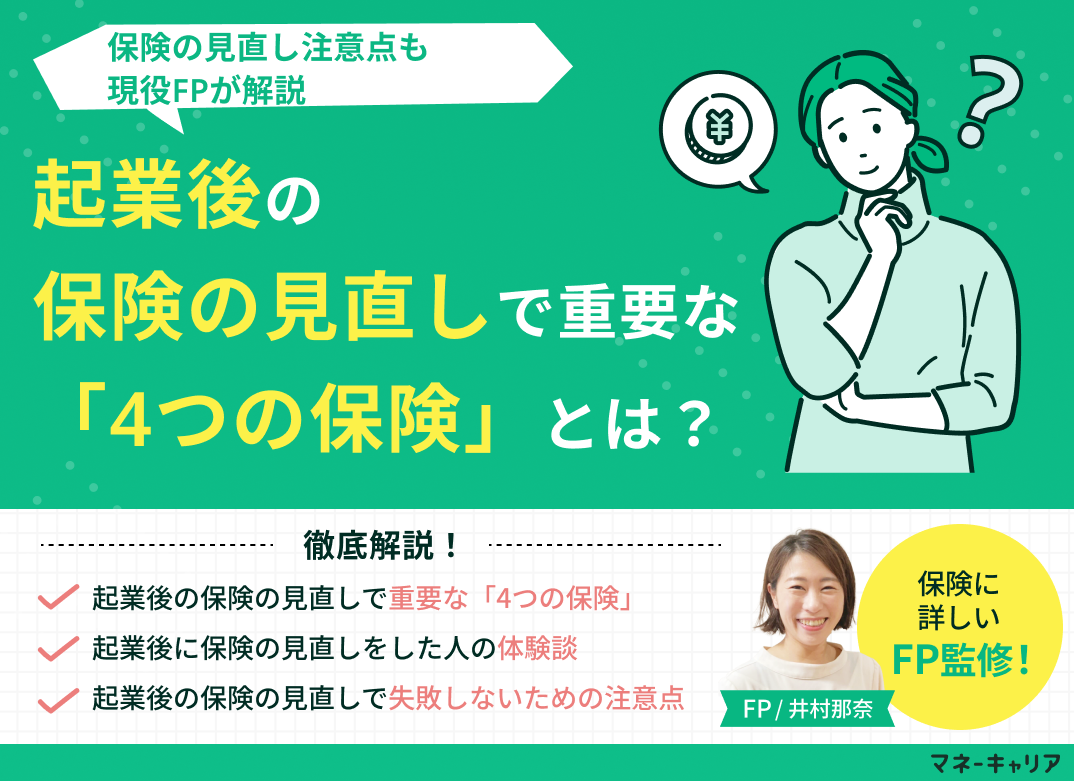

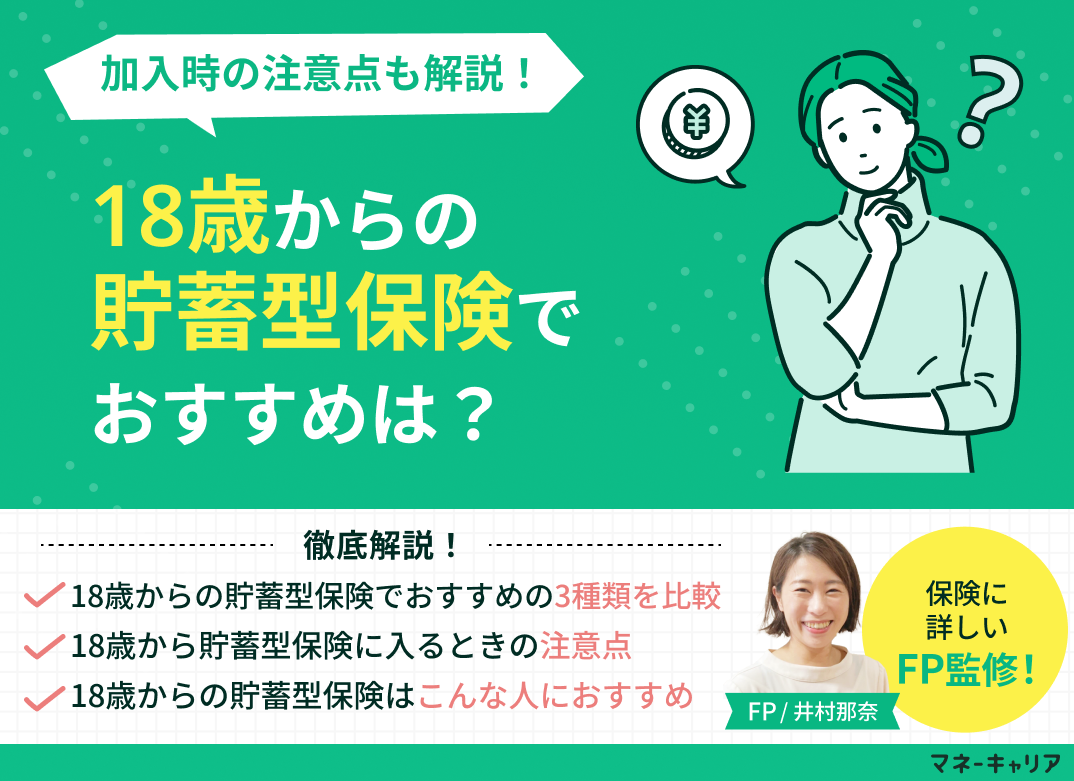
養老保険は手厚い保障に加えて、満期時の貯蓄性にも優れており、魅力的な保険です。ただし、他の保険に比べて毎月の保険料が高めになる傾向があります。加入を検討する際は、メリットとデメリットをよく理解し、自分のライフプランに合っているかをしっかり見極めることが大切です。計画的に選べば、将来の安心につながる良い選択になるでしょう。