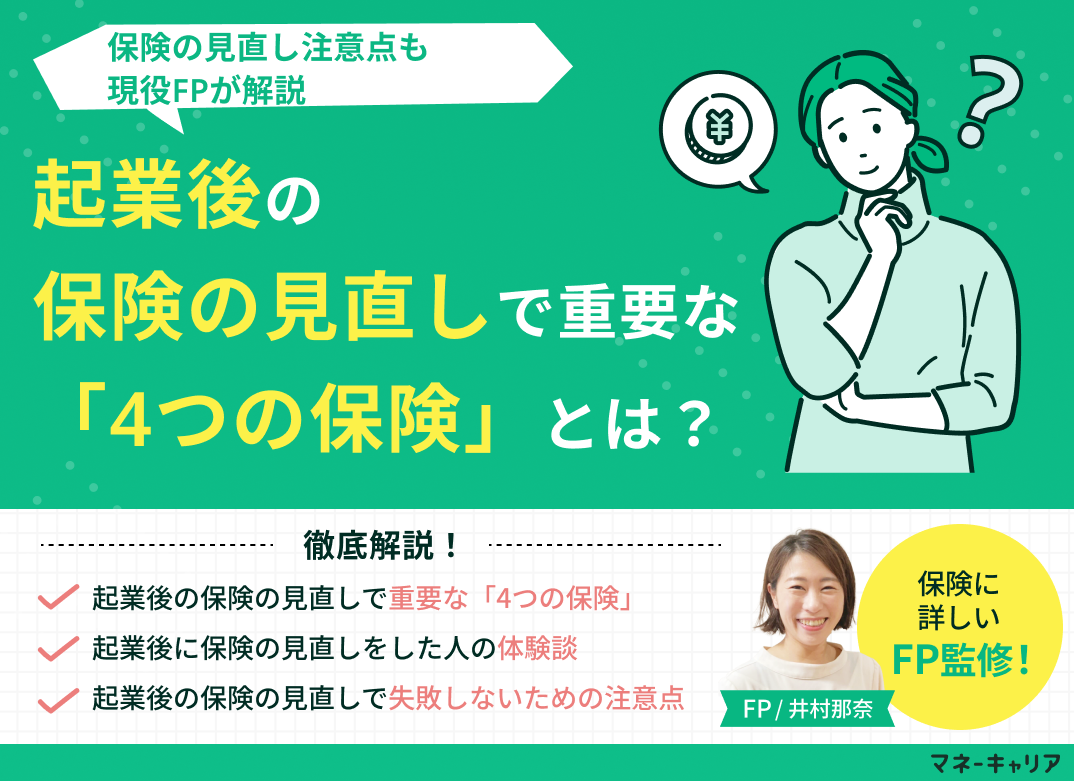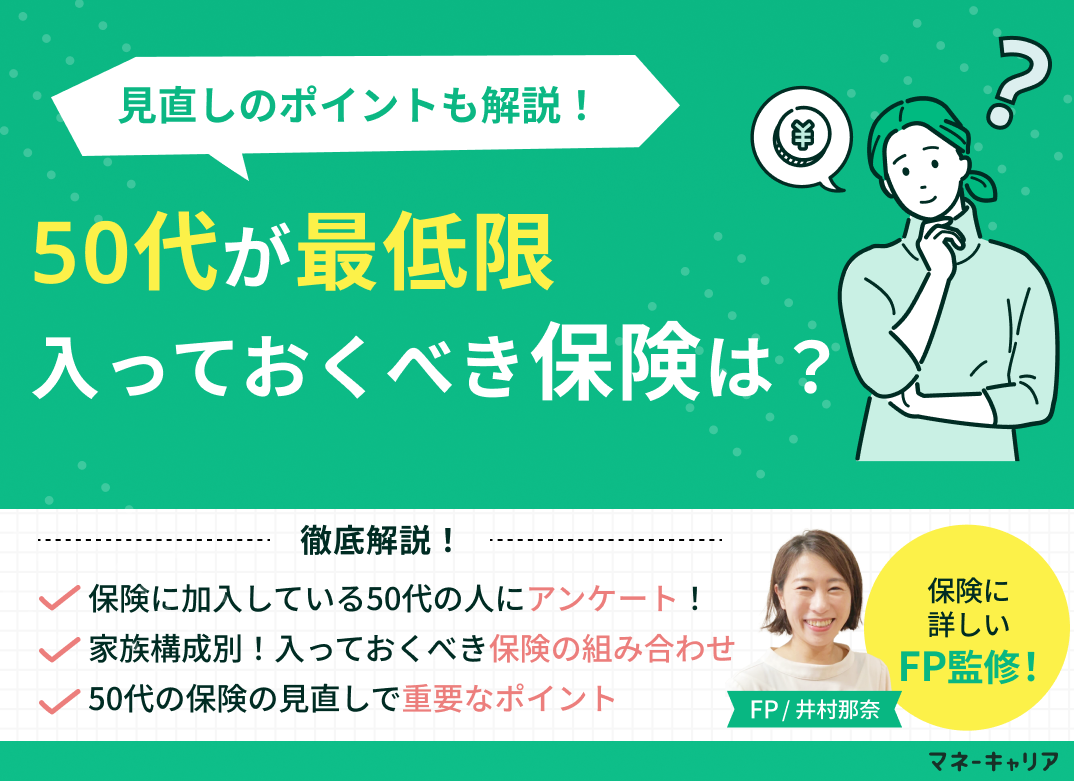- 生命保険の解約返戻金を受け取った後、税金が気になっている人
- 解約返戻金にどれくらいの税金がかかるか計算しておきたい人
- 一時所得や贈与税の確定申告について知りたい人

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 生命保険の解約返戻金の概要・課税について解説
- そもそも解約返戻金とは
- 解約返戻金にかかる税金の種類
- 解約返戻金に課税されない場合とは
- 生命保険解約時にかかる税金をシミュレーション
- 保険の支払総額が返戻金より高い場合
- 返戻金を契約者が受け取った場合
- 返戻金を契約者以外が受け取った場合
- 解約返戻金の税金で確定申告が必要な条件を紹介!
- 確定申告が不要な場合
- 確定申告が必要な場合
- 解約返戻金に関するよくある質問
- 解約返戻金の一時所得はいくらまで非課税?
- 解約返戻金で確定申告しないとどうなるの?
- 解約返戻金に関する質問・相談はマネーキャリアへ
- 解約返戻金に税金がかかる場合はシミュレーションが重要【まとめ】
生命保険の解約返戻金の概要・課税について解説

生命保険の解約返戻金について、知っておいたほうがいい知識は以下の3つです。
- そもそも解約返戻金とは
- 解約返戻金にかかる税金の種類
- 解約返戻金に課税されない場合とは
そもそも解約返戻金とは
そもそも解約返戻金とは、以下の2つのパターンの場合に返金されるお金です。
- 保険金を受け取らないまま保険を解約したとき
- 保険会社のほうから契約を解除したとき
保険は大きく以下の3つのタイプに分かれます。
| 保険のタイプ | 解約返戻金の特徴 |
|---|---|
| 無解約返戻金型 | 解約返戻金が0 |
| 解約返戻金型 | 払い込みとともに解約返戻金が増える 払い込みを終えると解約返戻金の伸び率がぐっと低くなる |
| 低解約返戻金型 または解約返戻金抑制型 | 払い込み中は解約返戻金が低額 払い込みを終えると解約返戻金が増える |
それぞれ特徴が異なるため、自分の保険商品がどのタイプなのか、保険証券を見て確認してみましょう。
解約返戻金にかかる税金の種類
生命保険の解約返戻金は基本的に所得税の対象ですが、場合によっては贈与税の対象となることもあります。
どちらの対象になるかは、保険の契約者と受け取った人が同一人物かどうかがポイントであり、簡潔のまとめると以下のようにあらわせます。
- 自分で払った保険を自分で受け取るのは所得(所得税の対象)
- 自分で払った保険を他の人が受け取るのは贈与(贈与税の対象)
解約返戻金に課税されない場合とは
解約返戻金を受け取っても、以下のいずれに該当する場合は非課税となります。
- 解約返戻金が支払保険料よりも少ないとき
- 契約者が受け取り、得た利益が50万円以下のとき
- 契約者以外が受け取り、解約返戻金が110万円以下のとき
生命保険解約時にかかる税金をシミュレーション

生命保険解約時にかかる税金を以下の3パターンでシミュレーションしていきます。
- 保険の支払総額が返戻金より高い場合
- 返戻金を契約者が受け取った場合
- 返戻金を契約者以外が受け取った場合
保険の支払総額が返戻金より高い場合
保険の支払総額が返戻金より高い場合は、利益が発生していないという考え方になります。
課税対象となる利益が0円なので、税金もかかりません。
具体的には、自分で契約した掛金総額300万円の生命保険を解約し、返戻金が200万円だった場合は、支払総額が返戻金よりも高いので税金がかからない計算です。
生命保険を解約する際は、まず自分の支払総額と解約返戻金の金額をチェックしましょう。
返戻金を契約者が受け取った場合
解約返戻金を契約者が受け取った場合は、一時所得として計算され、所得税を払うことになります。
一時所得の課税対象額は以下のように計算されます。
一時所得の課税対象額={(解約返戻金ー支払保険料)ー特別控除50万円}×1/2
具体的に、掛金総額480万円、解約返戻金600万円のケースでは以下の計算です。
{(600万円ー480万円)ー50万円}×1/2 =35万円
この35万円が他の所得と合算して、所得税の額が決定されます。
返戻金を契約者以外が受け取った場合
契約者以外が解約返戻金を受け取った場合は、贈与税の対象となり、贈与税は110万円の控除を受けられるので以下の計算になります。
贈与税対象額=解約返戻金ー110万円
具体的に、掛金総額480万円、解約返戻金600万円のケースで計算してみましょう。
600万円(解約返戻金)ー110万円(控除額)=490万円(課税対象額)
490万円×30%(税率)ー65万円(控除額)=82万円(贈与税の金額)
※参照:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
このように、同じ掛金総額、解約返戻金の金額であっても、受取人が違うと税金も大きく変わるので、しっかりシミュレーションをしつつ、受取人を決めることが大切です。
解約返戻金の税金で確定申告が必要な条件を紹介!

解約返戻金に税金がかかる場合、確定申告が必要なケースもあります。ここでは、以下の2点について解説します。
- 確定申告が不要な場合
- 確定申告が必要な場合
確定申告が不要な場合
確定申告が不要な場合は、以下の2つのケースです。
- 解約返戻金が一時所得にあたり、特定の条件を満たすとき
- 解約した保険が、源泉分離課税の対象となっているとき
| 勤め先の数 | 条件 |
|---|---|
| 1か所 | 給料と退職金以外の所得の合計が20万円以下 もしくは、給与と退職金以外の所得が他に無く、受け取った解約返戻金での利益が90万円以下 |
| 2か所 | 給料と退職金以外の所得が20万円以下 給与のすべてが源泉徴収されている 所得の合計から雑損所得、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各控除を差し引いた金額が150万円以下 |
確定申告が必要な場合
確定申告が必要なのは、基本的に給与と退職金以外の所得が解約返戻金の利益を含めて20万円以上になる場合です。
また、それ以外でも以下に当てはまる人も確定申告の必要があります。
- 給与が2,000万円超の人
- 源泉徴収なしで給与等の支払を受けている人
- 退職所得についての税額が、源泉徴収された金額よりも多い人
解約返戻金に関するよくある質問

解約返戻金に関してよく聞かれる以下の質問に回答していきます。
- 解約返戻金の一時所得はいくらまで非課税?
- 解約返戻金で確定申告しないとどうなるの?
解約返戻金の一時所得はいくらまで非課税?
まずひとつめの質問。
- 解約返戻金が一時所得のとき、いくらまでなら非課税?
これについては、税額のシミュレーションのところで解説した、一時所得の計算式を思い出してみましょう。
一時所得課税対象額={(返戻金の金額ー支払った保険料)ー特別控除50万円}×1/2
一般の会社員の場合、給料と退職金以外の所得の合計が50万円以内は税金がかかりません。
理由として、50万円までの利益については特別控除で全額差し引かれるからです。
解約返戻金で確定申告しないとどうなるの?
では、もう一つの質問。
- もし確定申告が必要なのにしなかった場合、どうなるの?
保険金については、保険会社のほうから税務署へ、支払調書という書類が提出されます。
これは、ある金額以上の保険金や解約返戻金の支払先や金額を記載した書類。
つまり受取人が確定申告の期限である3月15日までに申告しなかった場合は、保険会社からの情報を照合して、無申告であることがばれてしまうのです。
そして、無申告には、ペナルティとして無申告加算税という税金が上乗せされてしまいます。
無申告加算税は、本来申告すべきだった税額に対し、
- 納税額が50万円まで:15%
- 50万円~300万円:20%
- 300万円超の部分:30%
というように、最大で納税額の30%が加算されるという厳しいもの。
税額のシミュレーションを思い出してください。
あの金額にさらに上乗せされると思うと、かなりの負担になってしまいますね。
もし、確定申告の期限の3月15日を過ぎてから、無申告に気づいた場合はすぐに申告しましょう。
No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)をみると、期限から1か月以内に自主的に申告した場合は、無申告加算税は課されないことになっています。
かならず、4月15日までに申告を行いましょう。
解約返戻金に関する質問・相談はマネーキャリアへ

解約返戻金に関して、確定申告や解約返戻金の使い道についてのお悩みを持っている人は多いです。
- 実績豊富なお金のプロ(FP)が個別に相談を聞いてくれる
- お金の専門家(FP)が複雑な仕組みを分かりやすく解説してくれる
- 無料で何度でも相談可能
- 相談実績100,000件以上、相談満足度98.6%の信頼と実績がある
解約返戻金に税金がかかる場合はシミュレーションが重要【まとめ】

解約返戻金は、生命保険を何らかの理由で解約した場合に手元に返ってくるお金です。
しかし、保険の支払総額よりも解約返戻金のほうが高い場合は所得税、または贈与税の支払いが発生します。
所得税と贈与税、どちらの対象になるかは以下の点によって変わります。
- 所得税:契約者と受取人が同一の場合
- 贈与税:契約者と受取人が異なる場合