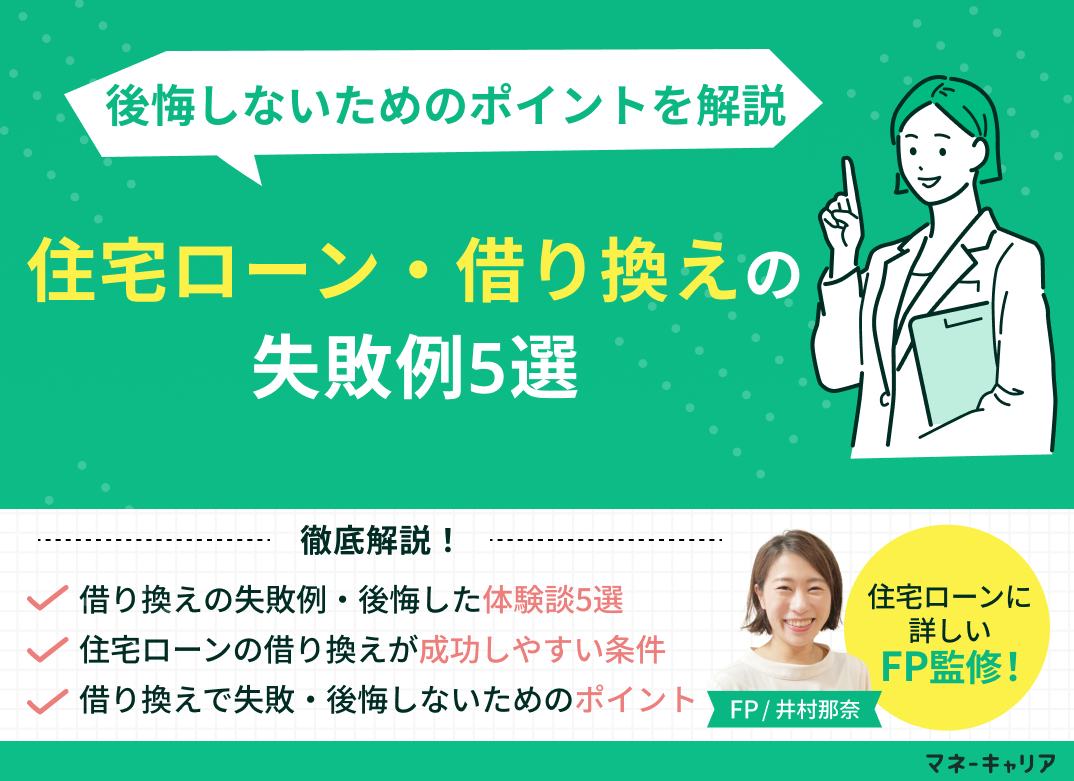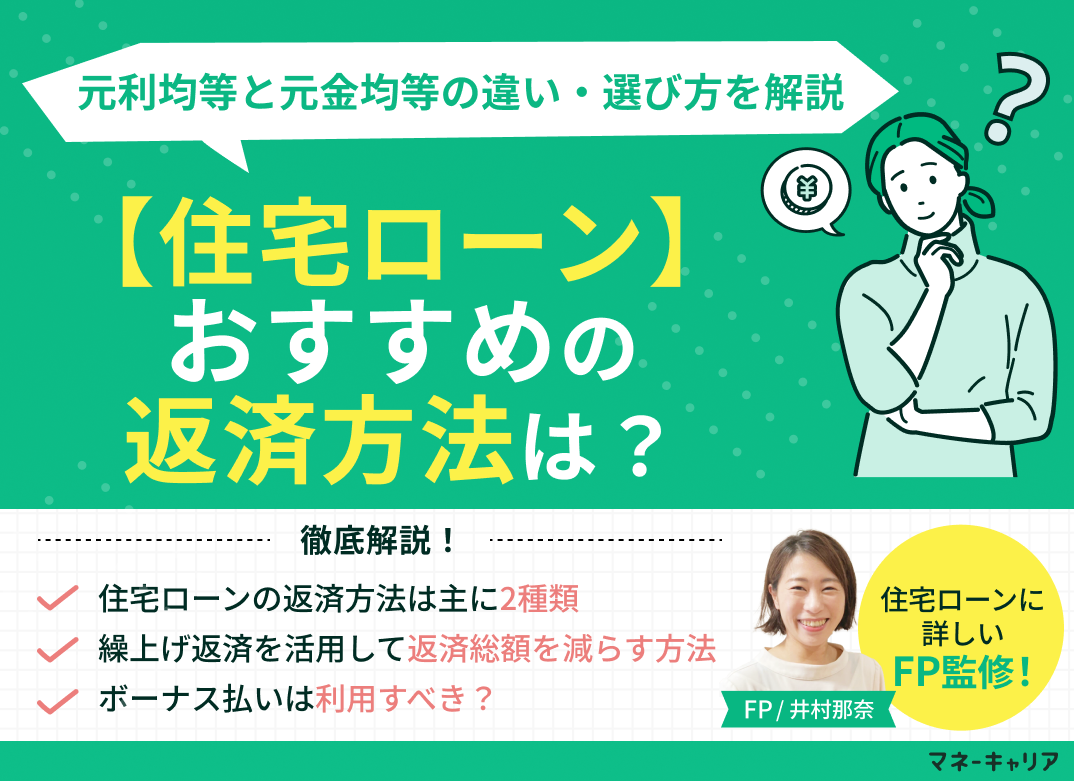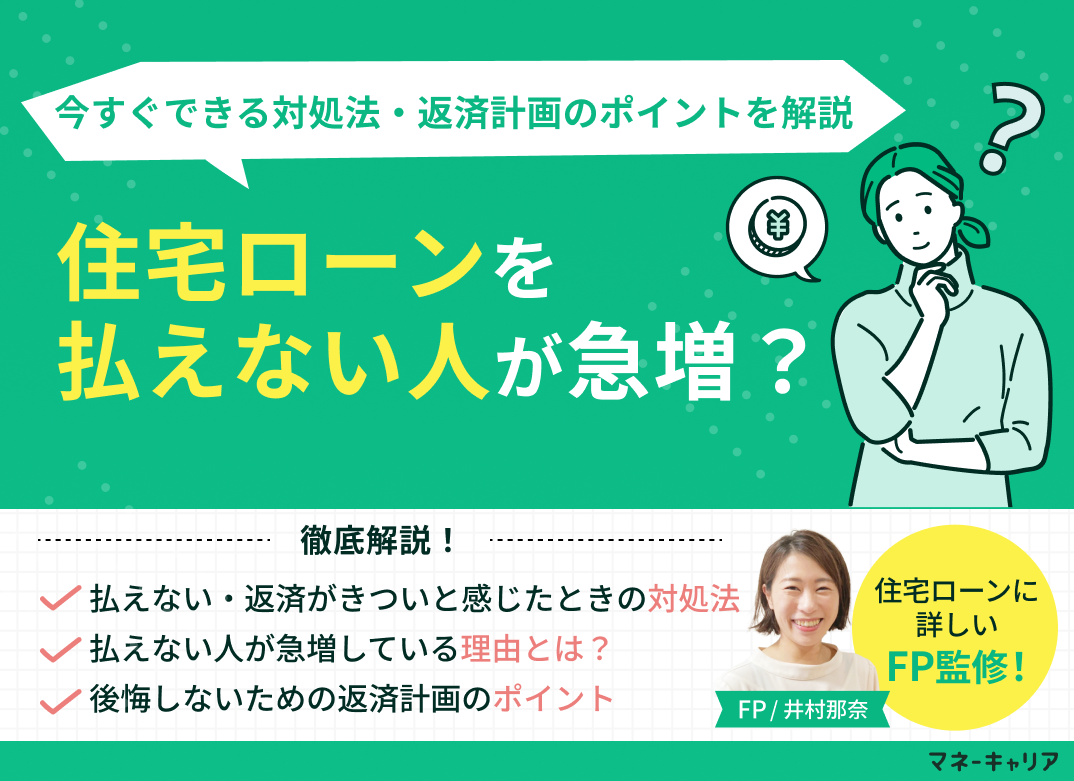この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 【共働き夫婦に向いている?】連帯債務型住宅ローンとは
- 連帯債務型とは
- ペアローンとどう違う?
- 共働き夫婦に向いているがリスクも
- 連帯債務型住宅ローンにする?迷う共働き夫婦はFPに相談してみよう
- 【体験談】住宅ローンを組んだ共働き夫婦にアンケート
- 住宅ローンの形態は?
- なぜこの形態を選びましたか?
- 連帯債務型を選んで実際に良かった点は?
- 連帯債務型で困ったことはありますか?
- 連帯債務型住宅ローンのメリット
- 借入額可能額が増える
- 夫婦ともに住宅ローン控除を受けられる
- 諸費用を節約できる
- 連帯債務型住宅ローンのデメリット
- 離婚しても債務は継続する
- 取り扱う金融機関が限られる
- 贈与税がかかるリスクがある
- 連帯債務型住宅ローンが向いている共働き夫婦の特徴3選
- 将来にわたり共働きを続ける夫婦
- ともに収入が安定している夫婦
- 住宅ローン控除を最大限活用したい夫婦
- 【共働き夫婦の疑問を解決!】連帯債務型住宅ローンのよくある質問
- 夫婦ともに審査の対象になる?
- 不動産の持ち主は誰になる?
- 住宅ローン控除は夫婦ともフルに受けられる?
- 主債務者しか団信に入れない場合どんなリスクがある?
- 最適な住宅ローンの組み方を知りたい共働き夫婦はマネーキャリアへの相談がおすすめ!
- 【まとめ】連帯債務型住宅ローンが共働き夫婦に合っているかはライフプランによる!
【共働き夫婦に向いている?】連帯債務型住宅ローンとは
連帯債務型の住宅ローンとは、1つのローンを2人以上で一緒に返済していくスタイルの住宅ローンです。
住宅ローンを組むときは、「1人で契約するケース」と「2人以上で契約するケース」があります。1人で契約する場合は、その人だけが返済の義務を負います。一方で2人以上で契約する場合は、契約者と連帯債務者がそれぞれに返済の責任を持つことになります。
家を購入するには多くのお金が必要になりますが、たとえば「自分ひとりの収入で無理なく返済できる」なら、単独で住宅ローンを組む選択もありです。でも「夫婦の貯金や収入を合わせて返済していきたい」と考えるなら、連帯債務型の住宅ローンを選ぶほうが現実的かもしれません。
ちなみに、連帯債務は夫婦でなくても利用できます。同じ家に住む親子や兄弟などでも設定可能です。ただし、実際には夫婦で利用するケースが圧倒的に多いため、この記事では「夫婦で連帯債務型の住宅ローンを組む」という前提で説明していきます。
連帯債務型とは
連帯債務型の住宅ローンは、夫婦2人の収入を合算して返済することが前提の住宅ローンです。
<連帯債務型住宅ローンの特徴>
- 夫婦2人がともに契約し、それぞれが返済義務を負う
- 連帯債務型にすると住宅ローン控除はそれぞれで受けられる(条件あり)
- ローンの返済義務は2人で連帯責任を負う
- 単独で借りる場合より借入可能額が増える
- 団信はひとりだけになるか、2人とも入れるかは金融機関による(フラット35は可能)
借入の条件は金融機関ごとに条件が違うので、注意しましょう。
ペアローンとどう違う?
▼連帯債務型ローンとペアローンの違い
| 連帯債務型ローン | ペアローン | |
|---|---|---|
| ローンの契約数 | 1本 | 2本 |
| 諸費用 | 1契約分 | 2契約分 |
| 団信 | 主契約者のみの場合あり | 2人とも加入 |
| 住宅ローン控除 | 2人とも受けられる | 2人とも受けられる |
| 返済義務 | 共同で返済義務あり | 各自の契約分に返済義務あり |
ペアローンは単独のローンを2つ組むことになります。そのため、夫婦それぞれが正社員で安定した雇用状態にあり、一定以上の収入があることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
共働き夫婦に向いているがリスクも
連帯債務型住宅ローンは、収入合算できるメリットが大きいです。住宅ローン控除もそれぞれで受けられるため、節税効果も期待できます。しかし、どちらかの収入が減ると返済に支障が出る可能性がある点は注意が必要です。
もし、どちらかが失業した場合、返済の猶予はなく、貯金が全くない状態ではリスクが高くなります。予期しない事態が発生する可能性があるため、事前に対策を考えておくことが重要です。
また、簡単に仕事を辞めることはできません。転職する際も、収入が大きく減少すると、住宅ローンの返済に影響が出るかもしれません。
連帯債務型住宅ローンにする?迷う共働き夫婦はFPに相談してみよう

同じ共働き夫婦でも、住宅ローンの組み方にはさまざまな選択肢があります。ペアローンが適しているのか、連帯債務型の住宅ローンを選ぶべきか迷った場合は、FPに相談するのも一つの方法です。
共働きといっても、会社員、公務員、自営業など、職種や雇用形態によって選ぶべきローンは異なります。さらに、ライフプランを考慮することが大切です。
ライフプランは、まず自分の将来像を描くことから始めます。自分の望みや希望を見据え、それに合わせて必要なお金をどうするか計画を立てることが重要です。
住宅購入を決める際は、自分たちのライフスタイルをしっかり考え「なぜ家を買うのか」「どんな家が欲しいのか」と具体的に考えることで、納得のいく住宅ローンを選ぶことができるでしょう。

【体験談】住宅ローンを組んだ共働き夫婦にアンケート
住宅ローンを組んだ共働き夫婦にアンケートを取りました。
それぞれのアンケート結果をもとに、住宅ローンの組み方などを参考にしてください。
住宅ローンの形態は?

なぜこの形態を選びましたか?

連帯債務型を選んで実際に良かった点は?

連帯債務型で困ったことはありますか?

連帯債務型住宅ローンのメリット

連帯債務型の住宅ローンにはどのようなメリットがあるのか、選択した場合どんな点が有利に働くかを確認してみましょう。
- 借入額可能額が増える
- 夫婦ともに住宅ローン控除を受けられる
- 諸費用を節約できる
単独で借りる住宅ローンとの違いを確認しましょう。
借入額可能額が増える
連帯債務型の住宅ローンは、単独ローンよりも借入可能額が増えるケースが多いです。単独では審査が通らない金額でも、返済金負担率が下がることで、審査が通りやすくなる可能性があります。
金融機関にとっては、2人で協力して返済をするというメリットがあります。連帯債務者は主債務者とは別に返済能力を持つため、複数の収入源を確保でき、人的担保としての機能が強化され貸し倒れリスクが軽減されます。
ただし、借入額が増えることで住宅購入はしやすくなりますが、その反面、返済額が増えるというデメリットもあることをしっかり認識しておきましょう。
夫婦ともに住宅ローン控除を受けられる
住宅ローン控除とは、返済期間10年以上で契約した住宅ローンがある場合に、一定条件を満たすと受けられます。新居に入居した年から最長で13年間、年末時点での住宅ローン残高の0.7%分を所得税から控除できる制度です。
所得税だけでは控除しきれない場合、翌年の住民税からも控除が行われます。例えば、年末の住宅ローン残高が3,000万円あれば、21万円税金が安くなります。住宅ローン控除は税額控除であるため、納めるべき税金が直接減額されるのです。
しかし、21万円より少ない税金しか納めていなければ、全額を引くことができません。全額を引けない場合は翌年の住民税から引かれます。
諸費用を節約できる
連帯債務型住宅ローンの返済は夫婦で行いますが、住宅ローンの契約は1つです。そのため、契約時にかかる事務手数料や印紙代は1契約分となり、ペアローンと比較して費用を節約できます。
諸経費の例
- 銀行に支払う融資手数料
- 抵当権設定の登録免許税
- 司法書士への手数料
これらの諸経費は、ペアローンの場合は別々に支払う必要があります。しかし、連帯債務型住宅ローンでは1契約分の支払いとなるため、合計の金額を抑えることができます。
連帯債務型住宅ローンのデメリット

連帯債務型はメリットが多いですが、一方でデメリットもあります。契約前に注意点をしっかり理解しておきましょう。
- 離婚しても債務は継続する
- 取り扱う金融機関が限られる
- 贈与税がかかるリスクがある
メリットとデメリットをしっかり把握したうえで契約の有無を判断しましょう。
離婚しても債務は継続する
連帯債務型住宅ローンは離婚しても債務がなくなることはありません。2人で返済することを前提にしているため、条件を変えるためには金融機関の審査を再度受ける必要があります。
家を売却して住宅ローンを完済できるのであれば、売却の選択も可能です。しかし、家の価値とローンの減少率は同じではなく、売却してもローンが残るケースも多いのです。
余裕がないローンの組み方をする場合は、特にリスクが高くなるので気をつけましょう。離婚をしなくても別の原因でローンが支払えなくなった場合は、売却しても完済ができない可能性があることも事実です。
取り扱う金融機関が限られる
連帯債務型住宅ローンは、ペアローンに比べ取り扱う金融機関が限られています。連帯債務型の住宅ローンは団信の加入が契約者のみの場合があります。
クロスサポート(連生団体信用生命保険付住宅ローン)は、契約者以外の連帯債務者に万が一のことがあった場合でも、ローン残高が0円となる住宅ローンです。
クロスサポートは契約者、連帯債務者のどちらが亡くなっても、ローンが無くなり、遺された家族の生活に役立ちます。
贈与税がかかるリスクがある
贈与とみなされると税金がかかるので注意しましょう。夫婦で家を共有する場合、贈与税がかかるリスクは、家の購入資金の負担割合と共有持分の割合が一致しない場合に生じます。
例えば、夫が家の購入資金の8割を負担したにもかかわらず、共有名義の登記で夫の持分が2分の1となっている場合、夫から妻へ、購入資金の差額に相当する持分(3割)が贈与されたとみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
夫婦間の贈与には、一定の要件を満たすことで贈与税が非課税となる「夫婦間の居住用不動産の贈与の特例」がありますが、この特例の適用要件を満たさない場合は贈与税がかかる可能性があるので注意しましょう。
夫婦間の居住用不動産の贈与の特例は、夫婦の婚姻期間が20年以上ある場合、2,000万円までの贈与が非課税となる制度です。
連帯債務型住宅ローンが向いている共働き夫婦の特徴3選

連帯債務型はどのような夫婦に向いているのでしょうか?向いている夫婦を3つ紹介します。自身に当てはまるかを確認してみましょう。
- 将来にわたり共働きを続ける夫婦
- ともに収入が安定している夫婦
- 住宅ローン控除を最大限活用したい夫婦
もし当てはまらない部分があれば、対策を考えましょう。
将来にわたり共働きを続ける夫婦
連帯債務型の住宅ローンは、共同で返済を行うため、長期にわたり夫婦で安定した収入が見込める場合は適しています。
共働きをできる限り続けるか、一時的と考えているかは、それぞれの家庭で異なります。お互いが共働きを続けることがベストと考えており、2人で安定収入を得ることに優先度が高い夫婦は連帯債務型の住宅ローンが向いているでしょう。
夫婦で協力し合い、共働きをすることを前提にライフプランを考え、お金のプランニングも2人の収入をもとに計画すれば、順調に返していくことができるでしょう。
ともに収入が安定している夫婦
住宅ローン控除を最大限活用したい夫婦
住宅ローン控除を最大限活用したい夫婦は、連帯債務型住宅ローンかペアローンがおすすめです。連帯債務型は、ペアローンに比べて融資関連の手数料が抑えられる点がメリットといえるでしょう。
住宅ローン控除は、住宅購入にかかる負担を軽減できる有効な節税手段です。ただし、控除を受けるには以下のような要件があります。
- 対象となる住宅の種類や仕様に応じて、控除限度額が定められている
- 控除を受ける人の年間所得が2,000万円以下であること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
住宅ローン控除は、入居した年から最長13年間(または10年間)適用されます。 そのため、10年以内に繰り上げ返済をしてローン残高が大きく減ると、控除額も減ってしまう点には注意が必要です。
【共働き夫婦の疑問を解決!】連帯債務型住宅ローンのよくある質問
連帯債務型を組もうとする人が抱える疑問に回答します。
- 夫婦ともに審査の対象になる?
- 不動産の持ち主は誰になる?
- 住宅ローン控除は夫婦ともフルに受けられる?
- 主債務者しか団信に入れない場合どんなリスクがある?
よくある質問の回答から、共働きで組む住宅ローンで問題になりそうな疑問を少しずつ解決しましょう。
夫婦ともに審査の対象になる?
連帯債務型の住宅ローンは2人とも審査の対象です。連帯債務型の住宅ローンは、夫婦それぞれが審査の対象となります。審査では、年齢・職業・信用情報などが総合的にチェックされます。
契約予定の住宅ローン以外に、車のローンやカードローンなどの返済があると、返済負担率(年収に対する返済額の割合)に影響する可能性があります。また、クレジットカードの支払い遅延がある場合も、信用情報に影響を及ぼすことがあるため注意が必要です。
延滞とみなされるのは、おおむね2カ月以上の支払遅れがある場合が一般的ですが、毎回の支払いがスムーズでない場合も、金融機関によってはマイナス評価となることがあります。
また、債務整理や保証会社による代位弁済などの「事故情報」が信用情報に登録されていると、審査に大きく影響する可能性があります。
不動産の持ち主は誰になる?
不動産を購入する際、頭金も住宅ローンも1人で負担すれば、その不動産はその人1人の名義になります。一方、頭金を2人で出し、ローンも連帯債務で借り、2人で返済していく場合は、共有名義にする必要があります。
頭金もローンも半分ずつ負担するのであれば、持ち分も2分の1ずつで問題ありません。ただし、頭金やローンの負担割合が異なる場合は「負担した割合に応じた持ち分」にしなければなりません。
たとえば、一方が多く負担しているのに持ち分を2分の1ずつにすると、負担の少ない側が「贈与を受けた」とみなされる可能性があります。贈与税の対象になるおそれもあるため、注意が必要です。
住宅ローン控除は夫婦ともフルに受けられる?
連帯債務型の住宅ローンは、夫婦の住宅ローン控除をフルに受けられる可能性があります。夫婦どちらかが控除しきれない額がある場合、夫婦で借入額の割合を調整すれば、単独でローンを組むよりより多くの控除を受けられるかもしれません。
以下の場合で説明します。
- 土地と家の購入代金(夫婦2分の1ずつの共有) 4,500万円
- 頭金 500万円
- 借入金(夫婦の連帯債務) 4,000万円
頭金を共有割合に応じてそれぞれが負担し、ローンを夫6:妻4で負担する場合、夫のローン負担額は2,400万円ですが、自己の持ち分に対応する借入金は2,000万円のため、控除対象は2,000万円となります。
差額の400万円は、夫が妻の持ち分を代わりに負担するローンとみなされます。一方、妻は自己の持ち分に対応する借入金が1,600万円となるため、控除対象も1,600万円となります。
頭金の負担割合が変わると、控除対象額も変動します。重要なのは、ローンの負担割合を収入などに合わせて決めることと、夫が妻の分を負担するローンは贈与とみなされることです。
主債務者しか団信に入れない場合どんなリスクがある?
連帯債務型で住宅ローンを組む場合、契約者(主債務者)しか団信に入れない場合があります。団信の扱いは金融機関や取り扱い商品ごとに違うので、条件はあらかじめ確認しましょう。
たとえば夫が主債務者、妻が連帯債務者の場合、妻が亡くなり収入が減ってもローンの返済は続くことになります。
連帯債務者が団信に入れない場合は、他の生命保険で死亡時に備える必要があります。2人で返していくことを前提としているので、万が一連帯債務者が亡くなった場合、返済金の支払いに困るリスクに備えなければなりません。
最適な住宅ローンの組み方を知りたい共働き夫婦はマネーキャリアへの相談がおすすめ!

今契約しようとしている住宅ローンは自分たちにの収入や状況に見合っているものなのか、冷静に考える必要があります。
ローンが通らなければ、住宅取得自体が難しくなり、ローンを抱えることはありません。しかし、ローンが通ってしまい支払いが開始すれば、簡単にはやめるわけにはいきません。
ローンの審査はあくまでも一時点での審査です。仕事も収入も家庭の状況も時間とともに変化はつきものです。ローンさえ通ればという考えでは、完済は難しいかもしれません。
連帯債務型住宅ローンを契約し借入額が増えることは、完済も難易度が上がることを考慮すべきです。2人の返済能力に見合った金額かを冷静に考えましょう。

【まとめ】連帯債務型住宅ローンが共働き夫婦に合っているかはライフプランによる!
共働き夫婦に適していると言われる連帯債務型住宅ローンですが、今後の働き方の変化によっては必ずしも最適とは言えなくなる可能性もあります。
特に若い世代で子供が増える可能性がある場合は慎重に検討しましょう。出産後一時的に収入が減る可能性があれば、それも見越した計画をたてることが必要でしょう。共働き夫婦が住宅ローンを組む場合、連帯債務型にするかどうかは、個別のケースによります。
ライフステージの変化に対応できるプランが理想ですが、基本は望むライフプランが何かによります。ライフプランを夫婦ですり合わせ、完済ができる住宅ローンを慎重に計画しましょう。
マネーキャリアでは、ライフプランニング、家計管理、資産形成を含むお金の全般の悩みを幅広く相談できます。
- 経験豊富な専門家が多数在籍
- FP相談満足度98.6%
- 累計相談件数が100,000件以上
- 対応エリアは全国47都道府県
- オンライン相談も可能
ライフプランに合わせた住宅ローンはマネーキャリアの専門家のアドバイスを受けながら検討しましょう。