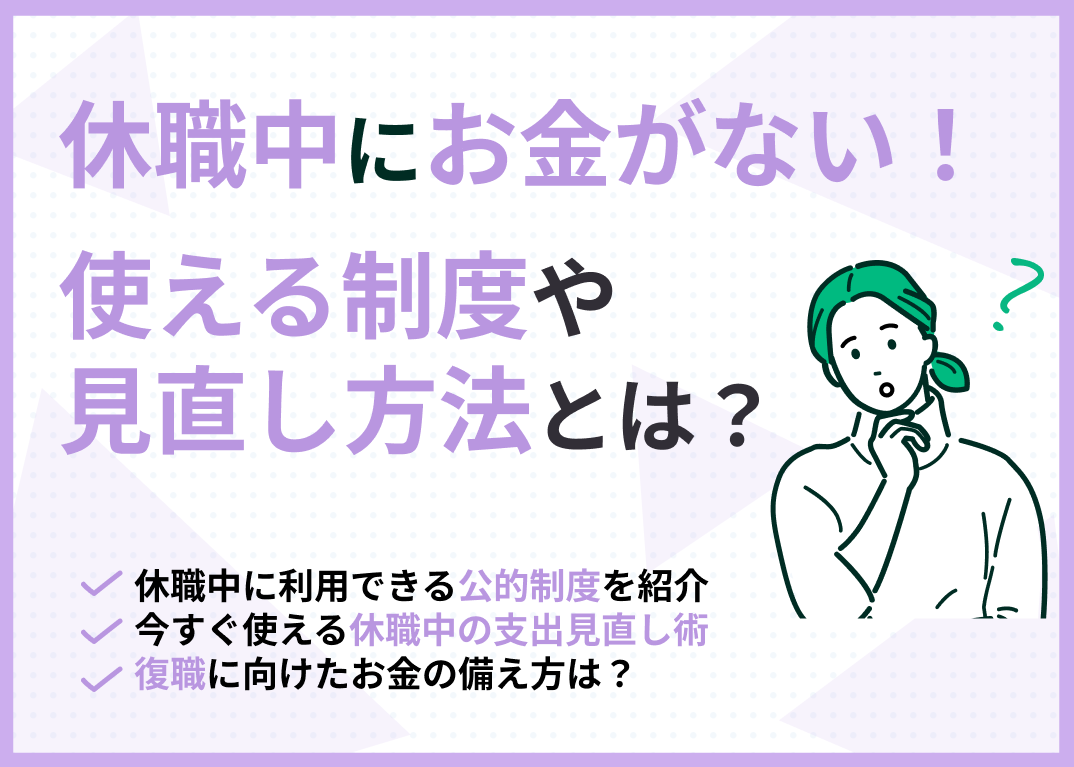
内容をまとめると
- 休職中に利用できる公的制度には、傷病手当や雇用保険給付、生活保護などがある。
- 中には、会社独自の休職制度を設けているケースもあるため、一度確認してみるのがおすすめ。
- また、自分はどの制度が利用できるか分からない、複数ある選択肢のうち、どの制度を選ぶべきか聞いておきたい、という方はお金の専門家であるFPへの相談が必須。
- マネーキャリアでは、経験豊富なFPがあなたの状況から使用できる制度、その後のライフプランまで丁寧に提案してくれる。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 休職中に利用できる公的制度
- 傷病手当金
- 雇用保険給付
- 生活保護制度
- 貸付制度
- 休職する際は会社独自の休職制度を確認すべき
- 今すぐ使える休職中の支出見直し術
- 固定費を削減をする
- 変動費を抑える
- 税金社会保険料の猶予申請をする
- 復職に向けたお金の備え方
- 復職後の生活設計を立てる
- 資産形成の考え方を見直す
- 投資制度の活用をしてみる
- 安心して休職を乗り切るには
- 相談できる専門家
- 相談先の選び方のポイント
- 休職中のお金がないを解決するためのよくある質問
- 傷病手当金はいつからもらえますか?
- 休職中に副業をしても良いですか?
- 休職期間が延長になりそうですが、どうすれば良いですか?
- 休職中にお金がない悩みを解決するには?
- 休職中にお金がない時に使える制度や支出の見直し方まとめ
休職中に利用できる公的制度
- 傷病手当金
- 雇用保険給付
- 生活保護制度
- 貸付制度
傷病手当金
雇用保険給付
生活保護制度
貸付制度
休職する際は会社独自の休職制度を確認すべき
休職する際は、公的な制度に加えて、自分が所属する会社の独自制度の有無も必ず確認しておくことが重要です。
多くの企業では、就業規則や社内制度として、法定以上の休職支援や給与補填制度を設けている場合があります。
たとえば、「企業独自の休職制度」として、一定期間の有給休暇の延長や、時短勤務への切り替え、復職支援プログラムの提供などが用意されているケースもあります。
また、大手企業や上場企業では、民間の保険を利用した団体保障制度を導入していることもあり、病気やケガによる所得補償が受けられることもあります。
さらに、給与の支給ルールや、健康保険組合を通じた追加の手当金制度など、所属企業ごとに内容が異なるため、休職前に人事や労務担当者へ確認することが大切です。
公的制度と企業独自の制度は併用できる場合も多く、活用できる制度を組み合わせることで、休職期間中の家計へのダメージを最小限に抑えることが可能です。
まずは、自社の就業規則や福利厚生のガイドブックをチェックしてみましょう。
今すぐ使える休職中の支出見直し術
休職中は収入が減少するため、支出の見直しは早急に行う必要があります。
特に固定費や変動費といった毎月かかる支出を見直すことで、少ない収入でも生活を維持しやすくなります。
さらに、税金や社会保険料は収入が減ったことを理由に支払いの猶予が認められる制度もあるため、積極的に活用するのがおすすめです。
収入が途絶えた状態であっても、支出をコントロールできれば精神的な安心感も得られます。
今のライフスタイルに必要な支出・不要な支出を見極め、無理のない形で生活を立て直すための準備をしていくのがおすすめです。
ここでは、今すぐ取り入れやすい3つの見直し術について詳しく解説します。
- 固定費を削減をする
- 変動費を抑える
- 税金社会保険料の猶予申請をする
固定費を削減をする
休職中に見直したい支出の中でも、まず手をつけたいのが固定費です。
固定費とは、毎月決まった金額が出ていく家賃や通信費、保険料、サブスクリプションサービスなどの支出を指します。
これらは使っていなくても支払わなければならないため、見直すことで効果的に節約できます。
たとえば、スマートフォンの料金プランを格安SIMに変更するだけでも月数千円の節約につながります。
サブスクリプションも複数契約している場合は、利用頻度が低いものを一時的に解約して支出を抑える方法が有効です。
また、家賃の見直しはすぐに対応できるわけではありませんが、可能であればより安い物件への引っ越しも視野に入れるのもおすすめです。
保険に関しても、補償内容が現在のライフスタイルに合っているかを見直し、必要に応じて保険料を抑える手段を検討する価値があります。
不要なオプションが付いていたり、複数の保険に加入していて重複していたりすることもあるため、契約内容を一度整理してみましょう。
変動費を抑える
変動費とは、食費や日用品費、交通費、交際費など、その月によって支出額が変動する項目です。休職中は、収入が限られる中でやりくりする必要があるため、変動費の管理も重要です。
ただし、削りすぎて生活の質を下げるのではなく、使い方を見直して効率よく節約する工夫が求められます。
その中でもまず取り組みやすいのが食費の見直しです。外食やコンビニを控え、自炊中心の生活にシフトすることで、月に1〜2万円以上節約できる可能性があります。
変動費は気づかないうちに増えていることも多いため、家計簿アプリなどで可視化しながら管理していくのがおすすめです。
税金社会保険料の猶予申請をする
休職中に収入が大幅に減少した場合は、国が提供する税金や社会保険料の支払い猶予制度を活用するのも有効な手段です。
これらの制度を利用することで、すぐに現金を用意できなくても一時的に支払いを延期でき、生活を維持する余裕が生まれます。
たとえば、所得税や住民税は「納税猶予制度」によって、最大1年の猶予が受けられるケースがあります。
社会保険料についても、国民年金の「免除申請」や「納付猶予」、健康保険料の減免申請など、状況に応じた支援制度があるため、一度市役所に問い合わせてみましょう。
また、会社員の場合は、休職中でも健康保険や厚生年金の一部を個人で負担する必要が出てくる場合があるため、早めに確認しておくことが大切です。
これらの手続きは、市区町村の役所や税務署、年金事務所などで行うことができ、申請に必要な書類や収入状況の証明を準備することでスムーズに対応してもらえます。
無理に支払いを続けて生活が破綻してしまう前に、制度を知って相談に行くことがおすすめです。
節約だけで乗り切ろうとせず、使える制度をしっかり活用することが、休職中の家計管理ではとても重要です。
復職に向けたお金の備え方
休職期間が落ち着いてきたら、復職後の生活や働き方に向けたお金の準備も意識しておくことが大切です。収入が戻るとはいえ、すぐに以前の状態に完全に戻るわけではありません。
例えば体調を見ながらの時短勤務や、急な出費があることも考えられるため、復職を見据えて家計を再構築しておくことが求められます。また、休職をきっかけに将来への備えの重要性を実感した方も多いはずです。
資産形成や投資についての知識を見直すことで、より安心して日常を再スタートできるようになります。
制度を活用しながら、ライフプランに合わせたお金の管理方法を考えるタイミングとしても、復職前後は最適な時期です。
以下では、復職を見据えたお金の備え方を、具体的な3つの視点から、詳しく紹介します。
- 復職後の生活設計を立てる
- 資産形成の考え方を見直す
- 投資制度の活用をしてみる
復職後の生活設計を立てる
復職後の生活を見据えて、まず行っておきたいのが生活設計の見直しです。
休職前と同じ働き方に戻れるとは限らず、体調面や家庭の事情によっては時短勤務や業務内容の調整が必要になるケースもあります。
そうなると、収入や支出のバランスも変わってくるため、無理のない生活設計をあらかじめ組んでおくと安心です。
また、復職後にかかる費用(通勤費、保育料、昼食代など)も考慮して、生活費の予算配分を変更しておくのがベストです。加えて、復職時には急な支出が発生する可能性もあります。
通勤用の服を新調したり、家族の生活リズムが変わったりと、思わぬ出費がかさむことも少なくありません。
ある程度の余剰資金を確保しておくことで、復職後の生活をスムーズにスタートできるようになります。
資産形成の考え方を見直す
休職を経験したことで、「収入がなくなるリスク」に直面した方も多くいるのではないでしょうか。そこで、これからの人生においては資産形成の重要性を改めて見つめ直すことが大切です。
将来的な不安を減らすためにも、日々の収支を見直しつつ、長期的な貯蓄や投資への視点を持っておくと良いでしょう。
まずは生活防衛資金として、数ヶ月分の生活費を現金で確保しておくことが基本です。
そのうえで、余剰資金を少しずつ積み立てていく方法として、国が行う制度を検討するのもひとつの手です。制度については以下で詳しく紹介していきます。
また、資産形成をするうえで気をつけたいのが、リスクとの向き合い方です。
焦って高リスクな投資に手を出すのではなく、自分のライフプランに合った形で資産を育てていくことが重要です。
家計や生活スタイルに合わせた「無理のない積立」が、将来の安心につながります。
投資制度の活用をしてみる
復職を機に、将来に向けた投資制度を検討することも選択肢のひとつです。
特に、つみたてNISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)などの制度は、少額からでも始められ、非課税のメリットがあるため、初心者にも取り入れやすいのが特長です。
たとえば、つみたてNISAであれば年間40万円までの投資額が非課税となり、運用益を効率よく積み上げることができます。
一方で、iDeCoでは老後資金としての積立に特化しており、所得控除の恩恵があるため、節税効果も期待できます。
こうした制度は、自分の収入やライフステージに合わせて選ぶことが重要です。復職後の収入を活かして、無理のない範囲で資産形成を始めることで、今後の生活に対する安心感も高まります。
また、どの制度を選べばいいか分からない場合は、FPなどの専門家に相談しながら進めると、自分に合った投資スタイルを見つけやすくなります。
プロの意見を取り入れて行動することも、安定した資産形成への一歩です。
安心して休職を乗り切るには
休職中は、収入が減る一方で支出は続くため、家計や将来への不安がつきものです。
特に公的制度や支出の見直し、復職後の資金計画など、自分ひとりでは判断が難しいことも多くあります。
そうしたとき、頼れるのがお金の専門家です。
「専門家に相談するなんてハードルが高い」と感じる方もいるかもしれませんが、実際には、自分に合った制度の選び方を第三者の視点で提案してくれる存在がいることで、安心して休職期間を乗り切ることができます。
ここでは、どんな専門家に相談できるのか、そして信頼できる相談先の選び方について詳しく紹介します。
- 相談できる専門家
- 相談先の選び方のポイント
相談できる専門家
休職中のお金の悩みを相談する相手としては、ファイナンシャルプランナー(FP)が最も身近で実用的な存在です。
FPは、収入や支出のバランスを分析し、家計の立て直しや将来の資金計画、公的制度の活用方法などを総合的にアドバイスしてくれるお金のプロです。
特に「FP資格」を保有している専門家は、保険や投資、税金、年金など幅広い知識を持っており、ライフスタイルに合わせた資金計画を立てるサポートができます。
休職中の支出の見直しに加え、復職後を見据えたアドバイスまで受けられる点が大きなメリットです。
また、病気や育児など個別の事情に寄り添いながらアドバイスをくれる専門家を選ぶことで、「自分のための解決策」が明確になります。
一人で抱え込まず、プロの手を借りることで道筋が見えやすくなります。
相談先の選び方のポイント
相談先を選ぶ際に意識したいのは、「中立的な立場かどうか」「相談のしやすさ」「費用の有無」の3つです。
中立性が高いサービスなら、特定の金融商品を売ることを目的とせず、本当に必要な情報だけを提供してくれます。
また、事前に相談相手のプロフィールや経歴、得意分野をチェックできる仕組みがあると、自分に合った専門家を選びやすくなります。
対応時間が柔軟なところや、何度でも相談できるサービスであれば、継続的な見直しも可能です。
初めての方には、顔を出さずに相談できるチャット型のサービスや、予約不要のオンライン面談もおすすめです。
対面よりもハードルが低く、ちょっとした疑問も気軽に聞ける環境が整っているのがメリットです。
こうした選択肢を活用すれば、不安な休職期間も安心して乗り越えやすくなることが期待できます。
休職中のお金がないを解決するためのよくある質問
休職中は、働けないことによる収入の減少だけでなく、手続きや制度の複雑さにも頭を悩ませる方が多くいます。
「傷病手当金はいつからもらえる?」「副業しても大丈夫?」「もし休職期間が長引いたら…」など、状況によって不安や疑問は人それぞれです。
ここでは、休職中によくあるお金に関する疑問に一つずつ丁寧にお答えしていきます。制度の内容や申請方法、注意点などを事前に知っておくことで、心に少し余裕を持つことができます。
- 傷病手当金はいつからもらえますか?
- 休職中に副業をしても良いですか?
- 休職期間が延長になりそうですが、どうすれば良いですか?
不安を軽くするための第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。
傷病手当金はいつからもらえますか?
傷病手当金は、会社を連続して3日間休んだ「4日目以降」から支給対象となります。
つまり、最初の3日は待機期間となり、その後の休業日について、会社から給与が支払われていない場合に限り支給されます。
申請のタイミングによって、実際に手元に入るのは1〜2か月後になるケースもあるため、早めの手続きと事前の資金確保が重要です。
また、申請には医師の診断書や勤務先の証明書、本人の申請書などが必要になります。書類不備があると審査が長引くこともあるため、あらかじめ準備しておくとスムーズです。
給付額は、標準報酬日額の約3分の2が目安ですが、健康保険の種類や加入状況によっても変わるため、詳細は自身が加入している健康保険組合に確認すべきです。
申請先がわからない場合は、会社の総務や社会保険担当に問い合わせるのも安心です。
参照:全国健康保険協会
休職中に副業をしても良いですか?
休職中の副業については、「就業規則」と「傷病手当金の支給条件」の両方を確認する必要があります。
まず、多くの企業では休職中の副業を禁止または制限している場合があります。
たとえ軽作業でも、会社に無断で副業を行うと規則違反とみなされる可能性があるため、事前に必ず確認をとることが大切です。
また、傷病手当金を受け取っている場合は、副業によって「労務に従事している」と判断されると支給が停止されることもあります。
副業の収入が少額でも、就労実態があると見なされれば支給停止や返還対象になるケースがあるため、慎重な判断が必要です。
体調の回復が最優先であることを踏まえ、仮に副業を検討する場合も、会社や健康保険組合に必ず相談してから動くようにしましょう。
休職期間が延長になりそうですが、どうすれば良いですか?
休職期間が延びそうなときは、早めに会社と主治医に連絡をとって対応を進めるべきです。
会社には、休職延長の意思と医師の意見書が必要になる場合が多く、あらためて診断書を提出することで正式に延長の手続きが行われます。
また、会社によっては最大休職期間が定められているため、自身の就業規則を確認しておくと安心です。一方、金銭面の支援である傷病手当金も、支給期間には上限があります。
原則として「支給開始日から最長1年6か月」が限度となっており、延長された休職がその期間を超える場合は、ほかの支援制度の活用を検討する必要があります。
たとえば、生活費が不足する場合には生活福祉資金貸付制度や生活保護制度も視野に入れることができます。
長期化が予想される場合は、キャッシュフローの見直しと、各種制度の申請タイミングをしっかり把握しておくことが大切です。
休職中にお金がない悩みを解決するには?
休職中にお金がない悩みを解決するには、使える制度や支出の見直し、将来に備えた家計設計など多角的な視点が欠かせません。
「手当や支援制度はあるけれど、いつ何を申請すればいいのか分からない」「収入が減る中で家計のバランスをどう保てばいいのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、将来の支出や生活再建まで見据えると、一人で考え続けるより専門家に相談するほうが早くて確実です。
そんな悩みをまるごと相談できるサービスとしておすすめなのが、マネーキャリアです。
マネーキャリアでは、FP資格を持つ専門家が、収入減に伴う公的制度の活用方法から、支出の見直し、将来のライフプラン設計まで幅広く対応してくれます。
中立的な立場で、一人ひとりの状況に合わせた提案を無料で受けられるのが魅力です。
相談満足度は98.6%と高く、どのような専門家が対応してくれるか事前にプロフィールを確認できるため、初めての方でも安心して利用できます。

家計やお金の悩み全般を無料でオンラインで解消
マネーキャリア:https://money-career.com/
マネーキャリアのおすすめポイントはこちら
- お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、年収や節税について知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選
- 資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能
- マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇っています
休職中でお金の不安を感じている方は、ぜひ活用してみてください。

休職中にお金がない時に使える制度や支出の見直し方まとめ
本記事では、休職中にお金がなくて困っている方に向けて、活用できる制度や支出の見直し方法について詳しく紹介しました。
傷病手当金や雇用保険給付、生活福祉資金などの制度は、申請のタイミングや条件を知っておくことで、生活の支えとなります。
また、支出面では、固定費・変動費の見直しや、税金・社会保険料の猶予申請を活用することで、赤字リスクを大きく軽減できます。
ただ、制度や手続きの内容は複雑で、どれが自分に当てはまるのか分からない、支出をどこまで削ればいいのか見当がつかない、と感じる方も多いのではないでしょうか。
さらに、将来の生活や復職後の資金計画にまで思いを巡らせると、不安はさらに大きくなります。 そんなときは、お金の専門家に相談してみるのがおすすめです。
中でも「マネーキャリア」では、FP資格を持つ専門家が、家計状況を丁寧に分析し、一人ひとりのライフスタイルに合わせた制度の活用法や資金の見直し、復職後を見据えたライフプランまで、無料でアドバイスしてくれます。
事前に専門家のプロフィールや口コミも確認できるため、安心して利用できます。
「制度やお金のこと、もっと早く知っておけばよかった」と後悔しないためにも、今のうちにできる備えを始めましょう。




















