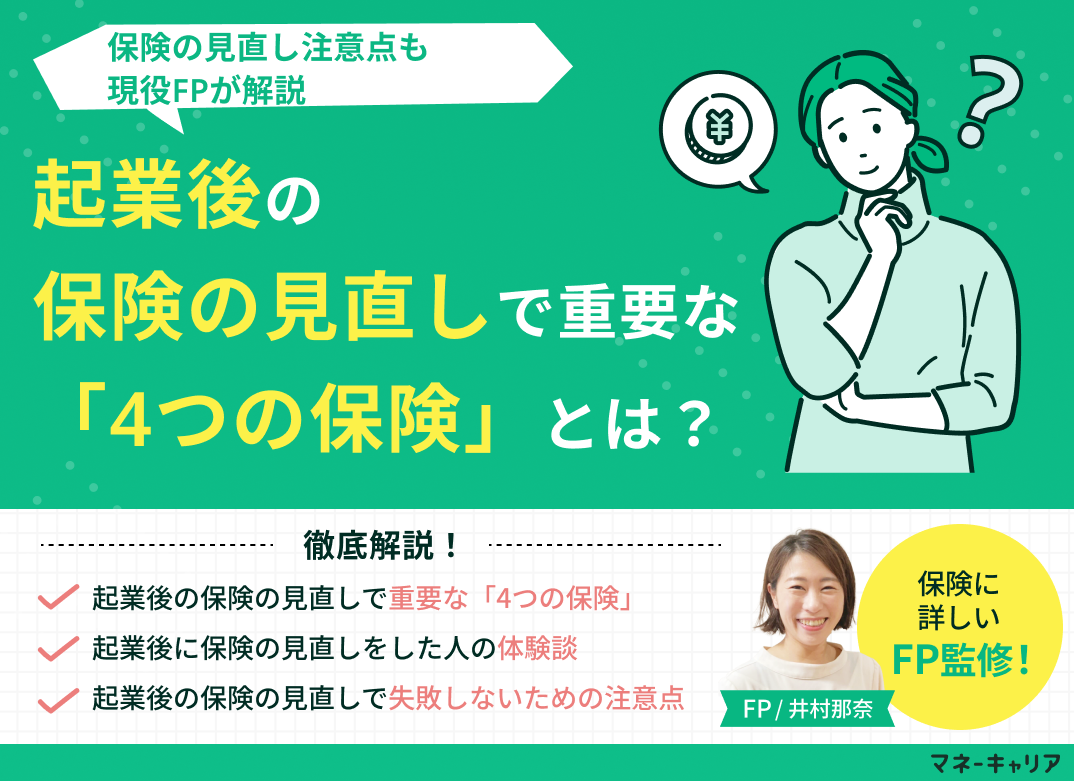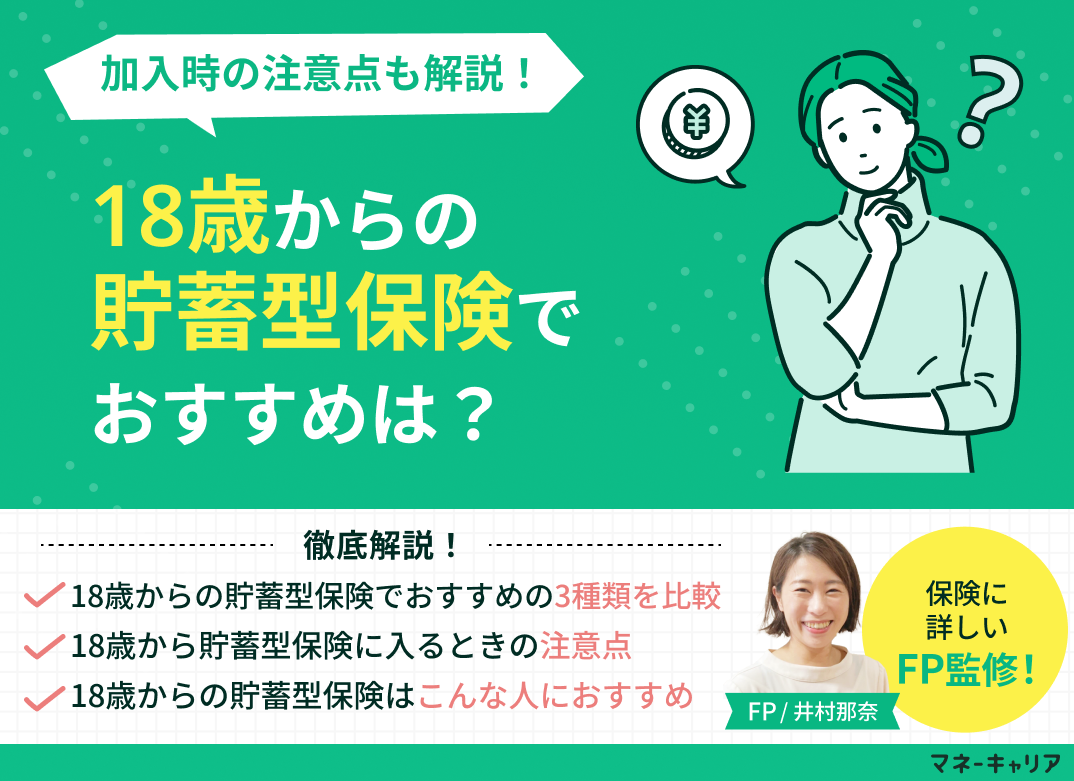「自分が死んだらお金はどうなる?」
「家族にお金を残す方法はなにがある?」
とお悩みではないでしょうか。
- 結論、自分が死んだ後に家族にお金を残す方法はいくつかあり、生命保険や相続、生前贈与などを活用することで効果的に資金を準備できます。
この記事では、自分が死んだあとに家族にお金を残す方法について解説します。
自分がいない暮らしで家族にどれくらいのお金があれば安心かについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
自分が死んだあとに家族にお金を残す方法3選
自分が死んだあとに家族にお金を残す方法は主に以下の3つです。
- 生命保険で残す
- 相続で残す
- 生前贈与を活用する
生命保険で残す【おすすめ】
1つめは、生命保険で残す方法です。
生命保険は、万が一の際に確実に家族に資金を残せる仕組みで、保険料を支払っている限り保障が継続されます。
特に、まだ幼いお子さんがいる家庭や、住宅ローンなどの負債を抱えている家庭にとっては、生命保険がもしもの時の経済的なリスクを大きく軽減してくれます。
また、保険金は受取人が指定されているため、相続手続きが簡単で、すぐに家族が資金を受け取れるという利点もあります。
相続で残す
2つめは、相続で残す方法です。
相続は、預貯金や不動産、有価証券など、亡くなった方の財産を家族が引き継ぐ方法です。
相続財産には基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)があり、この範囲内であれば相続税はかかりません。
例えば、配偶者と子ども2人がいる場合、4,800万円までは相続税が非課税となります。
ただし、相続手続きには時間がかかり、遺産分割協議が必要な場合もあるため、すぐに資金が必要な場合には不向きです。
また、相続財産が多い場合は相続税の負担も考慮する必要があるため、事前の税務対策が重要になります。
生前贈与を活用する【生きている間】
3つめは、生前贈与を活用する方法です。
生前贈与は、自分が生きている間に、自分の財産を家族に贈与する方法です。
年間110万円までの贈与は贈与税が非課税となるため、長期間にわたって活用することで多額の資産を移転できます。
また、教育資金の一括贈与(1,500万円まで非課税)や結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで非課税)などの特例制度も活用できます。
ただし、贈与は生前に行うため、自分の老後資金に影響しないよう慎重な計画が必要です。
自分がいない暮らし、家族にどれくらいのお金があれば安心?

参考として公益財団法人 生命保険文化センターの「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」(※)より世帯主が就労不能になった場合の必要生活資金は月額27.2万円です。
これを年単位に換算すると以下の通りです。
あくまで目安なので不測の事態に備えて必要な額を家族に残せるようにしましょう。
- 1年の生活費:326万円
- 15年の生活費:4,890万円
- 30年の生活費:9,780万円
葬儀やお墓にもお金がかかる
もし自分が死んでしまった場合、遺族の方針や規模にもよりますが、当然葬儀をしたりお墓を建てたりといった「死亡整理金」といったものも少なからず費用がかかります。
まず葬儀に関してですが、鎌倉新書の「第5回お葬式に関する全国調査」(※1)より
葬儀全体で必要な費用は110.7万円です。
次にお墓に関してですが、鎌倉親書の「第13回お墓の消費者全国実態調査」(※2)より
一般墓の平均購入費用は158.7万円です。
ですので、葬儀費用とお墓購入の費用を合わせた死亡整理金は約270万円ほど必要ということなります。
※1参照:第5回お葬式に関する全国調査|鎌倉新書
残された家族の必要な住居費
収入の20%や30%が適正家賃などの言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、出費のうち、住居費が占めるウェイトはどこの家庭も多いようです。
家賃は同じような間取りの物件であったとしても地域によってかなり額が変動しますが、総務省統計局の「平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計」(※)
によると借家の家賃は年単位で増加傾向であり、2018年度の1ヶ月平均家賃は55,675円です。
この数字の試算だと、家賃は年間で約70万円ほどの費用が必要になります。
世帯主が亡くなってしまうと世帯収入は大幅に少なくなるので、現在の自分の収入が1円も入ってこない家計状況で残された家族が生活する際、適切な家賃がどのくらいかシミュレーションしてみるとよいでしょう。
残された家族の必要な食費・生活費
食費は死亡整理金のように一時的に必要な費用ではなくほぼ永続的に発生するのでご自分の家族構成に合わせてどれほど必要か把握しておくとよいでしょう。
総務省統計局の「家計調査(二人以上の世帯)2022年(令和4年)9月分」(※)によれば2022(令和4年)9月分の調査においては、二人以上の世帯では消費支出全体が245,020円で食費が占める割合はおおよそ3割の80,789円でした。
この数字の資産だと食費だけで年間約100万円弱もの費用が必要になります。
子供の必要な教育費
子供の有無やその人数・年齢などにより大幅に費用は変動しますが食費などの生活資金と比べると教育費はかなり大きい額を必要とします。
文部科学省「平成30年度子供の学習費調査」(※1)によると
| 学校 | 公立の場合の学費 | 私立の場合の学費 |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 約22万4千円 | 約52万8千円 |
| 小学校 | 約32万1千円 | 約159万9千円 |
| 中学校 | 約48万8千円 | 約140万6千円 |
| 高等学校 | 約45万7千円 | 約97万円 |
が各教育段階で平均的な教育費です。
公立と私立で比較をすると
- 幼稚園から高等学校まで15年間全て公立:約540万円
- 幼稚園から高等学校まで15年間全て私立:約1,800万円
が教育費の平均です。
私立と公立で桁が変わるほど差があるとは驚きですね。
また、日本政策金融公庫令和3年度の「教育費負担の実態調査結果」(※2)によると、義務教育修了後高校に入学してから大学を卒業するまで子供1人あたり942.5万円の教育費が必要であり世帯年収のうち占める子供の年間在学費用の割合平均は14.9%です。
※1参照:平成30年度子供の学習費調査|文部科学省
緊急予備資金
緊急予備資金とは何らかの不測の事態に見舞われてしまった時に、生活を続けていくための予備のお金です。
日本FP協会の「くらしとお金の安心ブック」(※)によると毎月の生活費の最低でも3-6ヶ月分できれば1年や2年分残しておくと安心とされています。
緊急予備資金は意外と見落とされがちですが災害や急病にもしっかり備えておくことが大切です。
最近よく聞く終活って?
「就活」という言葉は皆さん知っていると思いますが、この「終活」という言葉を聞いたことがある人はそれほど多くないのではないでしょうか?
「終活」とは、「自分の人生の最期を意識して行う活動」のことです。
自分が生きている間に、お金の扱いなどはきちんと取り決めや意思表示をしておかないと残された家族はどうしていいかわからなくなってしまいますよね。
具体的な終活の内容としては、
- 医療や介護に関しての希望方針を決めておく
- 生前保有していた不動産や預金、株式をはじめとした資産をどう扱うかを決めておく
- 相続はどのようにするのか決めておく
「お金」について知るのが大切
ここまで記事を読んで頂いて、「そんなこと今まで知らなかった」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
適切な生命保険の選び方や財産の守り方などは家族構成やライフステージなどの影響を受けるので個人に合わせて十人十色です。
終活などで子供や配偶者への相続について自分の中で取り決めをする際も正しい知識、正しい目線で意思決定することが極めて重要です。
お金について知るのが非常に大切ですが、難しくて何をすればよいのかよくわからないですよね。そんな時は分かりやすくお金について教えてくれる人に相談してみませんか?
マネーキャリアであれば自分が死んでお金を残す方法など、さまざまな疑問や悩みをお金のプロにオンラインで相談することができます。ぜひ一度利用してみてはいかがでしょう。
死んで家族にお金を残す方法のまとめ
ここまで読み進めていただきありがとうございます。
この記事では、自分が死んでしまった後、残された家族はどのような出費をする必要があり
その額はどのくらいなのか、「死んでお金を残す方法」としてどのような選択肢があるのか
生命保険や貯金などを例に挙げて比較しながらみなさんにお伝えしました。
自分が死んだら家族にお金の苦労をかけていまわないだろうか...と不安になられていたと思いますが、本記事の内容を参考に将来の備えをしておけば万が一のことがあっても安心です。
子供の年齢や世帯人数により必要な金額は異なります。
自分のライフステージなどについて考え、本当に必要なお金をシミュレーションして最適な「死んでお金を残す方法」を見つけましょう。