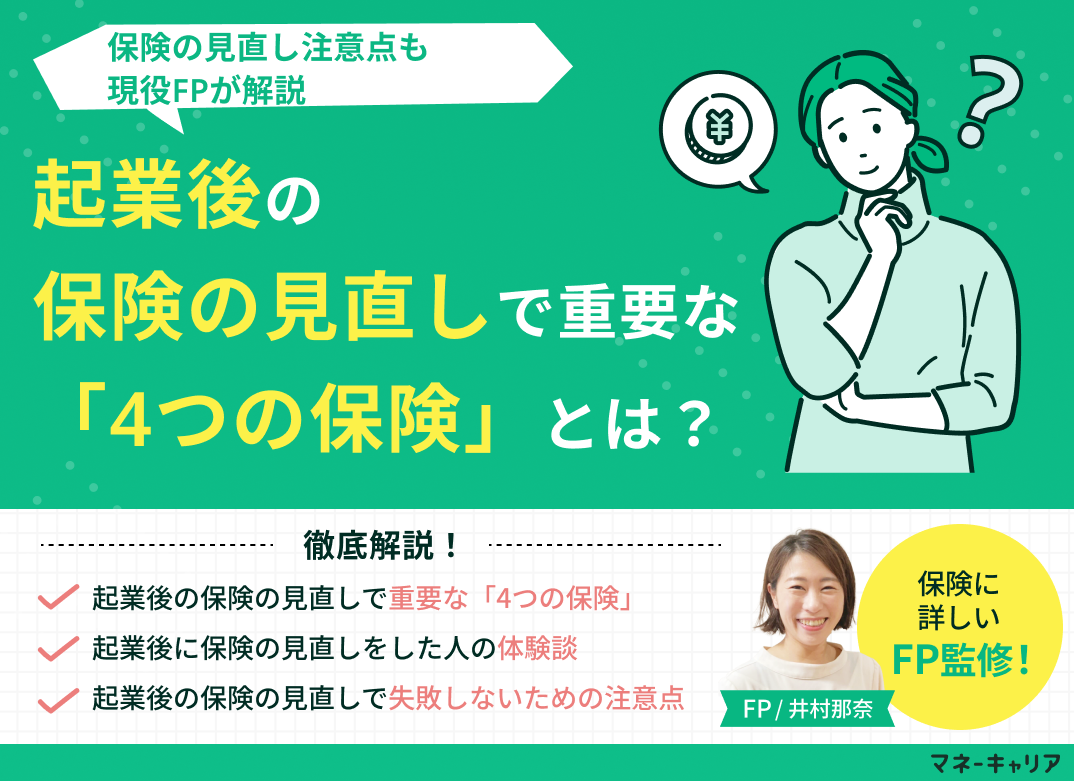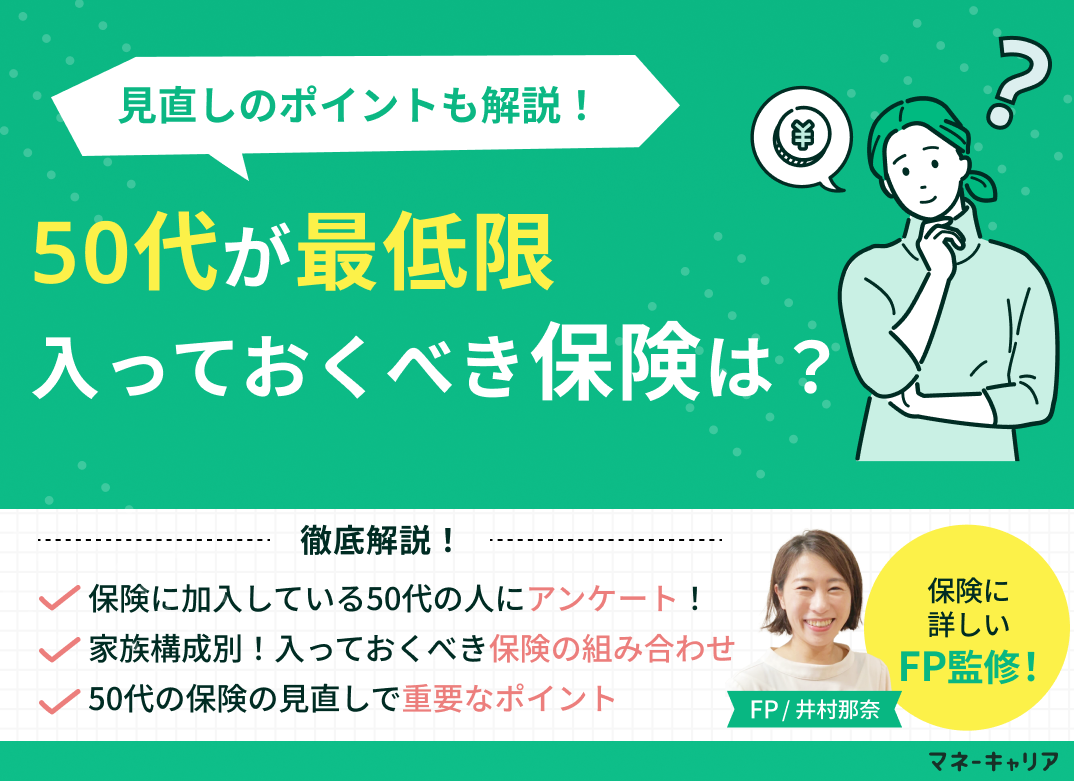- 結論、生命保険の受取人に指定できるかは保険の種類や給付金の種類によって異なります。

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
生命保険の死亡保険金の受取人を本人(自分)にすることは可能?
結論、生命保険の受取人を本人にできるかは保険の種類や給付金の種類によって異なります。
例えば、死亡保険金の場合は「死亡時に」お金がもらえる仕組みで、死亡した本人が受け取ることは不可能なため指定できません。
一方で、生存中に受け取れる死亡保障や満期金がある養老保険、医療保険・がん保険・個人年金保険などの給付金については受取人を本人に指定することができます。
そのため、自分の保険がどの種類にあたるかを確認し、誰にどう残すか・どの保障を自分で受け取るか、整理することが大切です。
独身の場合は生命保険の死亡保険金の受取人を本人以外の誰にしたらいいの?
独身の場合、基本的には二親等以内の血族を受取人にします。具体的には以下の人たちです。
- 親
- 兄弟姉妹
また、法律上は独身ではあるが、事実婚状態で内縁の妻・夫がいる人の場合、要件を満たすと内縁の妻・夫を受取人にできます。
この場合の要件は以下の3点です。
- お互いに戸籍上の配偶者がいないこと
- 保険会社が指定する期間以上の同居期間
- 保険会社が指定する期間以上、生計を共にしている
もし内縁の妻・夫を受取人に指定したい場合は、戸籍謄本や住民票などの証明できる書類が必要になります。
また、書類があれば必ず指定可能なわけではなく、各保険会社が独自の基準で認めた場合のみ、生命保険の受取人に設定できます。
本人を受取人にできる主な保険の種類
本人を受取人にできる主な保険の種類・給付金の種類は以下のとおりです。
- 生存保険(満期保険金)
- 年金保険(個人年金保険)
- 医療保険・がん保険などの給付金
- 高度障害保険金
生存保険(満期保険金)
一つ目は生存保険における満期保険金です。具体的には、養老保険やこども保険などが当てはまります。
これらは、満期まで生存していれば、契約者本人に保険金が支払われます。
養老保険の場合、保険期間中に死亡した場合は死亡保険金が受取人(本人以外)に支払われますが、満期まで生存した場合は満期保険金として本人が受け取ることができます。
また、こども保険では、子どもの進学時期に合わせて契約者本人を受取人に指定して、祝い金や満期保険金を受け取れるため、教育資金の準備に活用することができます。
年金保険(個人年金保険)
二つ目は個人年金保険における年金給付です。
個人年金保険では、契約者本人が受取人となり、一定期間または終身にわたって年金を受け取ることができます。
年金の中には、確定年金や終身年金などの種類があり、老後資金の確保を目的として契約者本人を受取人に指定するのが一般的です。
年金開始時期まで生存していることが前提となるため、契約者本人以外を受取人に指定するケースは基本的にありません。
ただし、万が一、年金受給開始前に契約者が死亡した場合は、死亡給付金として遺族が受け取ることになる点に注意が必要です。
医療保険・がん保険などの給付金
三つ目は医療保険やがん保険などの給付金です。
これらの保険では、契約者本人が入院や手術、がんの診断を受けた際に給付金が支払われます。
医療費の補填や治療期間中の生活費をカバーするための保険なので、被保険者本人が請求・受取可能です。
入院給付金、手術給付金、がん診断給付金など、さまざまな種類の給付金がありますが、いずれも契約者本人の治療や療養のために使用されることを前提としています。
そのため、これらの給付金については、契約者本人を受取人に指定することで、迅速な給付金の受け取りが可能になります。
高度障害保険金
四つ目は高度障害保険金です。
高度障害保険金とは、契約者本人が保険会社の定める高度障害状態になった場合に支払われる保険金です。
高度障害状態とは、両眼の視力を永久に失った場合や、言語またはそしゃくの機能を永久に失った場合など、日常生活に大きく支障をきたす状態を指します。
この保険金は、高度障害状態となった契約者本人の今後の生活費や介護費用をカバーする目的があるため、契約者本人を受取人に指定するのが一般的です。
ただし、契約者本人が意思表示できない状態の場合は、法定代理人や成年後見人が代理で受け取ることもあります。
生命保険の受取時にかかる税金

生命保険の受取時にかかる税金は、受取人が契約者本人か、契約者以外の人かによって異なります。
ここでは受取人設定が契約者本人の場合と契約者以外の場合の税金について詳しく解説します。
税負担の大小が大きく異なるため、2つのパターンの違いを把握しておくことが大切です
受取人が本人の場合
満期保険金や解約返戻金を契約者本人が受け取る場合は所得税の課税対象になります。
所得税には給与所得や事業所得など10種類があり、それぞれ課税対象となる金額の計算方法が異なります。
基本的には保険金の金額がそのまま課税対象となるのではなく、経費や特別控除額を差し引いた金額が課税対象です。
生命保険の保険金を受け取った際は一時所得として扱われ、以下の計算式で一時所得の金額を計算します。
一時所得の金額=(保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×1/2
ただし、保険契約から5年以内に受け取った満期保険金や解約返戻金は、一律20.315%が課せられる源泉分離課税となります。
受取人が本人以外の場合
生命保険の受取人が契約者本人以外の場合、契約者・被保険者・受取人の関係によって課税される税金の種類が変わります。
課税される税金の種類は以下のとおりです。
| 税金の種類 | 契約関係 | 控除額 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 相続税 | 契約者=被保険者 受取人は相続人 | 500万円×法定相続人数 | 夫が契約者・被保険者 妻が受取人 |
| 贈与税 | 契約者≠被保険者 契約者≠受取人 | 年間110万円 | 夫が契約者 妻が被保険者・受取人 |
受取人の設定によって税負担が大きく変わるため、契約時には税金面も考慮した選択が重要になります。
生命保険の保険金受取人を契約者本人にしたときの年末調整のポイント

年末調整とは会社員や公務員の給与から源泉徴収で天引きされていた1年間の所得税の合計額と本来徴収されるべきその年の所得税の総額を再計算し、過不足を調整する手続きです。
生命保険料控除など、一部の所得控除は年末調整で申告できるため、確定申告をせずに年末調整だけで済む人も多いです。
しかし、保険金を受け取った年は注意する必要があります。
解約返戻金や満期保険金を受け取った年には、給与所得以外の所得税の課税額が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
その年の所得が給与所得と一時所得のみの場合、以下の計算式で70万円を超えない場合は確定申告は不要です。
一時所得の金額=(保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×1/2
保険金の他に一時所得に該当する所得は、クイズの賞金や公営ギャンブルの払戻金などが該当します。
確定申告が必要な年にもかかわらず、確定申告を忘れてしまうとペナルティとして余分に税金を納める必要があります。
まとめ:生命保険の死亡保険金受取人を契約者本人にできる?自分で受け取るのは可能?

生命保険の死亡保険金を契約者本人に設定することは可能です。被保険者が自分以外であれば、死亡保険金を自分で受け取れます。
また、貯蓄型の保険の場合も解約返戻金や満期保険金を契約者本人に設定できます。
ただし、生命保険の保険金を受け取った際には税金が発生することがあるため注意が必要です。
保険金に関連する税金には所得税、相続税、贈与税があります。
<関連サイト>
生前対策には様々な種類があります。こちらも参考にしてみてください。