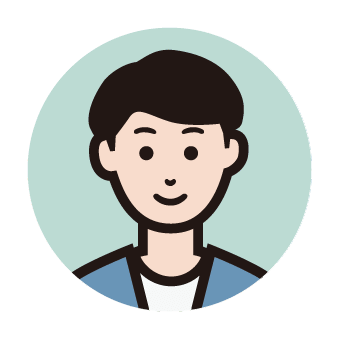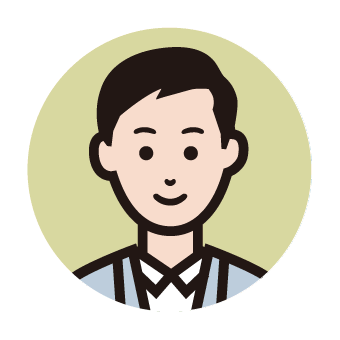内容をまとめると
- 基本的に、子どもの健康保険は「年間収入が多い方」の扶養に入れる。ただし、育児休業中は被扶養者の異動は必要なく、育休中の扶養継続も可能になります。
- ただし、各家庭によって最適な家計の状況は異なり、自分に合った節税効果の高い方法を選ぶのがポイント。
- 「マネーキャリア」のようなFP相談サービスなら、複雑な扶養や社会保険の手続きを詳しく教えてもらえる。また、家計の見直しから将来のライフプランまで無料で何度でも提案可能です。

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 妻の方が収入が多い場合、育休中の子どもの扶養はどうなる?
- 子どもの健康保険は「年間収入が多い方」の扶養に入れるのが原則
- 育児休業中は被扶養者の異動は必要ない
- 新たに産まれた子どもは改めて認定手続きを行う
- 子どもを扶養に入れるときの手続きは?
- 社会保険の扶養手続きに必要な書類一覧
- 扶養認定を削除する場合は片方の保険者の認定確認後に行なう
- 共働き夫婦の子どもの扶養についてよくある質問
- 子どもの扶養が不認定だった場合の手続きはどうなりますか?
- 子どもを夫の扶養にした場合、育休手当に影響はありますか?
- 年の途中でも子どもの扶養は変更できますか?
- 扶養制度を上手に活用したい方におすすめのサービス
- 【まとめ】育休中の子どもの扶養の手続きは早めに相談・準備をしよう
妻の方が収入が多い場合、育休中の子どもの扶養はどうなる?
扶養には大きく分けて「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類があり、それぞれの扶養は、目的や条件が異なります。
| 税法上の扶養 | 健康保険上の扶養 | |
|---|---|---|
| 目的 | 所得税や住民税の負担軽減 | 健康保険の保険料負担を軽減し、 被扶養者も保険給付を 受けられるようにすること |
| 対象 | 配偶者、16歳以上の子供 親族など ※16歳未満の扶養親族は 住民税の非課税限度額の 算定には含まれます。 | 主に配偶者、子供、 親、兄弟姉妹など |
| 収入の基準 | ・年間合計所得金額が48万円以下 (給与収入のみの場合は103万円以下) | ・年間収入が130万円未満 (60歳以上または障害者の場合は180万円未満) ※被保険者の年収の 2分の1未満であること |
税法上の扶養は「税金の控除を受けるための制度」ですが、健康保険上の扶養は「健康保険の給付を受けるための制度」です。この記事では健康保険上の扶養について解説します。
妻の方が収入が多い場合、育休中の子どもの扶養について下記の3点を紹介します。
子どもの健康保険は「年間収入が多い方」の扶養に入れるのが原則
共働き家庭における健康保険の扶養者に関するルールについて、下記のような条件が設けられています。
- 被扶養者となる人数に制限はなく、収入が高い方を被扶養者とします。
- 収入格差が少ない夫婦(年収の多い方の1割以内)では、届出により、主に家計を支える方が被扶養者として認められます。
- 共済組合員(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)の組合員である夫婦のどちらかまたは両方が扶養手当等の支給を受けている場合、その者の被扶養者として認定されます。
育児休業中は被扶養者の異動は必要ない
通常、夫婦間で収入の変動があった場合、収入の多い方の扶養に家族を入れる必要があります。しかし、育休中は一時的に収入が減少するため、この原則に従うと頻繁な扶養者の異動が発生し、手続きが煩雑になります。
そのため、厚生労働省の通知により、育休中の一時的な収入の変動は、特例として扶養者の異動を行わなくてもよいとされています。これは、被扶養者の地位を安定させるためです。
よって、妻の方が収入が多い家庭で、妻が育児休業を理由に、夫との収入が一時的に逆転した場合でも、休業中の異動手続きは不要となります。
新たに産まれた子どもは改めて認定手続きを行う
産まれたばかりの子供に関しては上記の『子どもの健康保険は「年間収入が多い方」の扶養に入れるのが原則』に記載のルールに沿って改めて認定手続きを行います。
育児休業が終わった後、収入状況に変化があったなど、場合によっては夫の扶養と判断される可能性もあります。
健康保険組合によっては、独自のルールを設けている場合もあるので、詳しくは自身の加入している組合に確認しましょう。
生まれた子ども被扶養者として健康保険に加入させるために、「被扶養者(異動)届」という書類を勤務先の会社、または加入中の健康保険組合に提出する必要があります。 この届出は、子どもが生まれたことによって、新たに被扶養者が増えたことを知らせるためのものです。
子どもが生まれたという事実は、自動的に伝わるわけではありません。 そのため、加入者自身が手続きを行う必要があるので注意しておきましょう。
子どもを扶養に入れるときの手続きは?

子どもがが生まれたり、自身の扶養に入れることになった場合、いくつかの手続きが必要になります。ここでは、子どもを扶養に入れる際の手続きについて、以下の2点を分かりやすく解説していきます。
社会保険の扶養手続きに必要な書類一覧
社会保険の扶養手続きに必要な書類は、状況によって異なります。ここでは、一般的なケースと、期日について解説します。
<準備が必要な書類一覧>
- 被扶養者(異動)届
- 戸籍謄(抄)本や住民票などの続柄を確認できる書類
- 源泉徴収票などの収入を確認できる書類
- 仕送り額がわかるもの
扶養認定を削除する場合は片方の保険者の認定確認後に行なう
夫婦の年収が逆転した場合、原則として収入が多くなった側の扶養に移す必要があります。このとき重要なのは、扶養認定の削除を行う保険者(健康保険組合など)は、年収が多くなった側の保険者が認定することを確認してから削除を行うという点です。
つまり、一方の保険者が一方的に削除するのではなく、もう一方の保険者との連携が必須となります。
具体的な手続きは以下の通りです。
- 収入が逆転した事実を双方の保険者に報告
- 収入が多くなった側の保険者に被扶養者認定の申請を行う
- 認定が確認された後、元の保険者で扶養削除の手続きを行う
共働き夫婦の子どもの扶養についてよくある質問
ここでは、共働き夫婦の子どもの扶養について、よくある質問とその答えをまとめました。ぜひ参考にして、夫婦にとって最適な選択を見つけてください。
子どもの扶養が不認定だった場合の手続きはどうなりますか?
保険者が被扶養者と認めないという決定をした場合には、次のように定められた手順に従って、被扶養者を決めることになっています。
- 扶養を認めない保険者は、「不認定通知書」を発行し、理由や被保険者の標準報酬月額、決定日などを記載する。
- 別の保険会社に対して、もう一方の配偶者を被扶養者として登録するためには、1の「不認定の通知」を添付して届出を行う。
- 保険者が2の届出を受けた後、1の「不認定の通知」に疑義を持った場合、5日以内に保険者同士で協議が行われる。
- もし3で合意が得られない場合は、最初に扶養届出が提出された月の標準報酬月額が高い被扶養者とする。
- 夫婦の標準報酬月額が等しい場合、届出により生計を主に維持する方を被扶養者とする。
- 5に異議を唱える場合、地方厚生局に申し立てて間に入ってもらう。
子どもを夫の扶養にした場合、育休手当に影響はありますか?
結論としては基本的に影響はありません。育休手当(育児休業給付金)は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に支給される給付金です。
この手当は、雇用保険から支給されるものであり、支給額は被保険者の所得や勤務形態によって決まります。扶養の有無は支給額には影響しませんので、安心して育児休業を取得できます。
育休手当は、育児休業を取得した際に受け取ることができる大切な給付金です。しっかりとした手続きを踏んで申請し、育児と仕事の両立を支援してくれる制度を活用しましょう。
年の途中でも子どもの扶養は変更できますか?
はい、可能です。
社会保険上の扶養は、扶養の事実が発生した時点でその都度手続きを行います。例えば、以下のような場合が考えられます。
- 夫婦間で収入の逆転が生じた場合
- アルバイトなどで一定以上の収入を得るようになった場合
- 就職した場合
手続きとしては、扶養者の勤務先に「被扶養者異動届」などの必要書類の提出が必要です。
健康保険組合に加入している方は、必要な手続きや書類提出について、勤務先を通じて申請することが一般的です。健康保険組合によっては、手続き期限が設定されている場合もありますので、早めに必要書類を揃えておくことが大切です。
手続き方法や必要書類については、加入中の保険者に直接確認することをおすすめします。保険者によって異なる場合がありますので、加入中の健康保険組合等のルールを把握しておきましょう。
扶養制度を上手に活用したい方におすすめのサービス

- お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、年収や節税について知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選。
- 資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能。
- マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇る。

【まとめ】育休中の子どもの扶養の手続きは早めに相談・準備をしよう
本記事では、妻のほうが収入が高い場合の育休中の子どもの扶養について、詳しく解説しました。
育休中に新たに生まれてくる子どもの扶養手続きは、早めの相談と準備が大切です。出産後の検診や、場合によっては医療機関の受診などで、子どもの健康保険証が必要になることがあるため、事前に話あっておくべきです。
もちろん、後から手続きをすることも可能ですが、スムーズに対応するためにも、育休に入る前から会社に相談しておくのがベストです。
ただし、扶養に関する制度は複雑で分かりにくい部分もあるため、疑問点があれば、会社の担当者や専門家に相談することも一つの方法といえます。そこでまずは、「マネーキャリア」で早めの相談と準備で、安心して出産・育児に臨めるよう体制を整えるのがおすすめです。
マネーキャリアなら、何度でも無料相談ができるため、回数や時間の心配がなく、いつでも無料で専門家に相談できます。スマホ一つで相談が可能なので、自宅にいながら気軽に利用可能です。ぜひこの機会にぜひ一度お試しください。