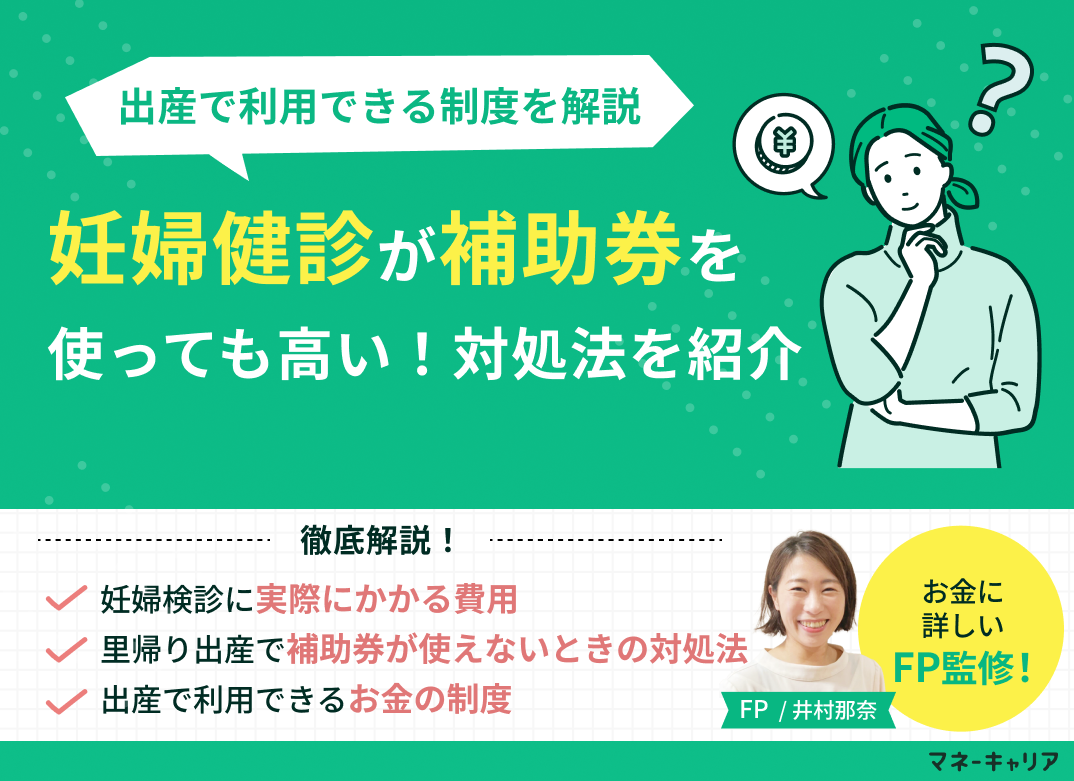
「妊婦検診って補助券があるのに、どうしてこんなに高いの?」
「里帰り出産したら補助券が使えなかった…これって自己負担になる?」
そんなモヤモヤや不安を感じている妊婦さんやご家族は多いでしょう。
結論からお伝えすると、補助券があっても自己負担が発生するのはよくあることです。
ただし、制度を正しく理解し、活用できるお金の仕組みを押さえれば、出産にかかる費用はしっかりカバーできます。
この記事では、妊婦検診で実際にかかる費用や補助券の使い方、里帰り出産時の対応方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
・「妊婦検診の費用が不安」
・「出産費用を少しでも抑えたい」
そんな方は、本記事を読むことで制度の正しい知識と費用の対策法を知り、お金の不安を軽減できます。
内容をまとめると
- 妊婦検診は補助券を使っても一部自己負担がある
- 里帰り出産時の補助券使用には条件と手続きが必要
- 出産に使える制度や控除をまとめて解説
- 生活費の見直しやお金の計画で出産後も安心
- マネーキャリアでは家計設計や支援制度の活用方法を無料で相談できる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
妊婦検診は補助券を使っても高い?実際にかかる費用
妊婦検診は補助券を利用しても、追加の検査や医療機関の費用設定によっては、総額で数万円の自己負担が発生する可能性があります。
一般的に妊婦検診は合計14回程度行われ、すべての検査を受けた場合、トータルで10万~15万円かかるとされています。
こども家庭庁によると、公費による補助の全国平均額は108,481円とのこと。
参照:こども家庭庁:「妊婦健康診査の公費負担の状況に係る調査結果について(令和5年4月1日現在) 」
全国平均の補助額から見た場合、おおよそ5万円程度の自己負担となるケースも少なくありません。
里帰り出産で妊婦検診の補助券が使えないときは?
里帰り出産をする場合、住んでいる自治体から出る補助券が出産する病院で利用できず、自己負担が大きいと感じている方もいるでしょう。
里帰り出産で妊婦検診の補助券が使えなかった場合も、償還払い申請をすれば後から補助金を受け取ることができます。
償還払い申請について、
- 妊婦検診時の支払い
- 申請方法
- 申請に必要な書類
妊婦検診時の支払い
里帰り出産で補助券が使えなかった場合、まずはその場で検診費用を全額自己負担します。
通常の検診内容であっても、1回数千円〜1万円以上かかるケースもあるでしょう。
申請方法
申請方法は、住んでいる自治体の保健センターや役所窓口に確認しましょう。
多くの自治体では「妊婦健康診査費助成申請書」など専用の様式を設けています。
申請に必要な書類
申請には、以下のような書類が必要になります。
- 妊婦健康診査費助成申請書兼請求書
- 母子健康手帳の「妊娠中の経過」欄のコピー
- 未使用の妊婦検診受診票または補助券
- 検診費用の領収書と明細書
- 振込先の金融機関の通帳コピー(本人名義)
- 印鑑または押印不要の場合は署名
- 支払金口座振替依頼書など
出産で利用できるお金の制度
出産前後では、さまざまな公的制度によって金銭的なサポートを受けられます。
一時的な出費が重なる時期ですが、制度を知って活用することで家計の負担を大きく減らせるでしょう。
- 傷病手当金
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 高額療養費制度
- 児童手当
- 医療費控除
これらの制度について、以下で1つずつ詳しく解説していきます。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで仕事ができない場合に支給される制度ですが、妊娠中のつわりや切迫流産などで就労が困難になった場合も対象です。
妊娠している本人が健康保険に加入しており、連続して3日間休み、4日目以降も仕事ができない状態が続くと支給対象になります。
出産手当金
出産手当金は、産前42日・産後56日の産休期間中に給与の支払いがない場合や減額された場合に支給される給付金です。
勤務先の健康保険に加入していることが条件で、1日あたり「標準報酬日額÷30×2/3」の金額が支給されます。
正確な金額ではありませんが、給与のおおよそ3分の2程度が受け取れるイメージです。
出産育児一時金
出産育児一時金は、赤ちゃん1人につき一律50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または妊娠週数22週未満の出産の場合は48.8万円)が支給される制度です。
加入している公的医療保険から支給され、直接支払制度を使えば病院の窓口での支払いを軽減できます。
高額療養費制度
医療費が一定の限度額を超えると、超えた分が払い戻されるのが高額療養費制度です。
帝王切開や妊娠中の入院治療などで、医療費の自己負担額が高額になった際にも活用できます。
児童手当
児童手当は、子どもが生まれた月の翌月から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで支給される給付金です。
原則として毎年6月・10月・2月に4ヵ月分まとめて振り込まれます。
医療費控除
医療費控除は、1年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えたときに、確定申告で所得税を軽減できる制度です。
出産に関わる費用(妊婦検診・分娩・入院など)も対象になります。
出産後も安定した生活を送るには?
出産は、家庭のお金の流れが大きく変わるタイミングです。
そのため、出産後も安定した暮らしを維持するには、家計の見直しと将来への備えが欠かせません。
出産前から以下のような準備ができていると、予期せぬ出費や育児中の収入減にも柔軟に対応できます。
- 生活費を見直す
- 将来のお金の見通しをクリアにする
- お金のプロに相談する
以下で、それぞれの内容を詳しく解説していきます
生活費を見直す
生活費を見直すことは、出産後の家計の安定に直結します。
育児用品や医療費など、新たに必要になる出費をカバーするためには、今ある支出のなかで削れる部分がないか確認することが重要です。
たとえば、通信費・保険料・サブスクなど、気づかぬうちに膨らんでいる固定費があるかもしれません。
将来のお金の見通しをクリアにする
将来に向けたお金の見通しを持つことで、精神的にも家計的にも安心できます。
教育費・住宅費・老後資金など、今後の大きな支出について時系列で把握し、いつ・いくら必要になるのかを具体的にシミュレーションしましょう。
お金のプロに相談する
お金の不安や疑問があるなら、お金のプロに相談するのがおすすめです。
将来のお金の見通しがわかるライフプラン表をFPが作成するため、効率的に将来設計を把握できます。
妊婦検診の費用に関するよくある質問
とくに初めての妊娠では、補助券の使い方や、どんな費用が自己負担になるのか戸惑うこともあるでしょう。
ここでは以下のような、妊婦検診に関する疑問にお答えします。
- 妊婦検診は受けなくてもいい?
- 補助券の対象ではない費用はある?
- 妊婦検診が高額になるケースとは?
制度の活用法を理解して、費用面でも安心して妊婦検診を受けられるようにしておきましょう。
妊婦検診は受けなくてもいい?
母体の健康状態や胎児の発育状況を定期的に確認し、万が一の異常を早期に発見するためにも、必ず妊婦検診を受診してください。
妊婦検診は法律で義務づけられてはいませんが、医療的には受けるべきものです。
補助券の対象ではない費用はある?
補助券を使っても、一部費用は自己負担になります。
たとえば、3D・4Dエコー、性別判定、個別相談、胎児スクリーニング検査などのオプション検査は対象外です。
妊婦検診が高額になるケースとは?
妊婦検診が高くつくのは、検査項目が多い初期や中期、または個人病院・私立病院を選んだ場合です。
血液検査や子宮頸がん検診などが含まれる回では、1回の費用が1~2万円になることも珍しくありません。
出産に伴いお金の不安があるなら「マネーキャリア」に相談
妊婦検診の費用は補助券があっても自己負担が発生しますが、里帰り出産時の償還払い申請や出産に利用できる制度を利用すれば、妊婦検診以外の負担額を抑えられます。
これから出産を迎える方は、まず受け取れる給付金を明確に把握することから始めてみてください。
とはいえ、「申請方法が複雑そう」「どの制度が使えるのかわからない」と悩む方も多いでしょう。
そんな方には「マネーキャリア」の無料相談がおすすめです。
出産費用や育児にかかるお金の相談が何度でも無料で、スマホから簡単に申し込み可能。
女性FPも多数在籍しているため、妊娠・出産に関する不安も安心して相談できます。
出産を控えて金銭面の不安がある方は、一度マネーキャリアに相談してみてはいかがでしょうか。




























