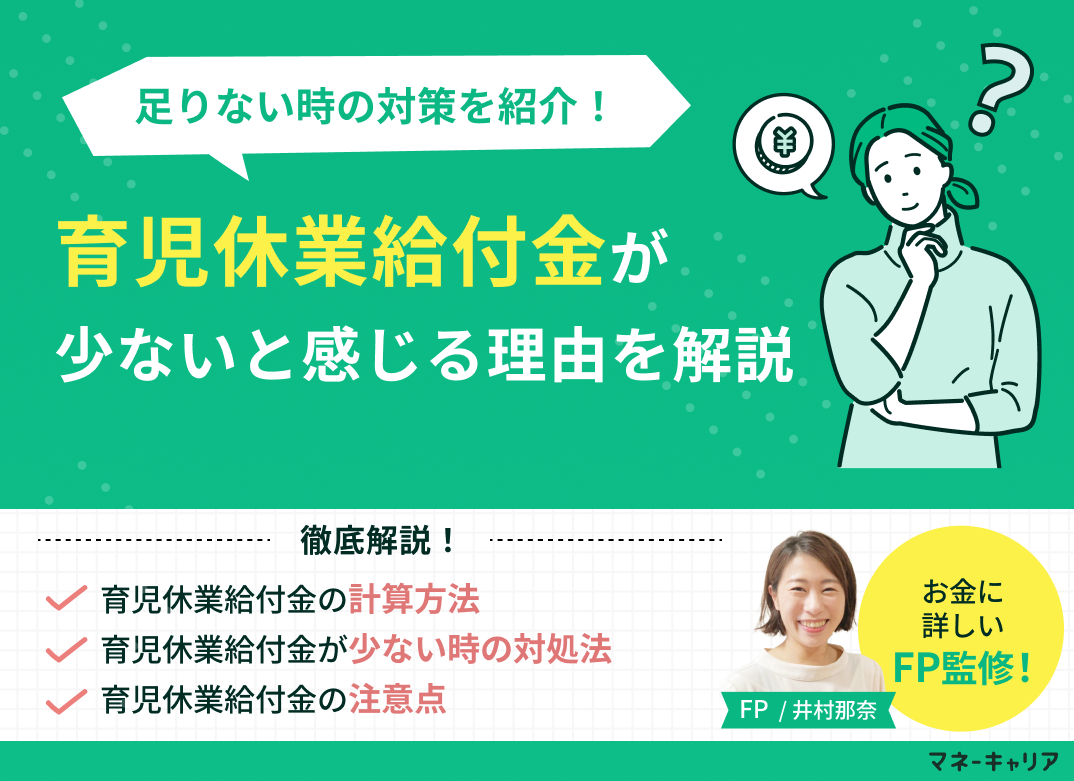
内容をまとめると
- 育児休業給付金は給与よりも少ないため家計管理が求められる
- 対策をせずにいると家計が赤字になるリスクがあるため注意が必要
- 子育てにかかる費用をシミュレーションして資金計画を立てておくと安心
- 家計の見直しや将来の資金計画についてはFPに相談するのがおすすめ
- マネーキャリアは相談実績10万件以上でお金の悩みを解決できる
- お金に関する相談なら実績が豊富なマネーキャリアが安心

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 育児休業給付金が少ないと感じる理由
- 支給額は給与より少なくなるため
- ボーナスが計算対象に含まれないため
- 育児休業給付金が少ないと感じるときの対策
- 家計を見直して支出を抑える
- スキマ時間を活用して副収入を得る
- 税金対策をして手取りを増やす
- 他の手当や支援制度を活用する
- お金の専門家(FP)に相談する
- 「少ない」といわれる育児休業給付金の注意点
- 給付金を受け取るには申請手続きが必要
- 減額・支給停止となる場合がある
- 「少ない」といわれる育児休業給付金の概要
- 支給要件
- 支給額
- 支給期間
- 支給タイミング
- 育児休業給付金が少ないことに関してよくある質問
- 育児休業給付金の支給額はどうやって決まりますか?
- 退職している場合でも給付金を受け取れますか?
- 育児休業給付金は課税対象ですか?
- 支給額が少なくなる月はありますか?
- 育児休業給付金だけでは生活が苦しいときはどうすればいいですか?
- 家計や子育て費用について相談したいときはどこを頼ればいいですか?
- 育児休業給付金が少ないと感じたら早めの対策が重要【まとめ】
育児休業給付金が少ないと感じる理由
育児休業給付金が少ないと感じられるのには、いくつかの理由があります。
- 支給額は給与より少なくなるため
- ボーナスが計算対象に含まれないため
支給額は給与より少なくなるため
育児休業給付金が少ないと感じる主な理由は、支給額が通常の給与より減るためです。
給付金は、以下の計算式で算出されます。
・育休開始から180日まで:休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%
・育休開始から181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×50%
「休業開始時賃金日額」は、育休開始前6ヶ月間の総支給額を180で割って算出される金額です。
支給率は67%または50%となるため、どうしても収入は育休前より少なくなります。
例えば、厚生労働者のシミュレーションによると、平均月収が約20万円の方の場合、180日目までは月額13万4,000円程度、181日目以降は10万円程度が支給されるとされています。
給与の約半分の収入になるため、家計を見直すなどの対策が必要です。
ボーナスが計算対象に含まれないため
育児休業給付金が少なく感じる理由の一つが「ボーナスが支給額の計算に含まれない」ことです。
給付金の算出には「休業開始時賃金日額」が使われますが、これは育休開始前6ヶ月間の給与総額(ボーナスは対象外)を180で割った金額です。
保険料控除前の基本的な給与のみが対象で、ボーナスは計算に反映されません。
そのため、ボーナスの割合が大きい働き方をしている方ほど、支給額が少なく感じる可能性があります。
育児休業給付金が少ないと感じるときの対策
育児休業給付金が少ないと感じるときは、早めに対策を取ることが大事です。
主な対策は、次のとおりです。
- 家計を見直して支出を抑える
- スキマ時間を活用して副収入を得る
- 税金対策をして手取りを増やす
- 他の手当や支援制度を活用する
- お金の専門家(FP)に相談する
家計を見直して支出を抑える
育児休業給付金が少ないと感じるときの対策の一つが、家計を見直して支出を抑えることです。
例えば、電気代、水道代、ガス代、保険料、交際費、通信費といった費用を見直すことで、毎月1万円以上の節約につながることもあります。
また、不要なサブスクを解約したり、スマホを格安SIM・プランに切り替えるといった工夫も、支出を抑える上で効果的です。
給付金が想定より少なくても、節約を心がけて支出を抑えることで、育児に集中できる安心した生活を維持しやすくなります。
スキマ時間を活用して副収入を得る
育児休業給付金だけでは少ないと不安を感じる場合、スキマ時間を活用して副収入を得るという選択肢もあります。
数千円〜数万円の収入があるだけでも、家計にゆとりが生まれ、精神的な安心感にもつながるでしょう。
最近では、短時間で取り組めるアルバイトや在宅ワークなど、育児の合間でも始めやすい仕事が増えています。
ただし、支給単位期間(育休開始日から1ヶ月ごとの期間)において、就業日数が10日を超えると、育児休業給付金の支給対象外となるため注意が必要です。
また、収入によっては給付金が支給停止や減額となる場合があります。
税金対策をして手取りを増やす
税金対策をして手取りを増やすことも、育児休業給付金が少ないと感じるときの対策の一つです。
各種控除を活用して節税を図れば、税負担を軽減でき、その分手元に残るお金を増やすことが可能になります。
例えば、育休中は夫が節税対策に取り組み、妻は復職後に節税に取り組むことで、給付金の不足をカバーすることができます。
主な控除は、以下のとおりです。
・寄附金控除
・住宅ローン控除
・特定支出控除 など
子育てには何かとお金がかかるため、税金対策には積極的に取り組むことをおすすめします。
他の手当や支援制度を活用する
育児休業給付金が少ないと感じる場合は、他の手当や支援制度の活用も検討してみましょう。
子どもが生まれると児童手当や児童扶養手当の対象になったり、自治体によっては出産に関連した独自の給付金が用意されていることもあります。
該当する制度を活用することで、家計の負担を軽減でき、安心して育児に専念しやすくなります。
特に自治体独自の給付金は申請期限が設けられていることも多いため、早めに内容を確認して、必要な手続きを忘れずに行いましょう。
お金の専門家(FP)に相談する
育児休業給付金の金額では生活が厳しいと感じる場合は、お金の専門家(FP)に相談してみるのも一つの方法です。
FPは、家計の現状やライフプランに応じて、支出の見直しや税金対策、子育てにかかる費用の準備方法など幅広いアドバイスをしてくれます。
また、教育資金や老後資金、マイホーム資金などの将来的に必要となるお金についても、具体的なシミュレーションを通じて、無理のない計画を提案してもらえます。
日々の家計管理だけでなく、将来への不安を軽減するためにも、専門家に相談してみましょう。
「少ない」といわれる育児休業給付金の注意点
育児休業給付金を受け取る上で、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
- 給付金を受け取るには申請手続きが必要
- 減額・支給停止となる場合がある
給付金を受け取るには申請手続きが必要
育児休業給付金を受け取るには、申請が必要なことを覚えておきましょう。
通常は、勤務先(事業主)が「受給資格確認手続き」と「支給申請手続き」を行います。
ただし、事業主ではなく本人がハローワークに申請書類を提出して手続きを行うことも可能です。
申請期限を過ぎてしまうと給付が受けられなくなる可能性もあるため、事前にスケジュールを確認して勤務先に早めに申請を依頼するか、自分で必要書類を準備して手続きを進めることが大切です。
減額・支給停止となる場合がある
育休中に仕事をして収入を得ると、育児休業給付金が減額されたり、支給されなくなったりする可能性があるため注意が必要です。
具体的には、1支給単位期間内に「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%以上の賃金が支払われた場合、育児休業給付金は支給されません。
また、80%未満であっても支給額が減額される仕組みです。
そのため、育休中に働くことを検討する際は事前にシミュレーションを行い、収入と給付金のバランスを確認しておくことが大切です。
「少ない」といわれる育児休業給付金の概要
育児休業給付金を正しく活用するためには、支給要件や支給額などの制度内容を理解しておくことが大事です。
内容を理解しておくことで、育休中の収入の見通しが立てやすくなり、家計のシミュレーションもしやすくなります。
- 支給要件
- 支給額
- 支給期間
- 支給タイミング
支給要件
育児休業給付金の支給要件は、次のとおりです。
・1歳未満の子どもを養育する目的で育児休業を取得した雇用保険の被保険者である
・育休開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間数が80時間以上)ある月が12ヶ月以上ある
・支給単位期間において就業日数が10日以下である(10日を超える場合は、就業時間が80時間以下である)
このような要件を満たすことで、育児休業給付金を受け取ることができます。
また、パート・アルバイト、契約社員など期間を定めて雇用される方は、養育する子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約の満了が明らかでない必要があります。
支給額
育児休業給付金の支給額は、次の計算方法で算出されます。
・育休開始から180日まで:休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%
・育休開始から181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×50%
育児休業の開始からの経過日数によって支給額は異なり、180日までは高めで181日目以降は減額されます。
「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前6ヶ月間に支払われた総支給額(ボーナスを除く)を180で割った金額です。
厚生労働省のモデルケースでは、平均月収が15万円の場合、育児休業開始から180日目までは月額約10万円、181日目以降は約7万5,000円が支給されるとされています。
また、平均月収が30万円程度であれば、180日目までは月額約20万1,000円、181日目以降は約15万円が支給される見込みです。
支給期間
育児休業給付金の支給期間は、原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日までです。
ただし、子どもが1歳になる前に復職した場合は、復帰日の前日までが支給対象となります。
また、保育所に入れないなど一定の条件を満たす場合には、支給期間が「1歳6ヶ月」や「2歳」まで延長されることもあります。
支給タイミング
育児休業給付金は、2ヶ月ごとにまとめて2ヶ月分が支給される仕組みです。
申請が受理されて支給が決定すると、おおむね1週間程度で給付金が振り込まれます。
育児休業給付金が少ないことに関してよくある質問
育児休業給付金が少ないことに関してよくある質問は、次のとおりです。
- 育児休業給付金の支給額はどうやって決まりますか?
- 退職している場合でも給付金を受け取れますか?
- 育児休業給付金は課税対象ですか?
- 支給額が少なくなる月はありますか?
- 育児休業給付金だけでは生活が苦しいときはどうすればいいですか?
- 家計や子育て費用について相談したいときはどこを頼ればいいですか?
育児休業給付金の支給額はどうやって決まりますか?
育児休業給付金の金額は、育休開始前の収入をもとに算出され、経過日数に応じて支給率が変わる仕組みになっています。
・育休開始から180日まで:休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%
・育休開始から181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×50%
上記のとおり、育休開始から181日目以降は、育児休業給付金の支給率が67%から50%に下がります。
退職している場合でも給付金を受け取れますか?
育児休業給付金は職場復帰を前提とした制度であるため、基本的に退職すると受給の対象外となります。
ただし、退職日が支給単位期間の末日である場合は、給付金が支給されます。
育児休業給付金は課税対象ですか?
支給額が少なくなる月はありますか?
育児休業給付金の支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×支給率」で算出され、育休の経過日数に応じて支給率が変わる仕組みになっています。
支給率は、育休開始から180日までは67%で、181日目以降は50%に減額されます。
支給額が途中で下がることを踏まえて、資金計画を立てておくことが大切です。
育児休業給付金だけでは生活が苦しいときはどうすればいいですか?
育児休業給付金だけでは生活が苦しいと感じたときは、支出を見直して家計を引き締めることが大切です。
育児休業給付金は通常の給与より少ないため、それまでと同じ生活を続けていると赤字になる可能性があります。
固定費や日々の出費を見直して、収入が減ってもやりくりできる家計にすることが重要です。
そうすることで経済的な不安が減り、子育てに集中できるようになります。
家計の見直しに自信がない場合は、FPなどの専門家に相談することを検討してみましょう。
家計や子育て費用について相談したいときはどこを頼ればいいですか?
「家計の見直し方がわからない」「子育てにどれくらい費用がかかるのか不安」と感じている方は、FPへの相談を検討してみましょう。
FPに相談すれば、家計の状況に合った見直しポイントや節約方法、子育て費用のシミュレーションなど、具体的なアドバイスが受けられます。
マネーキャリアなら、FPに何度でも無料相談が可能です。
また、家計の見直しや子育て費用だけでなく、保険、住宅ローン、税金対策、資産形成など幅広いお金の悩みに対応しています。
オンライン相談にも対応しているため、自宅にいながら専門家に相談できます。
育児休業給付金が少ないと感じたら早めの対策が重要【まとめ】
育児休業給付金は、通常の給与よりも支給額が少なく、経過日数によって支給率が下がるため「思ったより少ない」と感じる方も少なくありません。
給付金だけでは生活費が足りず赤字に陥るリスクもあるため、家計の見直しなどの対策が必要です。
対策を講じることで、お金の不安を軽減し、子育てにも集中しやすくなります。
そのため「育児休業給付金が少ない」「このままだと赤字かも」と感じたら、早めにFPなどの専門家に相談し、現実的な解決策を見つけて取り組みましょう。




























