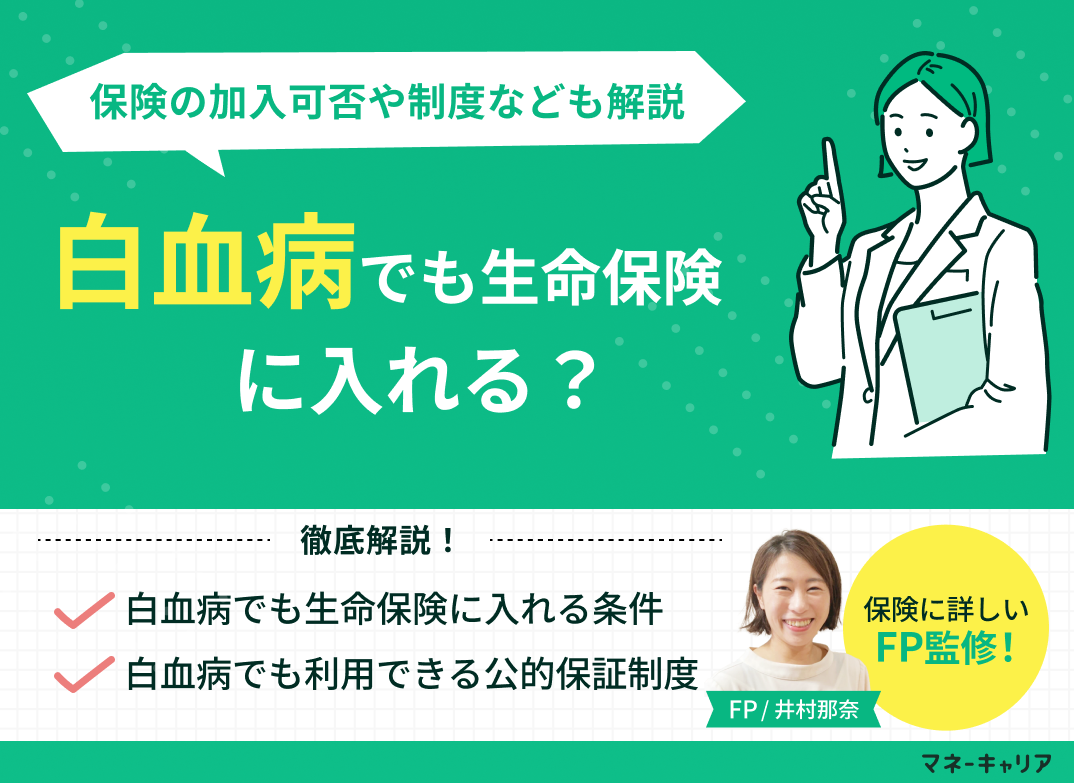「自己免疫性肝炎になると保険に入れないって本当?」
「自己免疫性肝炎でも加入できる保険があるか知りたい」
とお悩みではないでしょうか。
- 結論、自己免疫性肝炎でも生命保険に加入できる可能性はありますが、条件や保険会社によって大きく異なります。
この記事では自己免疫性肝炎の方が保険に加入する方法や対処法を紹介します。
この記事を読むことで、自己免疫性肝炎でも最適な保険を見つける方法がわかり、将来の不安を軽減できるようになるので、ぜひご覧ください。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
自己免疫性肝炎でも生命保険に入れる可能性はある
例えば、完治後2年以上経過している場合や、症状が安定している場合には、通常の生命保険に加入できるケースがあります。
ただし、保険会社によって引受基準が異なるため、複数の保険会社で審査を受けることが重要です。
また、病状の詳細や治療経過によっては、条件付きでの加入や引受基準緩和型保険での加入となる場合もあります。
そのため、単に加入できる保険を探すのではなく、よりよい条件で加入できる保険を探すことが重要です。
自己免疫性肝炎とは?症状と治療について解説
自己免疫性肝炎とは、本来体を守るはずの免疫が、誤って自身の肝臓の細胞を攻撃してしまう慢性的な肝疾患のことです。
主な症状には倦怠感、黄疸、食欲不振などがあり、進行すると肝硬変や肝不全に至る可能性があります。
主な治療方法としては免疫抑制剤を用いた薬物療法などがあり、治療費は月額約3~5万円程度かかることが多いです。また、症状が重い場合は社会復帰するまでに数ヶ月から数年間の療養が必要になるケースもあります。
このような長期的な治療費や収入減少に備えるため、適切な保険への加入が重要となります。
自己免疫性肝炎で生命保険に入れない場合の対処法
自己免疫性肝炎で生命保険に入れない場合の対処法は以下のとおりです。
- 引受基準緩和型保険を検討する
- 障害者手帳を取得する
- 障害年金などの公的保障制度を活用する
これらの対処法を理解して、自分に合った保障を確保しましょう。
引受基準緩和型保険を検討する
引受基準緩和型保険は告知項目が3~5項目程度と少なく、自己免疫性肝炎の方でも加入できる可能性が高い保険です。
▼引受基準緩和型保険の告知項目の例
- 最近3カ月以内に、医師から入院・手術をすすめられたことがある
- 過去2年以内に、入院・手術をしたことがある
- 過去5年以内に、がん・上皮内がん、肝硬変、統合失調症、認知症、アルコール依存症で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがある
ただし、保険料が通常の保険より割高になり、保障額に上限がある場合が多いです。また、加入から1年間は保障額が半額になる「削減期間」が設けられていることもあります。
そのため、自分は引受基準緩和型保険に加入した場合にどれくらいメリットがあるのか見極めることが重要です。
障害者手帳を取得する
自己免疫性肝炎の症状が重い場合、障害者手帳を取得できる可能性があります。
障害者手帳とは、身体的・精神的な障害がある方が、様々な福祉サービスや支援を受けるために交付される手帳の総称です。
例えば肝機能障害で身体障害者手帳(1級~4級)を取得すると、医療費の助成や税金の減免などの支援を受けられます。
また、障害者手帳があることで、交通機関の割引や補装具費の支給、障害者雇用などの支援を受けることができます。
経済的な負担を軽減するためにも、条件に該当する場合は積極的に申請することをおすすめします。
障害年金などの公的保障制度を活用する
自己免疫性肝炎により就労が困難になった場合、以下のような公的保障制度を活用できる場合があります。
また、会社員の場合は傷病手当金により、最大1年6ヶ月間、給与の約3分の2を受け取ることができます。
さらに、高額療養費制度を用いれば医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、超えた分の払い戻しを受けることができます。
これらの公的制度を適切に活用することで、経済的な負担を大幅に軽減できます。
自己免疫性肝炎に関するよくある質問
自己免疫性肝炎に関するよくある質問として以下について解説します。
- 自己免疫性肝炎は難病指定ですか?
- 給付金額はいくらですか?
- 手術代はいくらですか?
よくある質問への解説を見て、不安や疑問点を解消しましょう。
自己免疫性肝炎は難病指定ですか?
厚生労働省により「指定難病」として認定されており、医療費助成制度の対象となります。月額の医療費負担には上限が設けられ、所得に応じて2,500円~30,000円程度の自己負担で治療を受けることができます。
この制度により、長期的な治療が必要な方の経済的負担が大幅に軽減されます。
ただし、難病医療費助成制度を利用するには、指定医療機関での診断と都道府県への申請が必要な点には注意しましょう。
給付金額はいくらですか?
自己免疫性肝炎で受けられる給付金額は、制度によって異なります。
例えば、障害基礎年金の場合、1級で年額約104万円、2級で年額約83万円が支給されます。
また、傷病手当金は標準報酬日額の3分の2が最大1年6ヶ月間支給され、月収30万円の場合は月額約20万円となります。
| 制度名 | 給付額(年額) |
|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 約104万円 |
| 障害基礎年金2級 | 約83万円 |
| 傷病手当金 | 給与の約67% |
そして、追加で保険に入っている場合は上乗せとして入院給付金や手術給付金などを受け取ることができます。
手術代はいくらですか?
自己免疫性肝炎の手術代は、手術の種類や病院によって大きく異なります。
例えば肝生検の場合、保険適用で約4万円程度の自己負担となります。
重症化して肝移植が必要になった場合、3割負担の方の支払額は500万円程度になり、上乗せで高額医療費制度を活用することで更に自己負担を抑えることができます。
ただし、入院中の差額ベッド代や食事代、交通費などは別途必要となるため、トータルの費用は高額のままである可能性があります。
そのため、専門家(FP)に相談して、保障プランを備えることがおすすめです。
自己免疫性肝炎の保険加入でお悩みならマネーキャリアに相談!
ここまで、自己免疫性肝炎でも保険に加入する方法や対処法、よくある質問などを紹介してきました。
内容をまとめると以下のとおりです。
- 自己免疫性肝炎でも完治後2年以上経過していれば通常の保険に加入できる場合がある
- 引受基準緩和型保険なら加入しやすく、最低限の保障を確保できる
- 難病指定により医療費助成制度が利用でき、経済的負担を軽減できる
- 公的給付制度と民間保険を組み合わせることで十分な保障を確保できる
- 保険会社によって審査基準が異なるため、複数社での比較検討が重要
しかし、自己免疫性肝炎では最適な保険選びや公的制度との組み合わせ方法の判断が困難な場合があります。
そこでおすすめなのが、マネーキャリアの保険無料相談窓口への相談です。
マネーキャリアでは、持病をお持ちの方の保険選びや公的制度を活用した最適な保障設計をサポートいたします!
相談料は無料なのでお気軽にご相談ください!