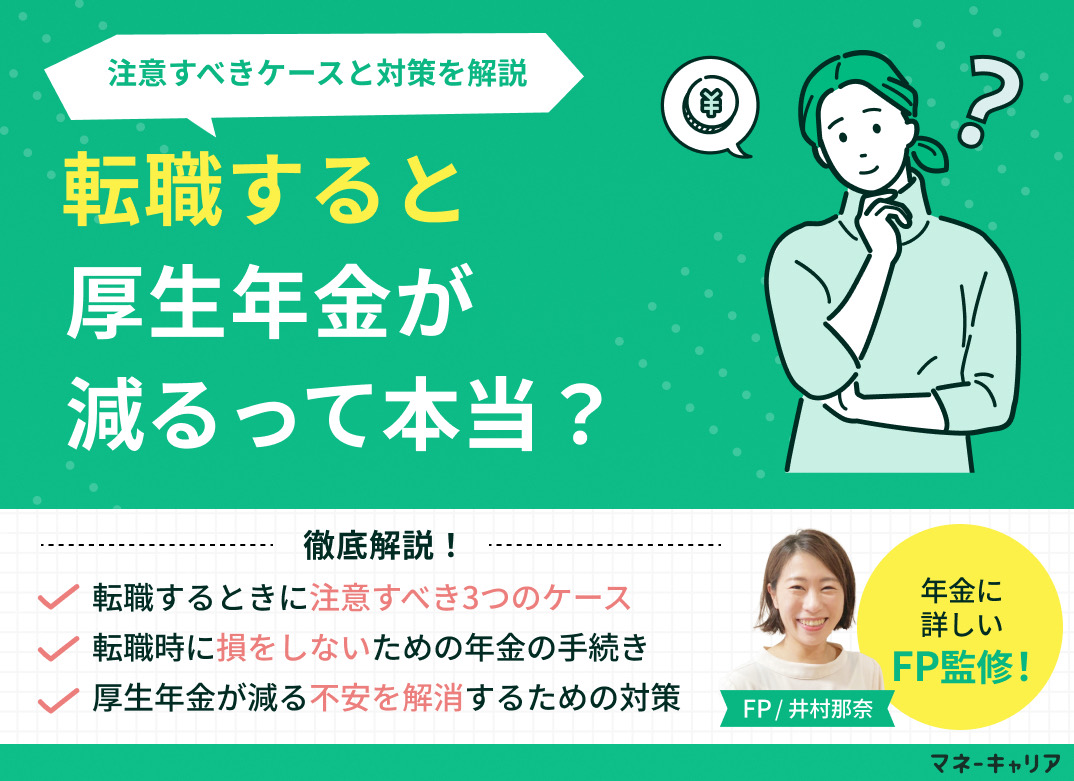NEW ARTICLES新着記事
-
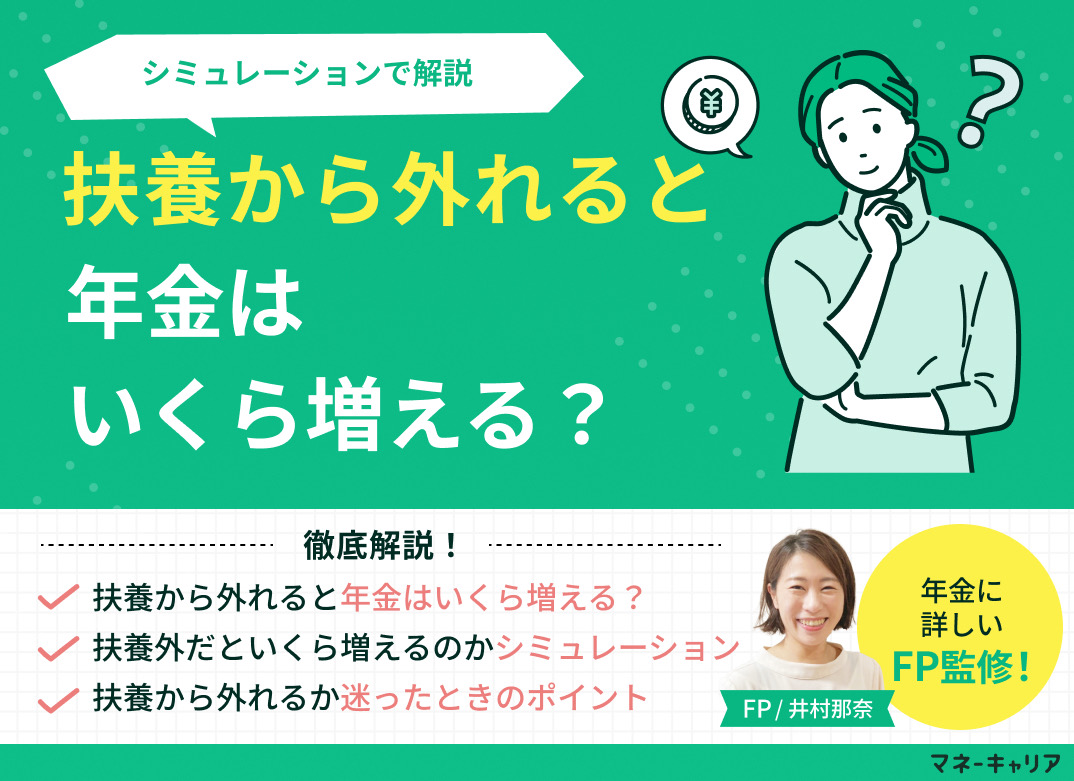 扶養から外れると年金はいくら増える?シミュレーションで解説
扶養から外れると年金はいくら増える?シミュレーションで解説2025-09-19
-
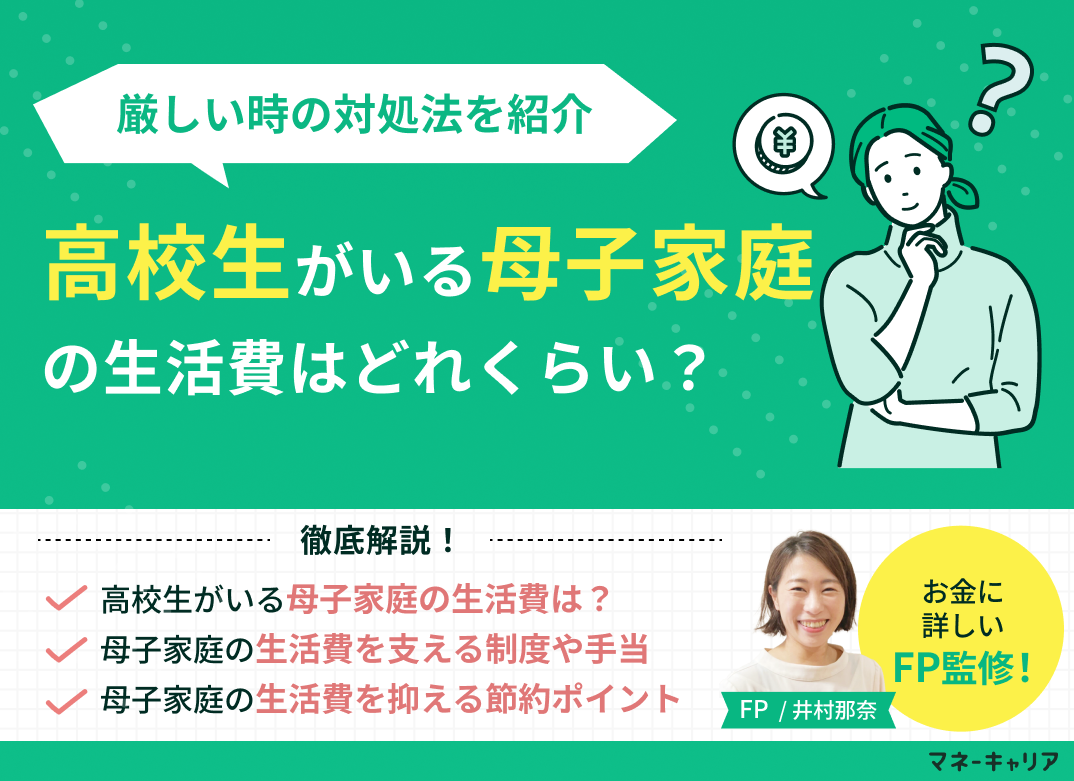 高校生がいる母子家庭の生活費は?節約ポイントや厳しいときの対処法
高校生がいる母子家庭の生活費は?節約ポイントや厳しいときの対処法2025-09-19
-
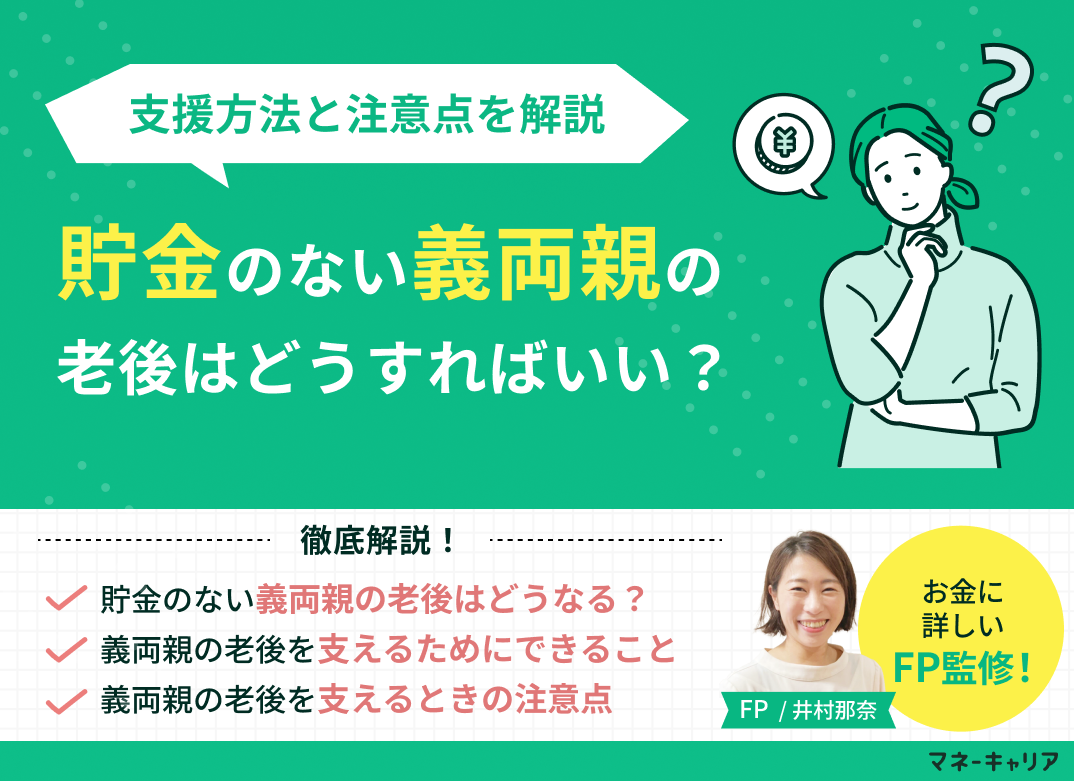 貯金のない義両親の老後はどうすればいい?支援方法と注意点を解説
貯金のない義両親の老後はどうすればいい?支援方法と注意点を解説2025-09-19
-
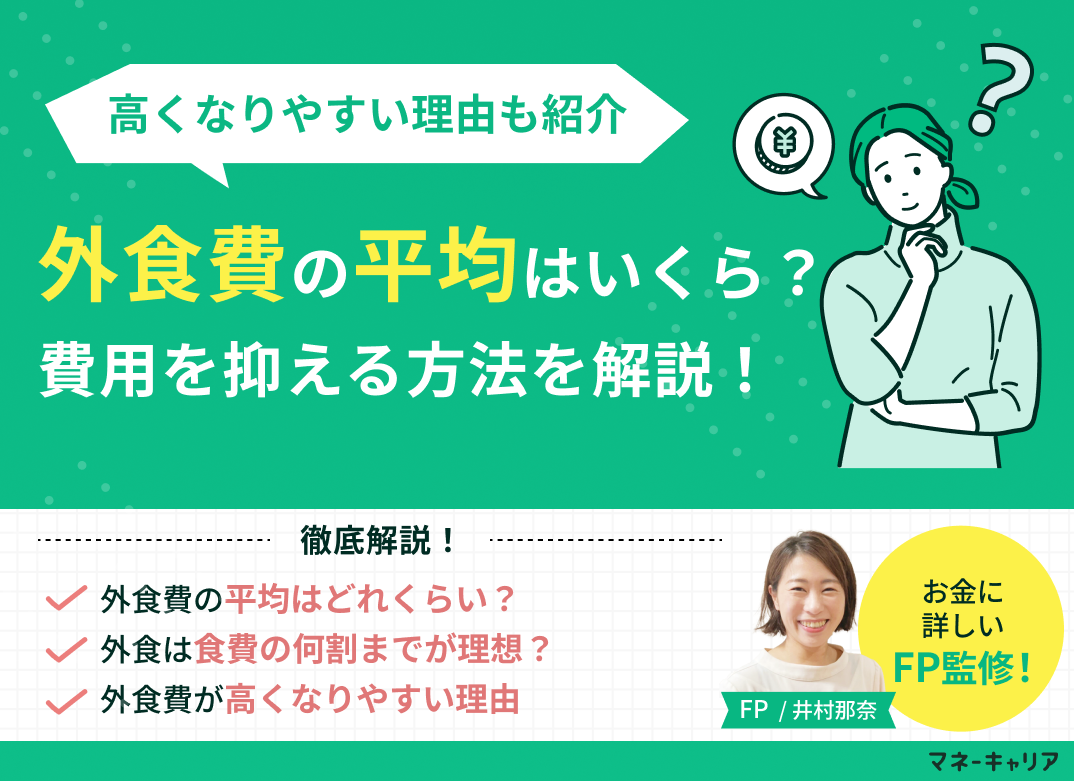 外食費の平均はいくら?高くなりやすい理由や費用を抑える方法を解説
外食費の平均はいくら?高くなりやすい理由や費用を抑える方法を解説2025-09-19
-
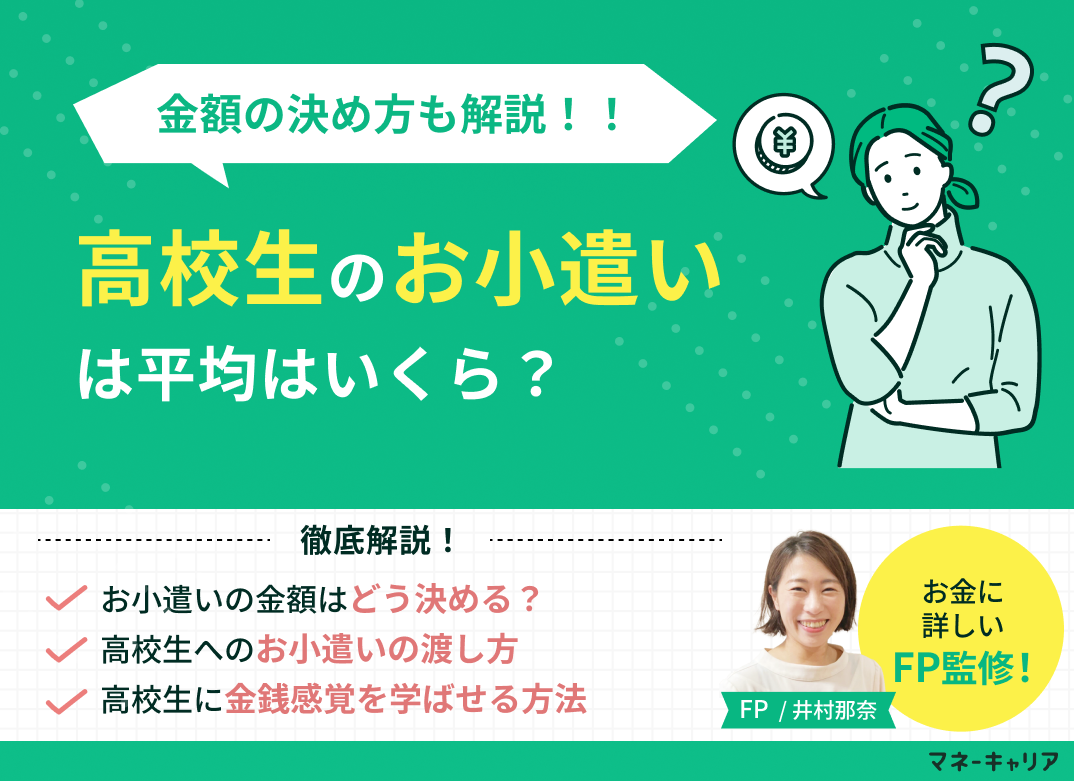 高校生のお小遣いは平均いくら?金額の決め方や金銭感覚を学ばせる方法
高校生のお小遣いは平均いくら?金額の決め方や金銭感覚を学ばせる方法2025-09-19
-
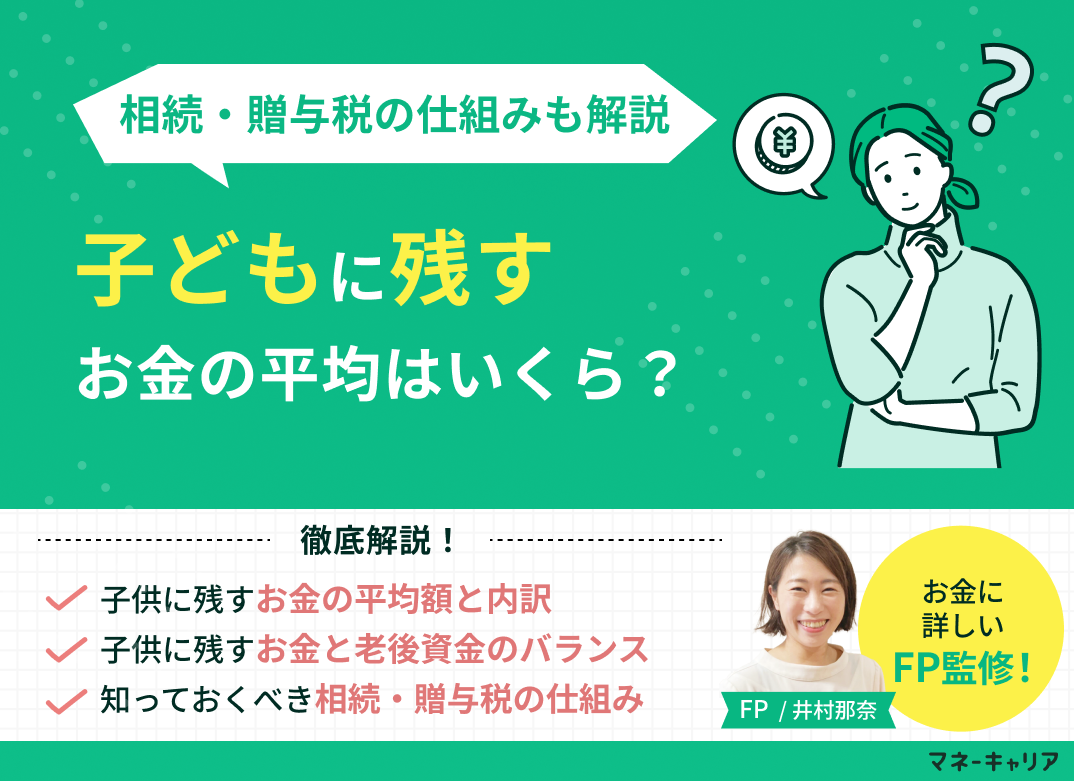 子供に残すお金の平均はいくら?相続・贈与税の仕組みとお金の準備方法
子供に残すお金の平均はいくら?相続・贈与税の仕組みとお金の準備方法2025-09-19
-
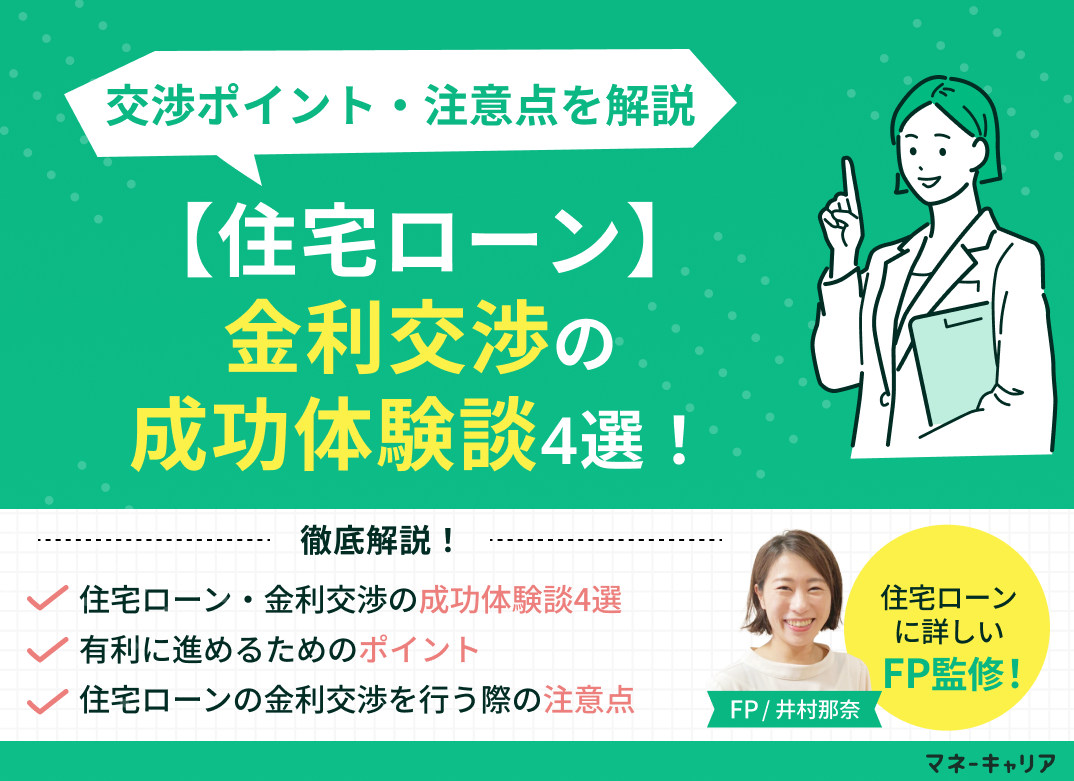 【住宅ローン】金利交渉の成功体験談4選!交渉ポイント・注意点を解説
【住宅ローン】金利交渉の成功体験談4選!交渉ポイント・注意点を解説2025-09-18
-
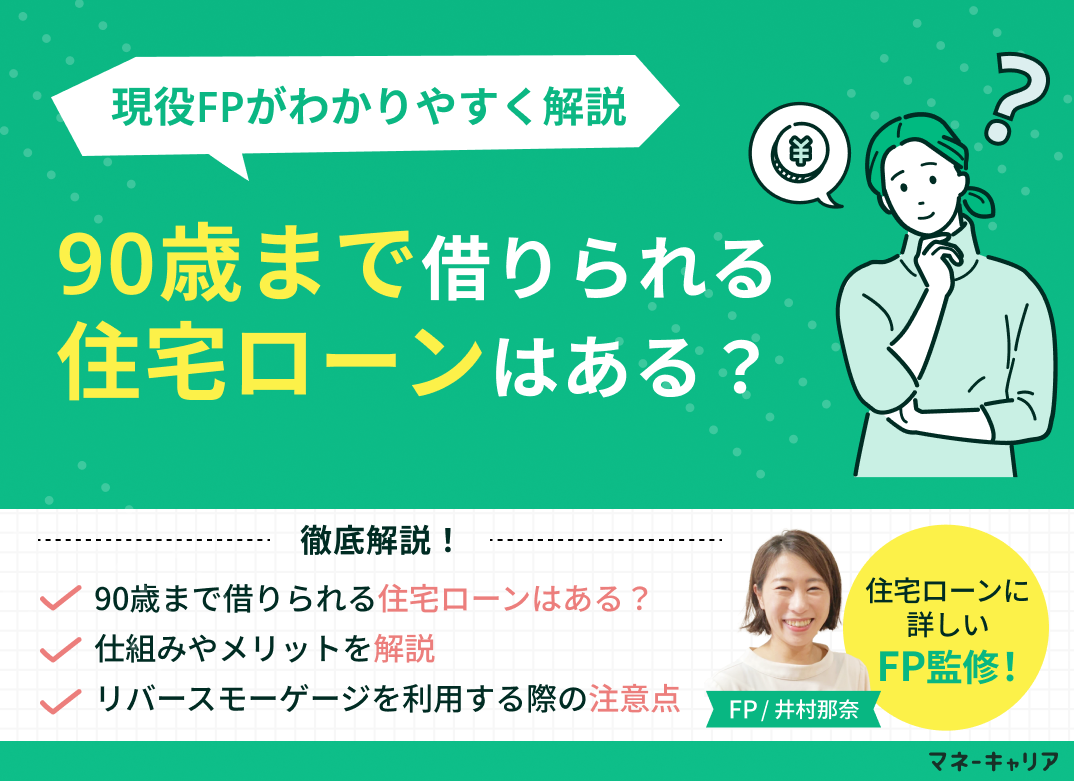 90歳まで借りられる住宅ローンはある?現役FPがわかりやすく解説
90歳まで借りられる住宅ローンはある?現役FPがわかりやすく解説2025-09-18
-
 転職で住宅ローンの金利は変わる?返済中に気をつけたい注意点を解説
転職で住宅ローンの金利は変わる?返済中に気をつけたい注意点を解説2025-09-18
-
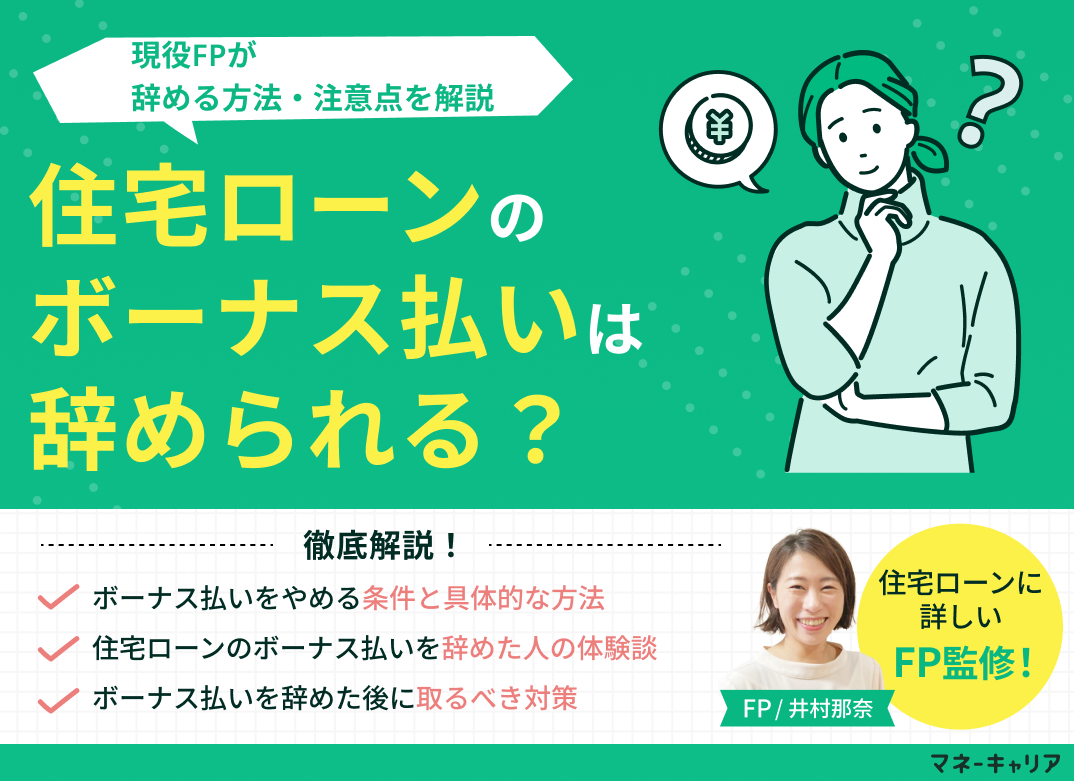 住宅ローンのボーナス払いを辞められる?辞める方法・注意点を解説
住宅ローンのボーナス払いを辞められる?辞める方法・注意点を解説2025-09-17
-
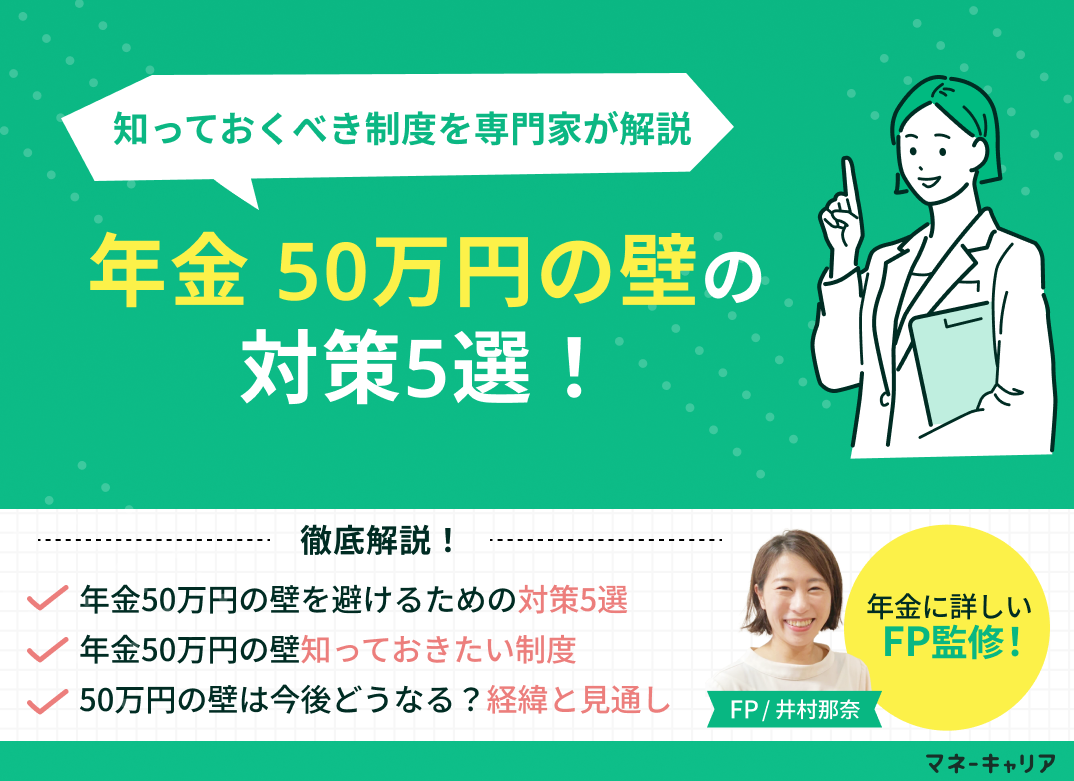 年金「50万円の壁」の対策5選!知っておくべき制度を専門家が解説
年金「50万円の壁」の対策5選!知っておくべき制度を専門家が解説2025-09-17
-
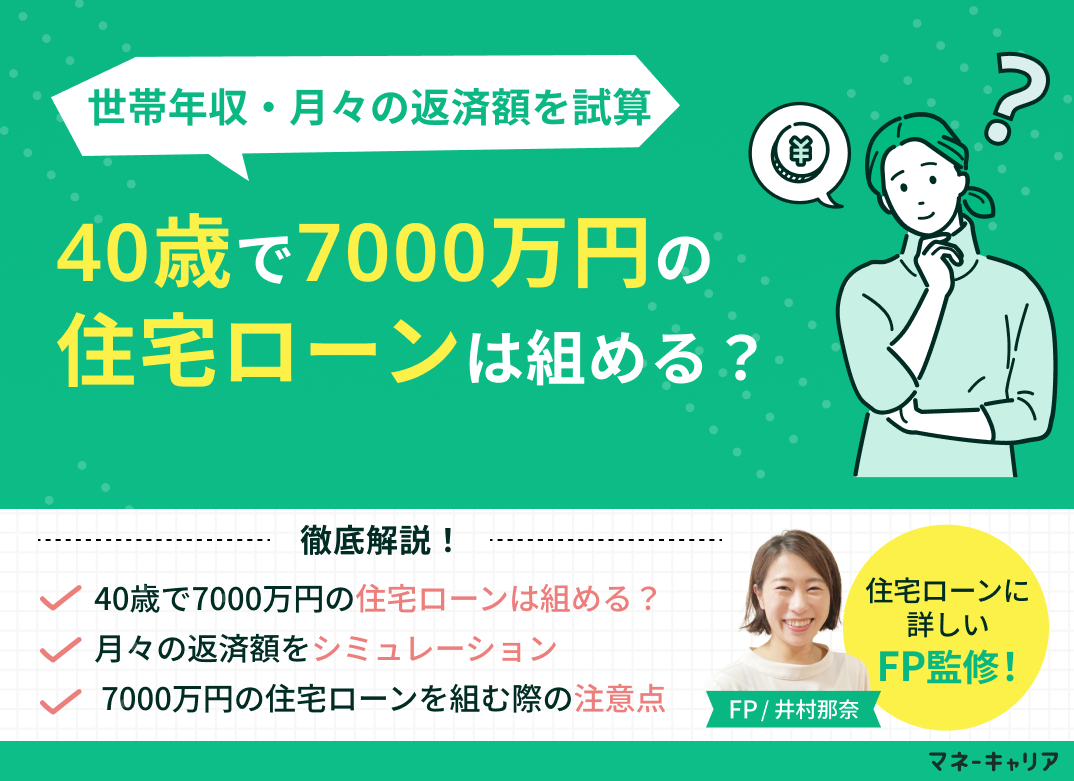 40歳で7000万円の住宅ローンは組める?世帯年収・月々の返済額を試算
40歳で7000万円の住宅ローンは組める?世帯年収・月々の返済額を試算2025-09-17
-
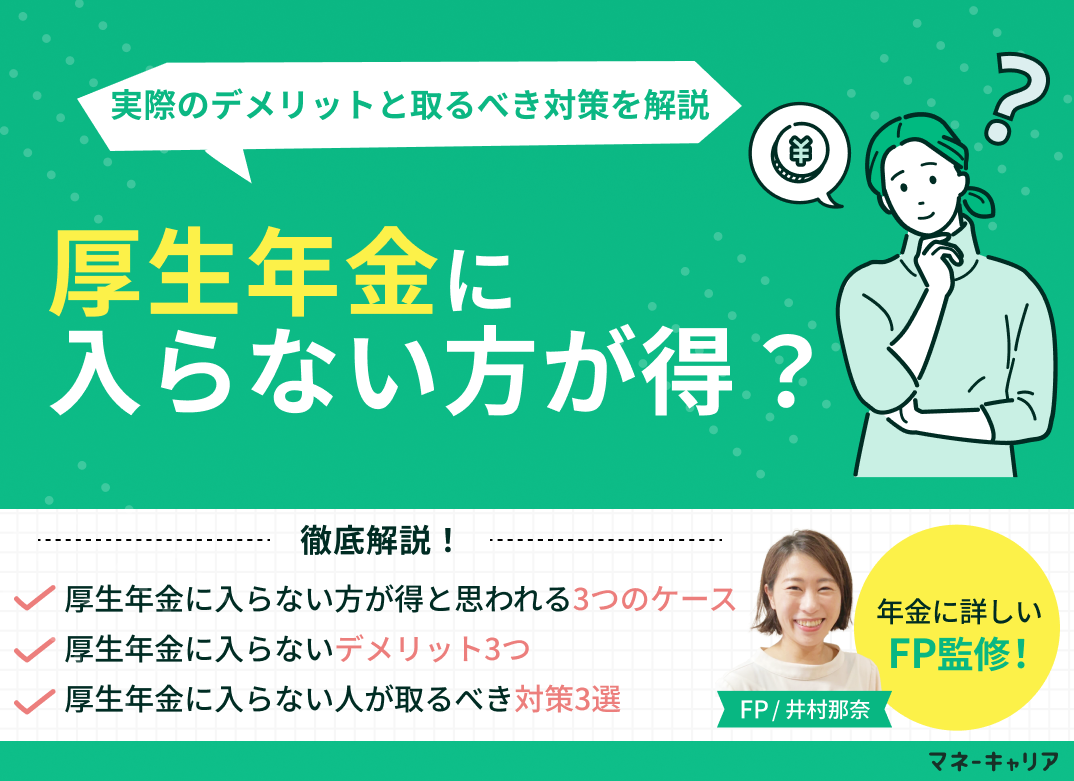 厚生年金に入らない方が得?実際のデメリットと取るべき対策を解説
厚生年金に入らない方が得?実際のデメリットと取るべき対策を解説2025-09-17
-
 住宅ローンで火災保険に入らないのは可能?必要性・保険料を抑えるコツを解説
住宅ローンで火災保険に入らないのは可能?必要性・保険料を抑えるコツを解説2025-09-17
-
 再雇用で厚生年金に加入しないのは可能?加入しないデメリットや対策も解説
再雇用で厚生年金に加入しないのは可能?加入しないデメリットや対策も解説2025-09-17
-
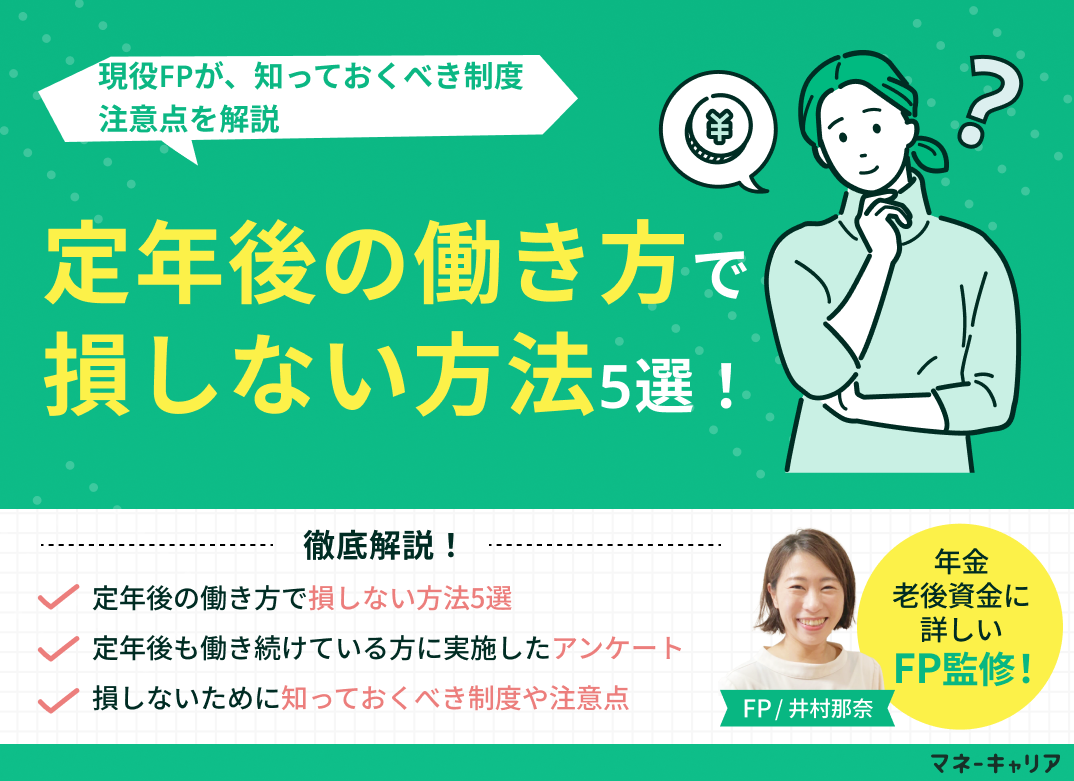 定年後の働き方で損しない方法5選!知っておくべき制度・注意点を解説
定年後の働き方で損しない方法5選!知っておくべき制度・注意点を解説2025-09-17
-
 転職1年目で住宅ローンは組める?審査に通りやすいケースと対策を解説
転職1年目で住宅ローンは組める?審査に通りやすいケースと対策を解説2025-09-17
-
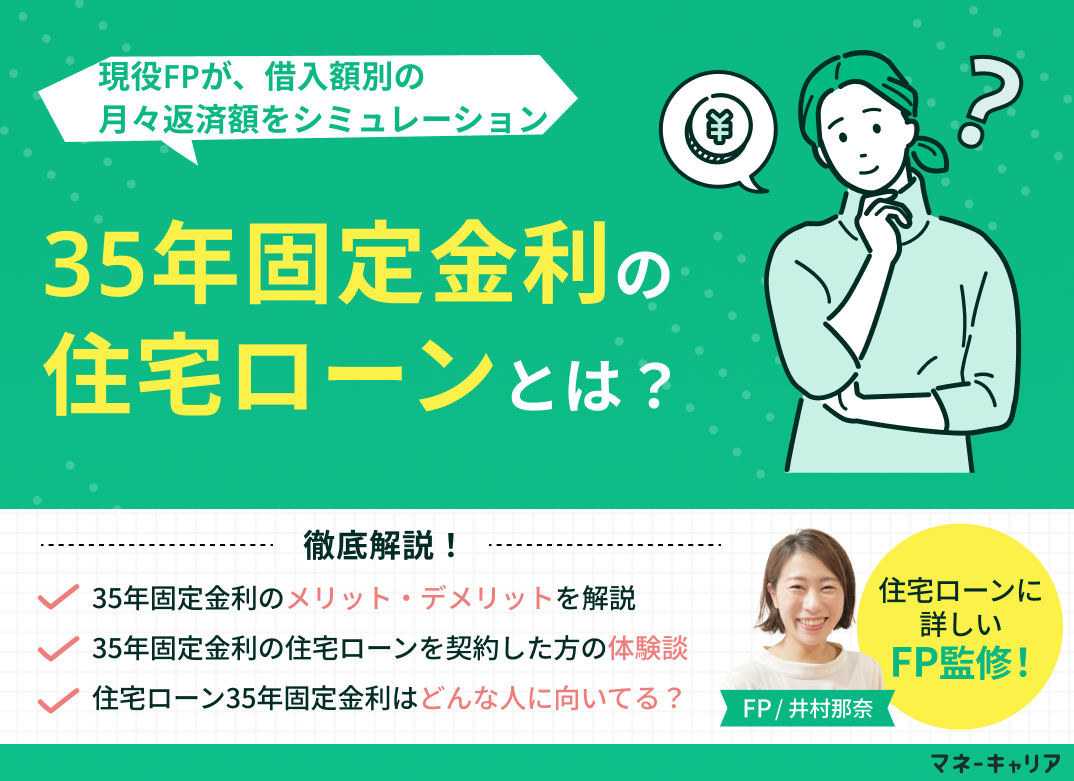 住宅ローン35年固定金利とは?借入額別の月々返済額をシミュレーション
住宅ローン35年固定金利とは?借入額別の月々返済額をシミュレーション2025-09-12
-
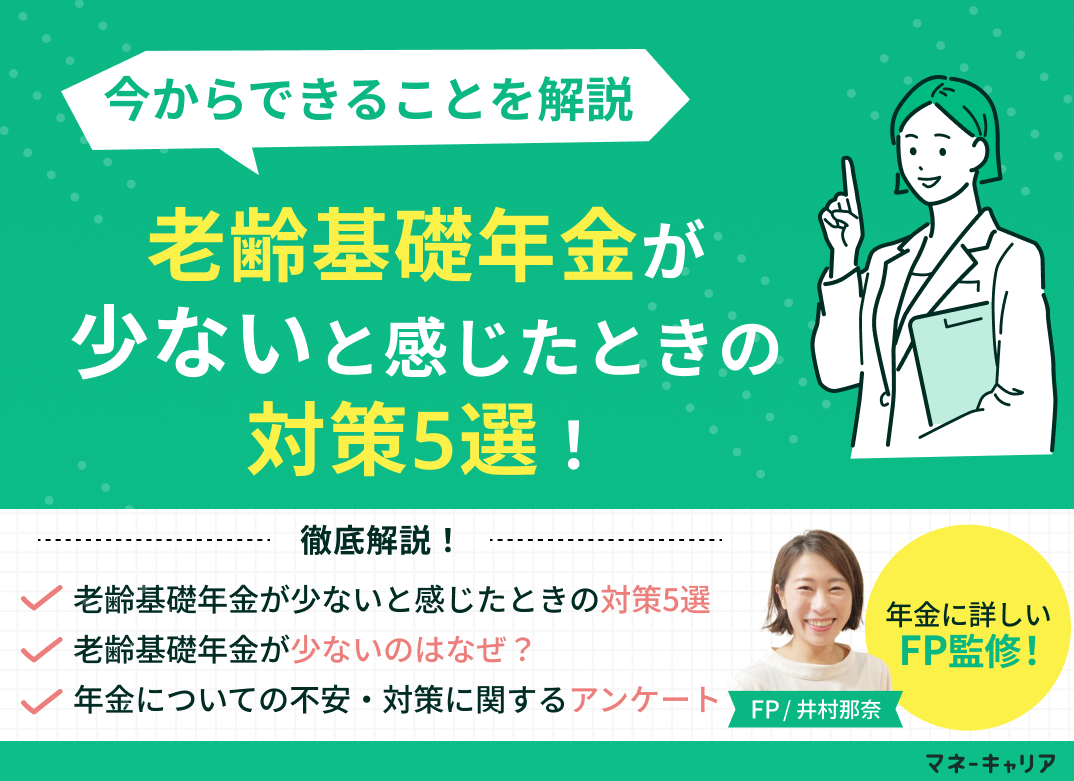 老齢基礎年金が少ないと感じたときの対策5選!今からできることを解説
老齢基礎年金が少ないと感じたときの対策5選!今からできることを解説2025-09-12

人気記事
-
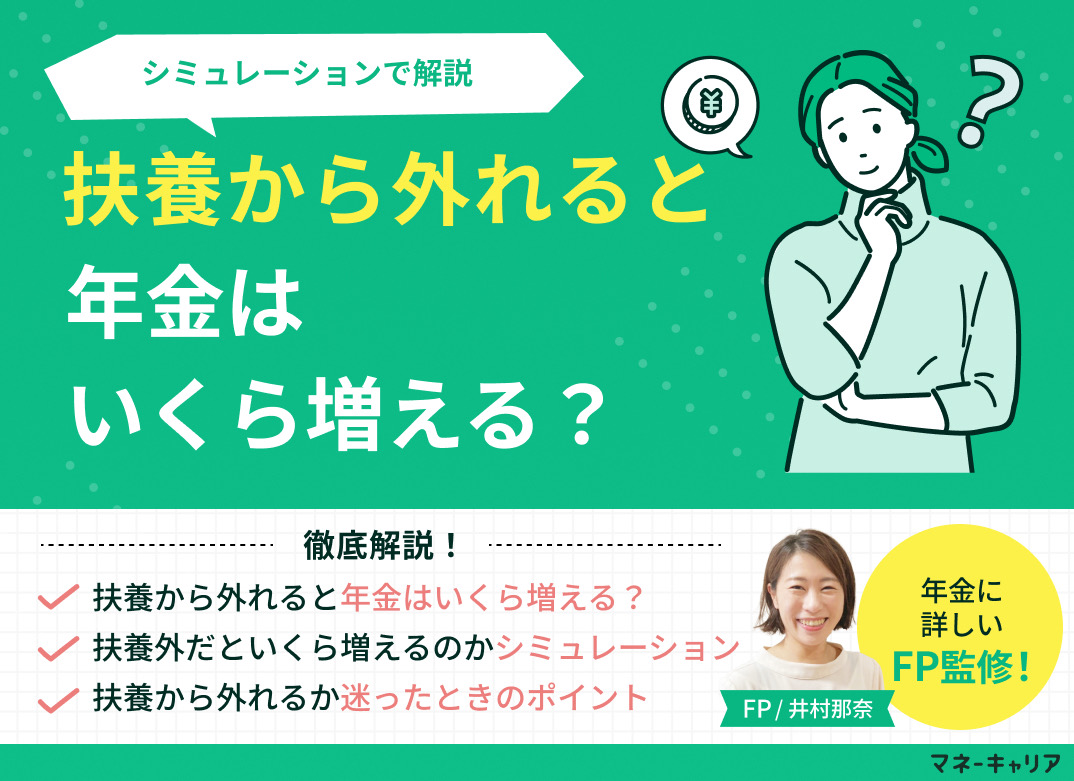 扶養から外れると年金はいくら増える?シミュレーションで解説
扶養から外れると年金はいくら増える?シミュレーションで解説2025-09-19
-
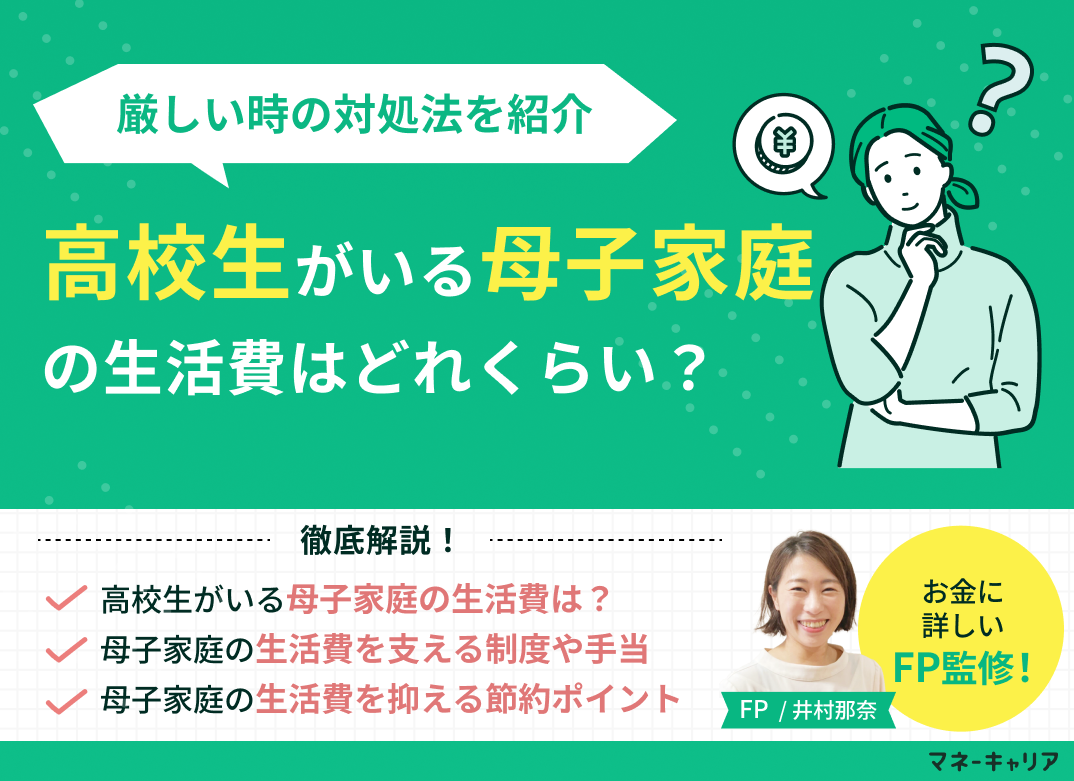 高校生がいる母子家庭の生活費は?節約ポイントや厳しいときの対処法
高校生がいる母子家庭の生活費は?節約ポイントや厳しいときの対処法2025-09-19
-
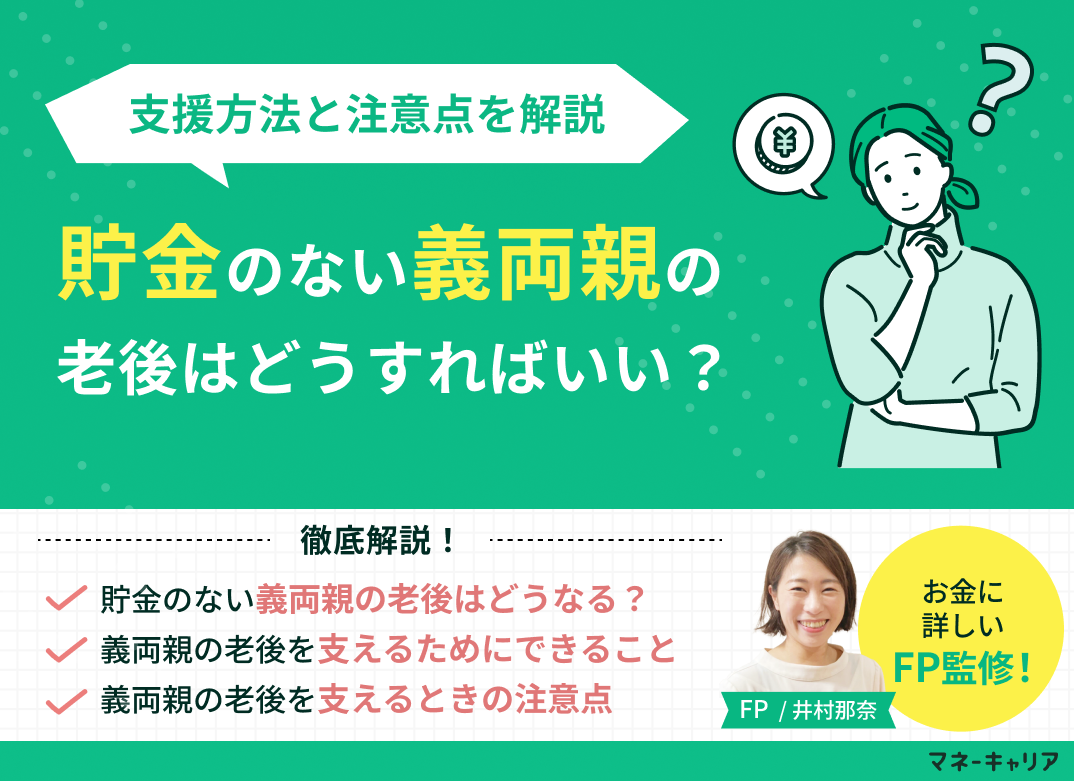 貯金のない義両親の老後はどうすればいい?支援方法と注意点を解説
貯金のない義両親の老後はどうすればいい?支援方法と注意点を解説2025-09-19
-
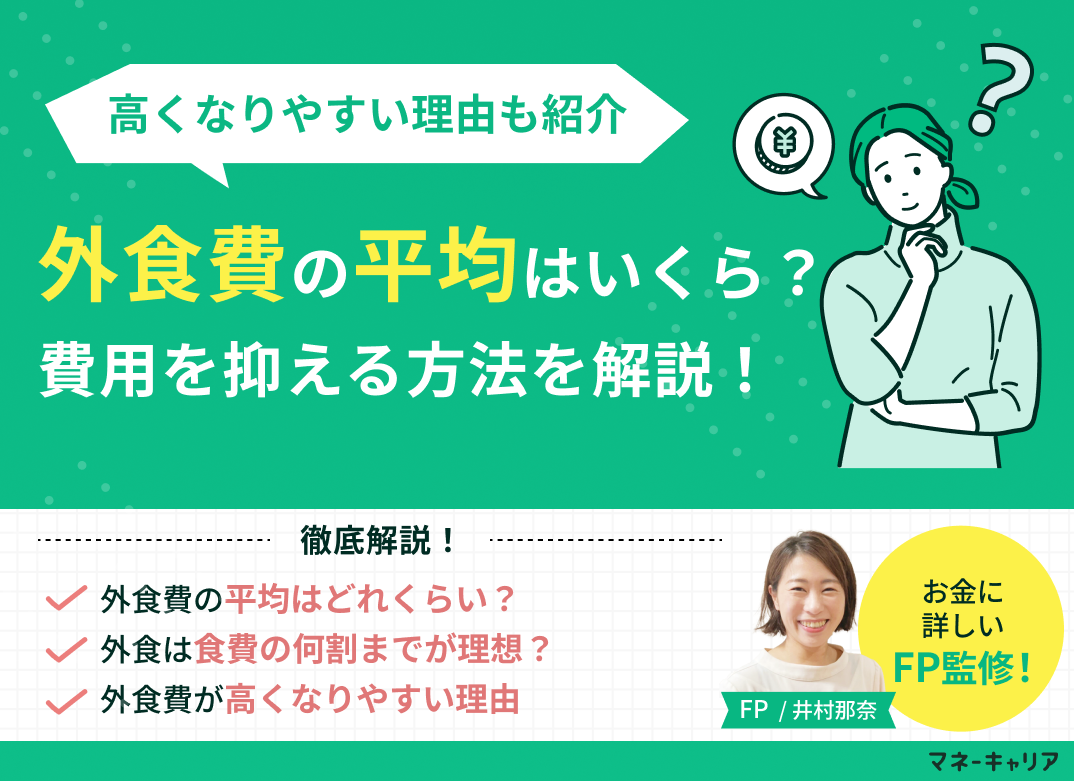 外食費の平均はいくら?高くなりやすい理由や費用を抑える方法を解説
外食費の平均はいくら?高くなりやすい理由や費用を抑える方法を解説2025-09-19
-
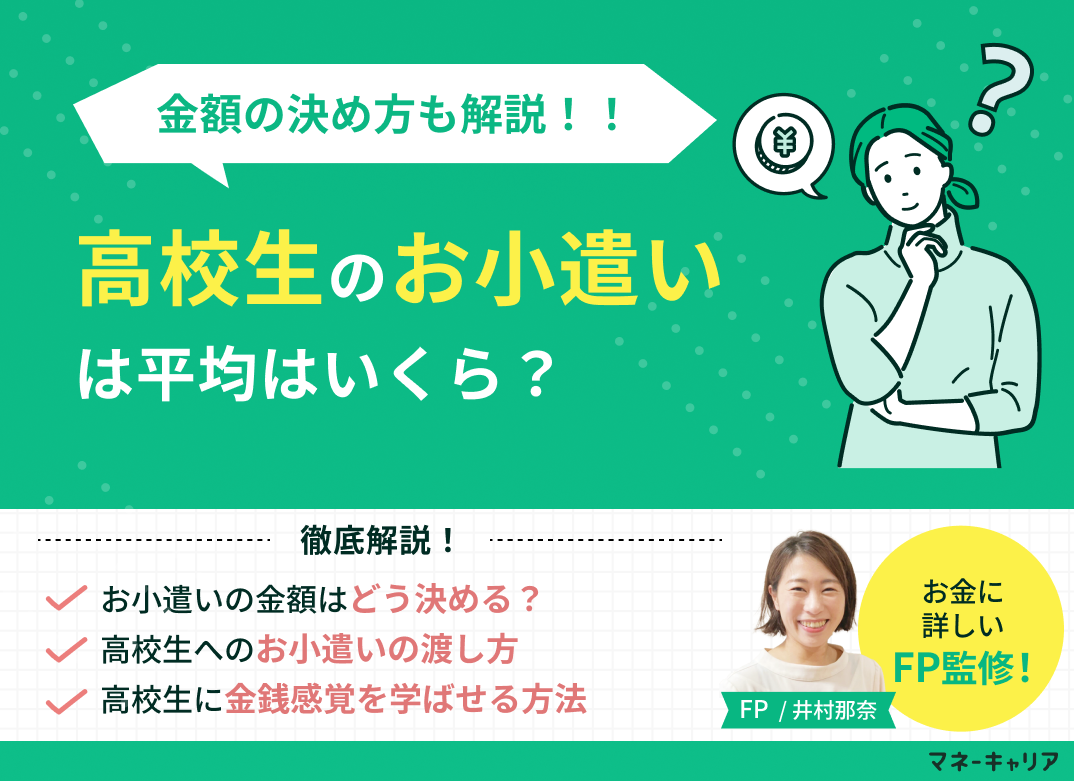 高校生のお小遣いは平均いくら?金額の決め方や金銭感覚を学ばせる方法
高校生のお小遣いは平均いくら?金額の決め方や金銭感覚を学ばせる方法2025-09-19
-
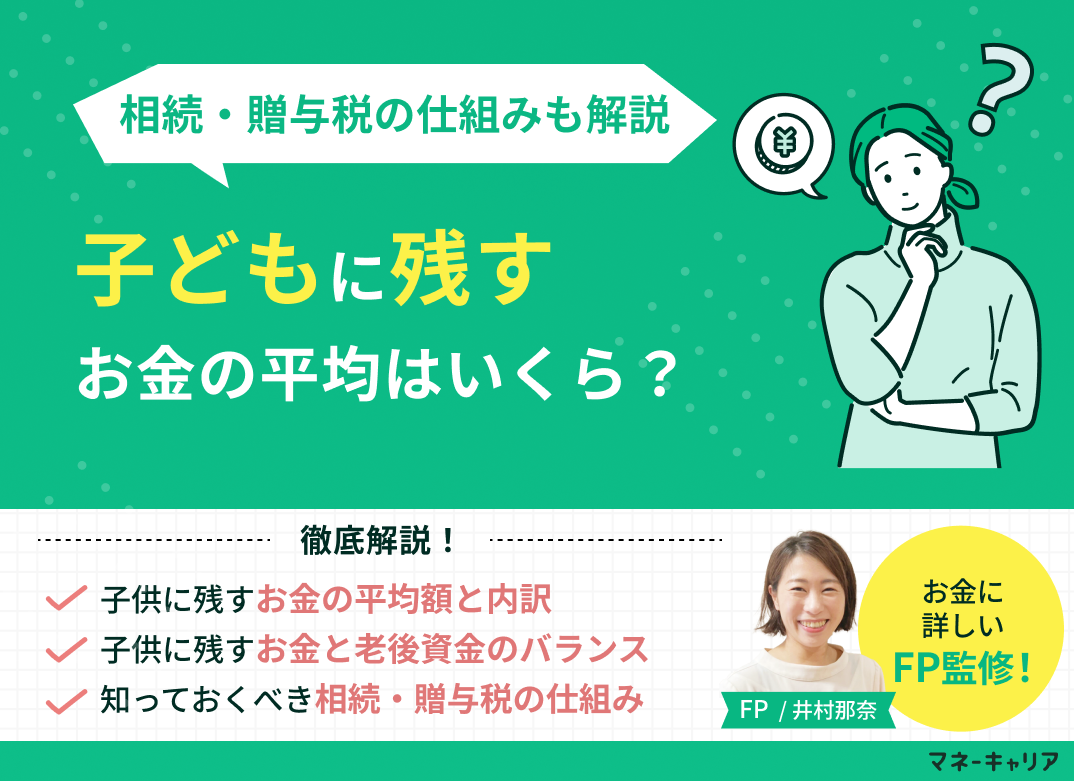 子供に残すお金の平均はいくら?相続・贈与税の仕組みとお金の準備方法
子供に残すお金の平均はいくら?相続・贈与税の仕組みとお金の準備方法2025-09-19
-
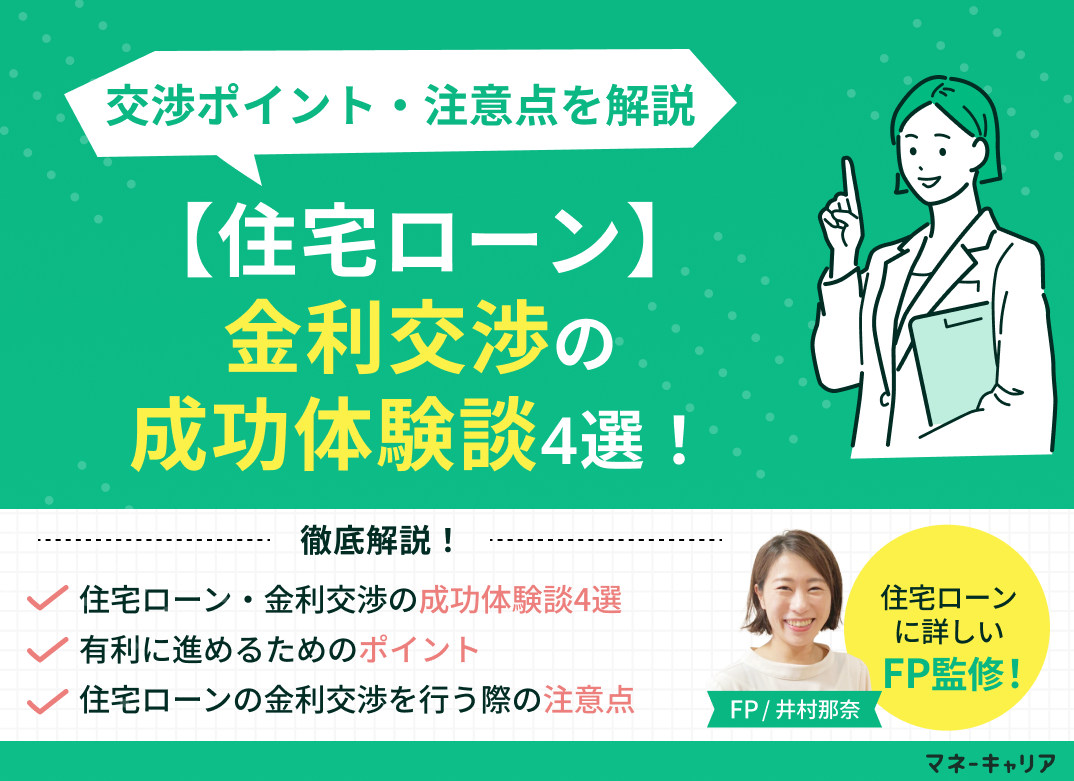 【住宅ローン】金利交渉の成功体験談4選!交渉ポイント・注意点を解説
【住宅ローン】金利交渉の成功体験談4選!交渉ポイント・注意点を解説2025-09-18
-
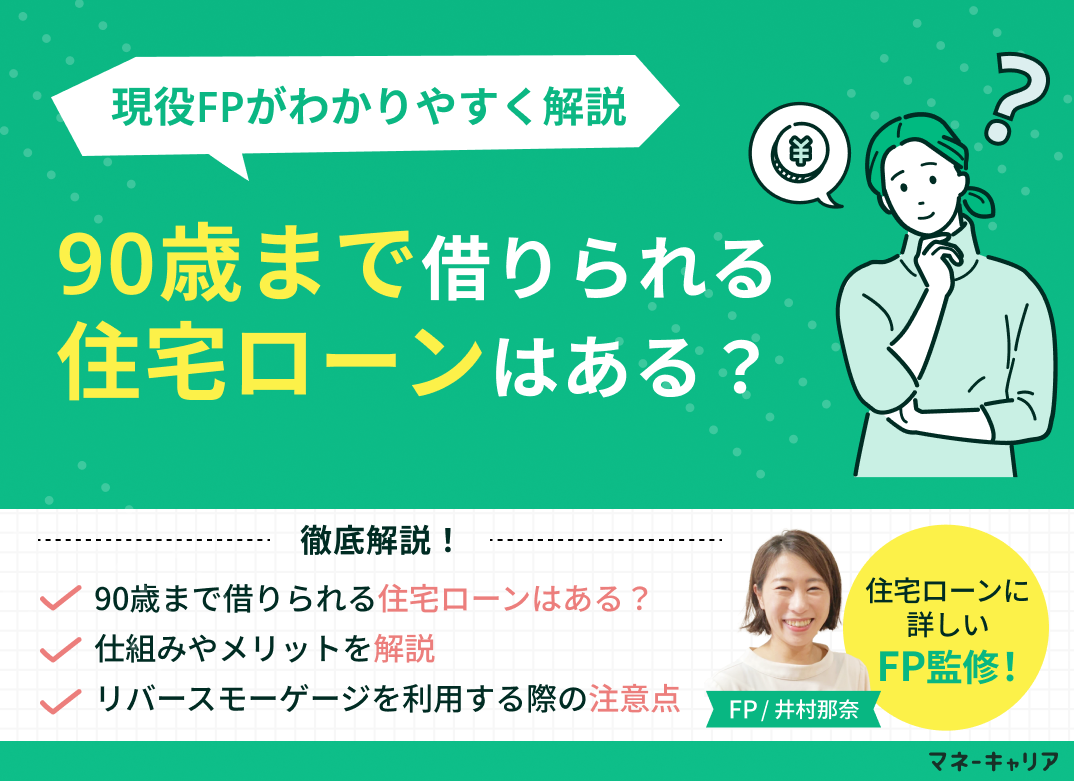 90歳まで借りられる住宅ローンはある?現役FPがわかりやすく解説
90歳まで借りられる住宅ローンはある?現役FPがわかりやすく解説2025-09-18
-
 転職で住宅ローンの金利は変わる?返済中に気をつけたい注意点を解説
転職で住宅ローンの金利は変わる?返済中に気をつけたい注意点を解説2025-09-18
-
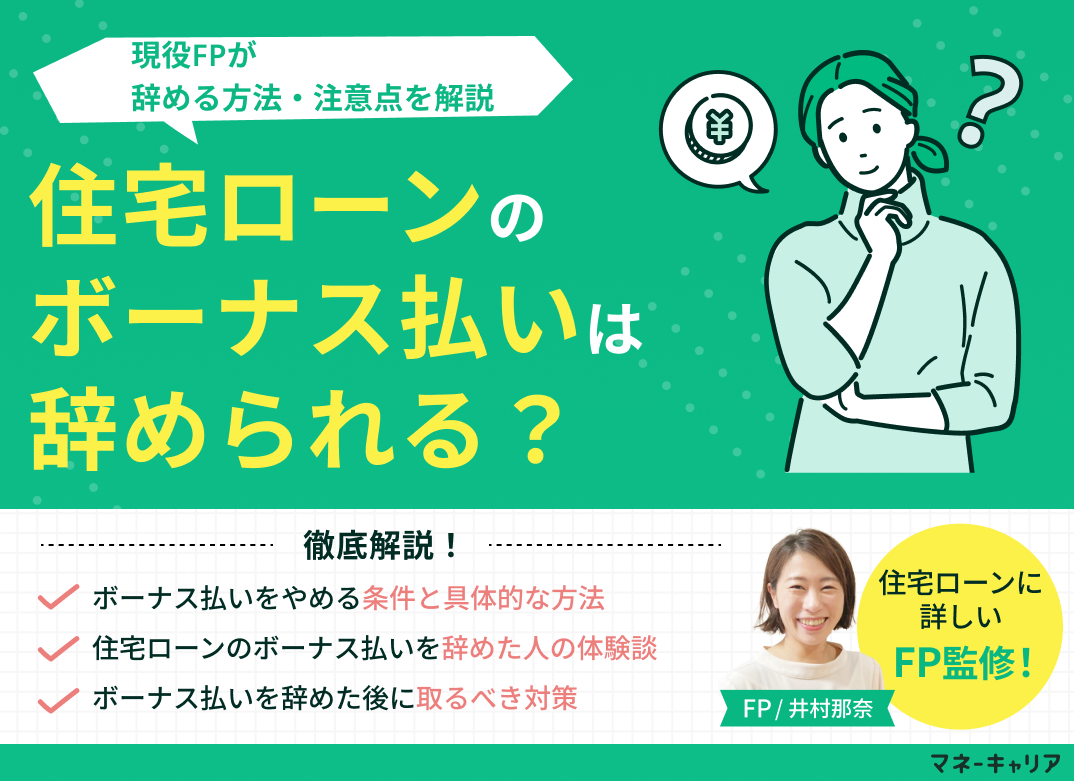 住宅ローンのボーナス払いを辞められる?辞める方法・注意点を解説
住宅ローンのボーナス払いを辞められる?辞める方法・注意点を解説2025-09-17
-
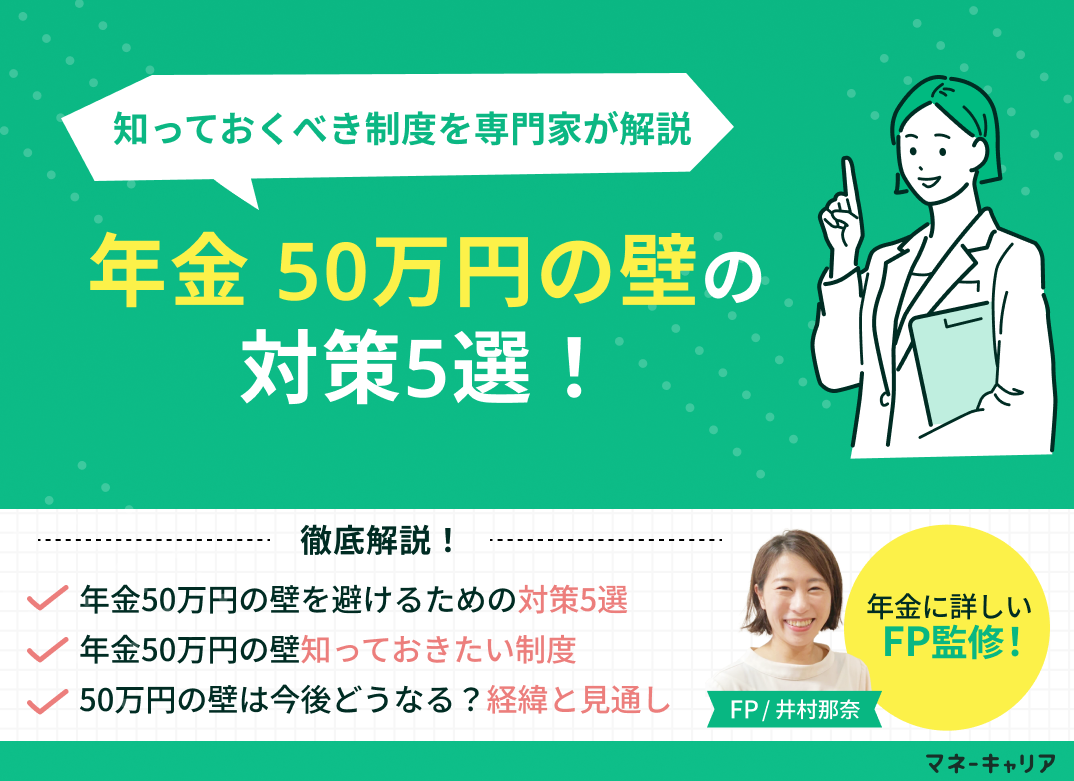 年金「50万円の壁」の対策5選!知っておくべき制度を専門家が解説
年金「50万円の壁」の対策5選!知っておくべき制度を専門家が解説2025-09-17
-
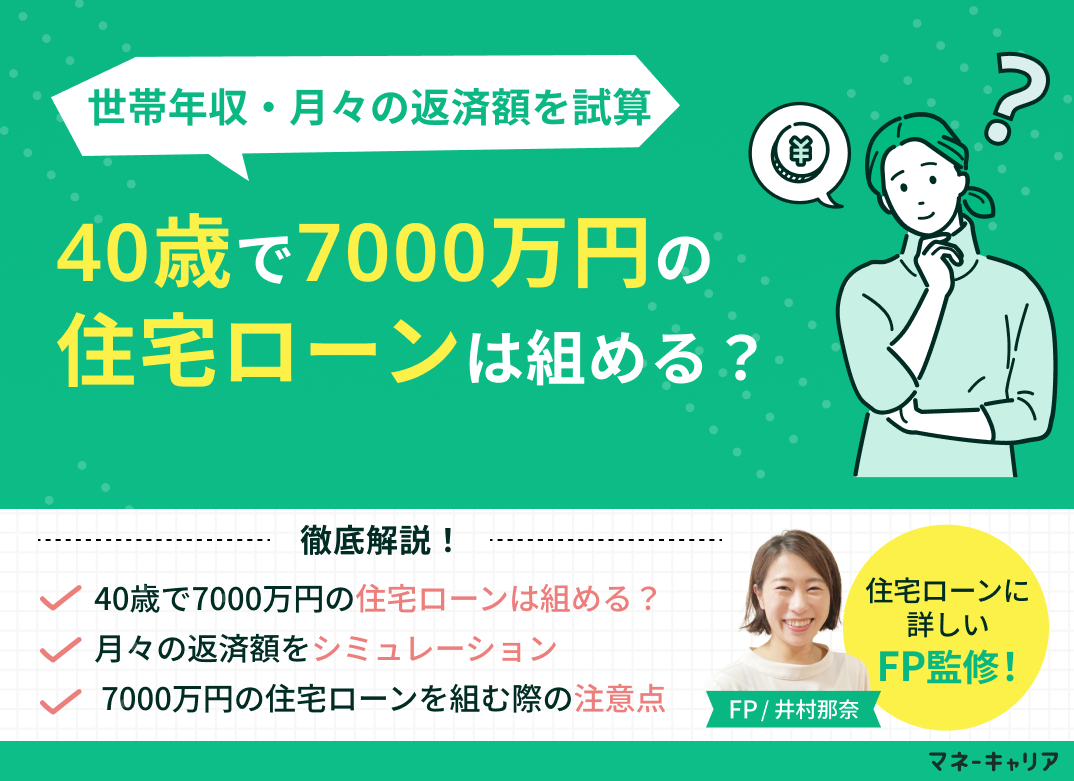 40歳で7000万円の住宅ローンは組める?世帯年収・月々の返済額を試算
40歳で7000万円の住宅ローンは組める?世帯年収・月々の返済額を試算2025-09-17
-
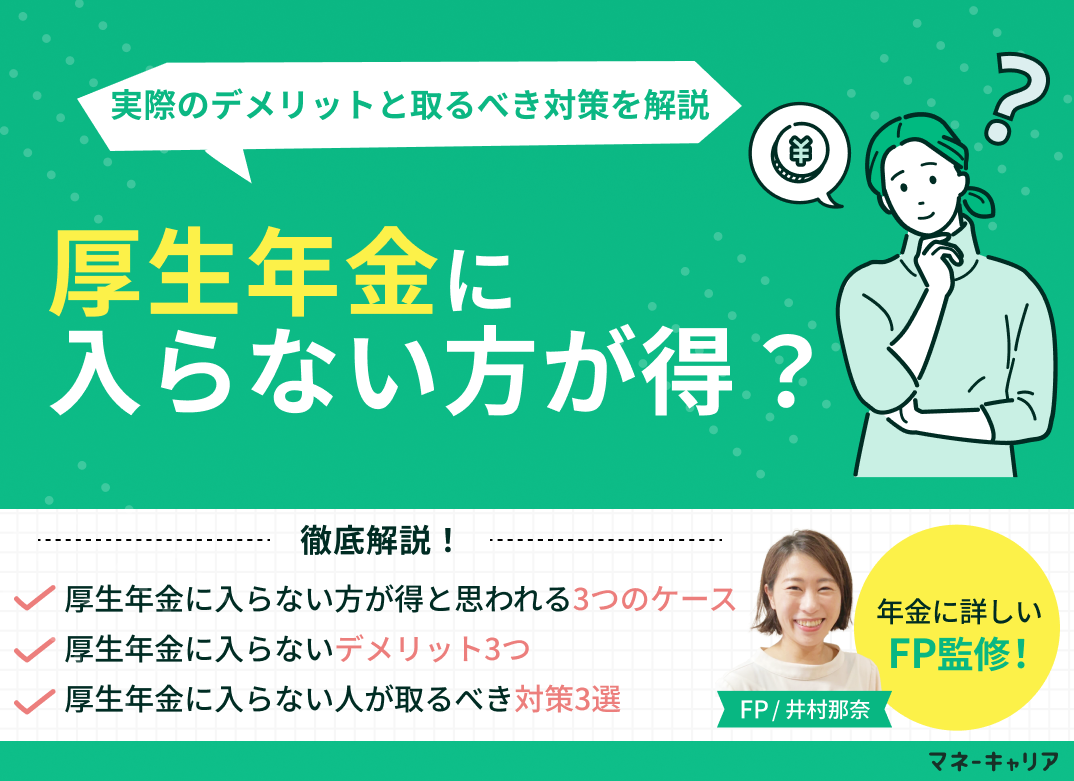 厚生年金に入らない方が得?実際のデメリットと取るべき対策を解説
厚生年金に入らない方が得?実際のデメリットと取るべき対策を解説2025-09-17
-
 住宅ローンで火災保険に入らないのは可能?必要性・保険料を抑えるコツを解説
住宅ローンで火災保険に入らないのは可能?必要性・保険料を抑えるコツを解説2025-09-17
-
 再雇用で厚生年金に加入しないのは可能?加入しないデメリットや対策も解説
再雇用で厚生年金に加入しないのは可能?加入しないデメリットや対策も解説2025-09-17
-
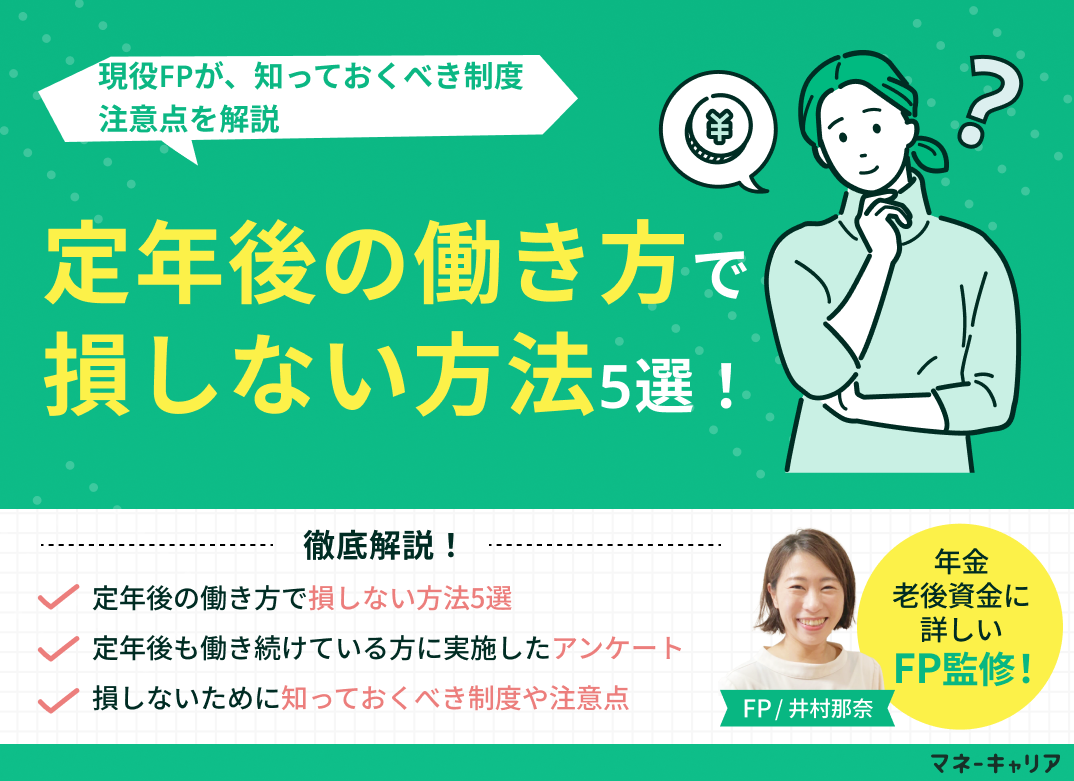 定年後の働き方で損しない方法5選!知っておくべき制度・注意点を解説
定年後の働き方で損しない方法5選!知っておくべき制度・注意点を解説2025-09-17
-
 転職1年目で住宅ローンは組める?審査に通りやすいケースと対策を解説
転職1年目で住宅ローンは組める?審査に通りやすいケースと対策を解説2025-09-17
-
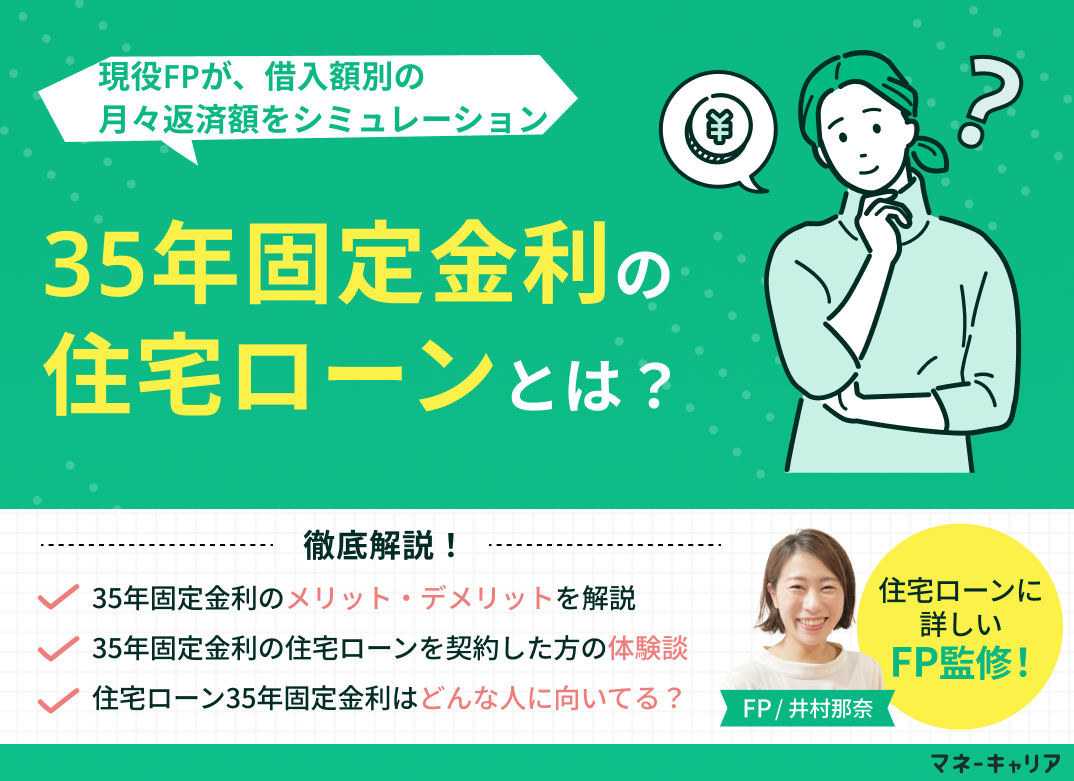 住宅ローン35年固定金利とは?借入額別の月々返済額をシミュレーション
住宅ローン35年固定金利とは?借入額別の月々返済額をシミュレーション2025-09-12
-
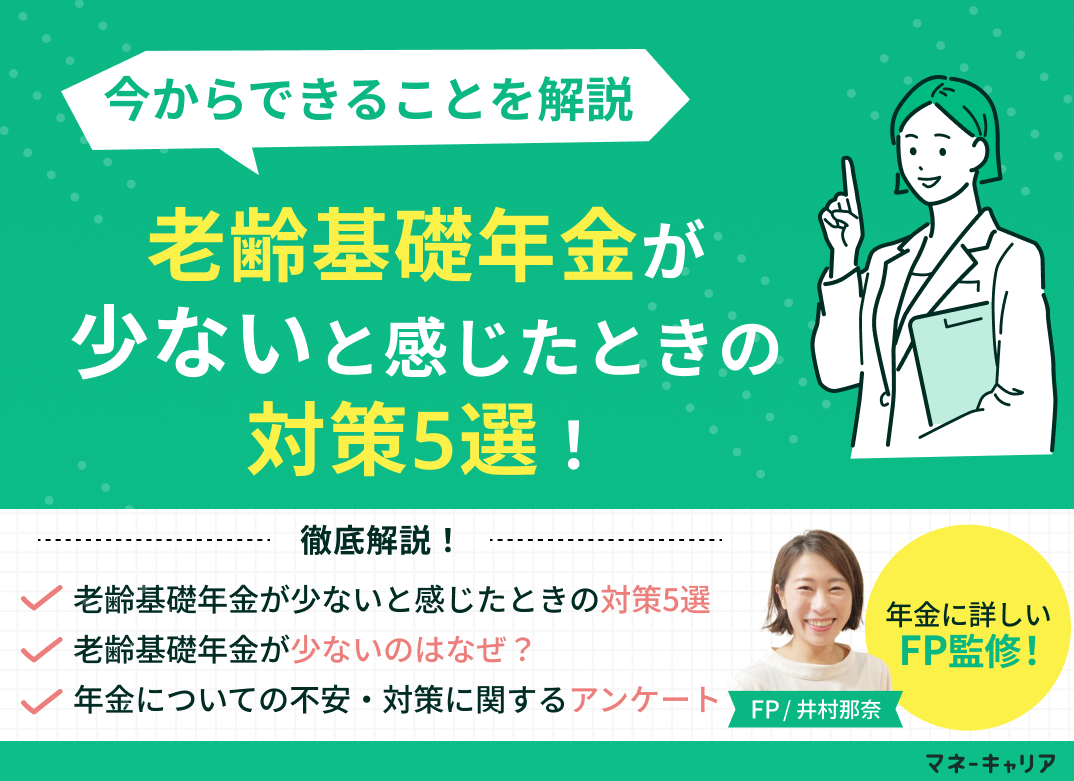 老齢基礎年金が少ないと感じたときの対策5選!今からできることを解説
老齢基礎年金が少ないと感じたときの対策5選!今からできることを解説2025-09-12