

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 公務員夫婦で住宅ローン6000万円は可能?
- 必要な世帯年収の目安は800万円以上
- 理想的な頭金の目安は600万円以上
- 【結論】公務員夫婦・住宅ローン6000万円は「無理なく返せるか」が重要
- 無料FP相談を活用して、ライフプランを踏まえた返済計画を立てよう!
- 公務員夫婦・住宅ローン6000万円の月々の返済額をシミュレーション
- 借入期間35年の場合
- 借入期間30年の場合
- 借入期間25年の場合
- 公務員夫婦が住宅ローン6000万円で失敗しないための注意点
- 夫婦にとって最適なローンの組み方を検討する
- 返済負担率を必ず確認する
- 住宅の維持費も忘れずに試算する
- 教育資金や老後資金とのバランスを考慮する
- 無料FP相談を活用して最適な返済プランを立てる
- 【まとめ】公務員夫婦の6000万円ローンは慎重な計画が必要
公務員夫婦で住宅ローン6000万円は可能?
安定した収入と雇用が魅力の公務員夫婦。住宅購入を検討する際、「6000万円のローンは現実的なのか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、世帯年収や頭金の準備状況によっては十分に可能ですが、重要なのは「借りられるか」ではなく「無理なく返せるか」です。
まずは、公務員夫婦が6000万円の住宅ローンを組む際に押さえておきたいポイントを、以下の3つの視点から解説します。
- 必要な世帯年収の目安は800万円以上
- 理想的な頭金の目安は600万円以上
- 【結論】公務員夫婦・住宅ローン6000万円は「無理なく返せるか」が重要
安定した職業だからこそ、長期的な返済計画を立てて、安心してマイホームを手に入れるための判断材料にしてください。
必要な世帯年収の目安は800万円以上
6000万円の住宅ローンを組むには、金融機関の審査基準や返済負担率を踏まえた世帯年収が重要です。
一般的には年収の6〜8倍が借入可能額の目安とされており、6000万円の借入には世帯年収800万円以上〜1000万円以上が必要と考えられます。
返済負担率とは、年間返済額が年収に占める割合のことです。住宅ローン審査ではこの指標が重視され、以下のような基準があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一般的な審査基準 | 30~35%以下 |
| 理想的な返済負担 | 20~25%以下 |
| 返済率が高い場合 | 家計を圧迫し、生活費や教育費に影響が出る可能性あり |
シミュレーション 世帯年収1000万円の場合
<前提条件>
- 借入金額:6000万円
- 金利:1.5%(全期間固定)
- 返済期間:35年
- 返済方法:元利均等返済
- 頭金・ボーナス・繰上げ返済なし
- 手取り年収:800万円(年収1000万円想定)
<試算結果>
- 毎月返済額:約18.3万円
- 年間返済額:約219.6万円
- 返済負担率:約27.5%(219.6万円 ÷ 800万円 × 100)
この返済負担率は、審査基準内ではあるものの、理想的な水準(25%以下)をやや上回るため、家計に余裕を持たせたい場合は年収1000万円以上が望ましいといえます。
理想的な頭金の目安は600万円以上
住宅ローン6000万円を検討する場合、理想的な頭金は物件価格の1〜2割が目安とされ、600万円〜1200万円程度が妥当です。
頭金を多く入れることで借入額を抑えられ、月々の返済負担や総支払額の軽減につながります。また、金融機関によっては金利優遇の対象となることもあり、審査にも有利に働くケースがあります。
ただし、家計の状況やライフプランによって、最適な頭金の額は異なります。手元資金をすべて頭金に充ててしまうと、急な支出に対応できなくなるリスクもあります。
頭金なし・フルローンでの購入も可能ですが、返済負担や将来の資金計画を踏まえた判断が重要です。
【結論】公務員夫婦・住宅ローン6000万円は「無理なく返せるか」が重要
公務員夫婦は安定した雇用と収入により、金融機関から高く評価される傾向があります。そのため、6000万円という高額な住宅ローンでも審査に通りやすいケースが多いです。
しかし、「借りられる額」と「無理なく返せる額」はまったくの別物です。審査に通ったからといって、それが安心して返済できる金額とは限りません。
住宅ローンは長期にわたる支払いが前提となるため、借入額を決める際には以下のような視点が重要です。
- 返済負担率(理想は手取り年収の20〜25%以内)
- 教育費や老後資金など将来の支出
- 収入の変動リスク(育休・転勤など)
- 完済時の年齢と退職後の生活設計
営業トークに流されず、「借りられるか」ではなく「返せるか」を基準に、冷静な資金計画を立てることが求められます。
無料FP相談を活用して、ライフプランを踏まえた返済計画を立てよう!

住宅ローン6000万円という高額な借入を検討する際は、ライフプランに基づいた返済計画の設計が不可欠です。
マネーキャリアの無料FP相談では、家庭の収支や将来のライフイベントを踏まえたシミュレーションとアドバイスが受けられます。
不動産営業とは異なり、FPは中立的な立場から冷静な判断をサポートしてくれるため、「借りられる額」ではなく「返せる額」を見極めることが可能です。
家族構成や教育費、老後資金なども含めた長期的な視点での資金設計ができるため、安心して住宅購入に踏み切るための心強い味方となるでしょう。

公務員夫婦・住宅ローン6000万円の月々の返済額をシミュレーション
公務員夫婦で6000万円の住宅ローンを検討する場合、月々の返済額がどれくらいになるのかは、借入期間によって大きく変わります。
安定した収入があるとはいえ、返済負担が家計に与える影響は無視できません。無理なく返済を続けるためには、シミュレーションを通じて具体的な金額を把握しておくことが重要です。
ここでは、借入期間ごとの月々の返済額を以下の3つのケースで比較します。
- 借入期間35年の場合
- 借入期間30年の場合
- 借入期間25年の場合
それぞれの返済額を把握し、ライフプランに合った借入期間を選ぶ参考にしてください。
借入期間35年の場合
まずは借入期間35年の場合を見てみましょう。以下の条件でシミュレーションを行いました。
- 借入金額:6000万円
- 金利:1.5%(全期間固定)
- 借入期間:35年
- 頭金・ボーナス・繰上げ返済なし
- 返済方法:元利均等返済
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入金額 | 6000万円 |
| 借入期間 | 35年(420カ月) |
| 毎月返済額 | 約183,711円 |
| 年間返済額 | 約2,204,532円 |
| 総返済額 | 77,158,479円 |
毎月約18.3万円の返済は、公務員夫婦の世帯年収が1000万円前後であれば現実的な水準といえます。
借入期間30年の場合
続いて借入期間30年の場合を見てみましょう。 以下の条件で住宅ローン6000万円の返済シミュレーションを行いました。
- 借入金額:6000万円
- 金利:1.5%(全期間固定)
- 借入期間:30年(360ヶ月)
- 頭金・ボーナス・繰上げ返済なし
- 返済方法:元利均等返済
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入金額 | 6000万円 |
| 借入期間 | 30年(360カ月) |
| 毎月返済額 | 約207,072円 |
| 年間返済額 | 約2,484,864円 |
| 総返済額 | 約74,545,965円 |
毎月の返済額は約20.7万円となり、世帯年収が1000万円前後の公務員夫婦であれば、返済負担率は約31%(手取り800万円換算)とやや高めです。
生活費や教育費など将来の支出を考慮すると、頭金の投入や繰上げ返済の検討が現実的な選択肢となります。
借入期間25年の場合
最後は借入期間25年の場合を見てみましょう。以下の条件で住宅ローン6000万円の返済シミュレーションを行いました。
- 借入金額:6000万円
- 金利:1.5%(全期間固定)
- 借入期間:25年(300ヶ月)
- 頭金・ボーナス・繰上げ返済なし
- 返済方法:元利均等返済
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入金額 | 6000万円 |
| 借入期間 | 25年(300カ月) |
| 毎月返済額 | 約238,527円 |
| 年間返済額 | 約2,862,324円 |
| 総返済額 | 約71,558,100円 |
毎月の返済額は約23.8万円となり、世帯年収1000万円・手取り800万円の公務員夫婦の場合、返済負担率は約35.8%と高めです。
これは金融機関の審査基準ギリギリであり、生活費や教育費などの支出を圧迫する可能性があります。
公務員夫婦が住宅ローン6000万円で失敗しないための注意点
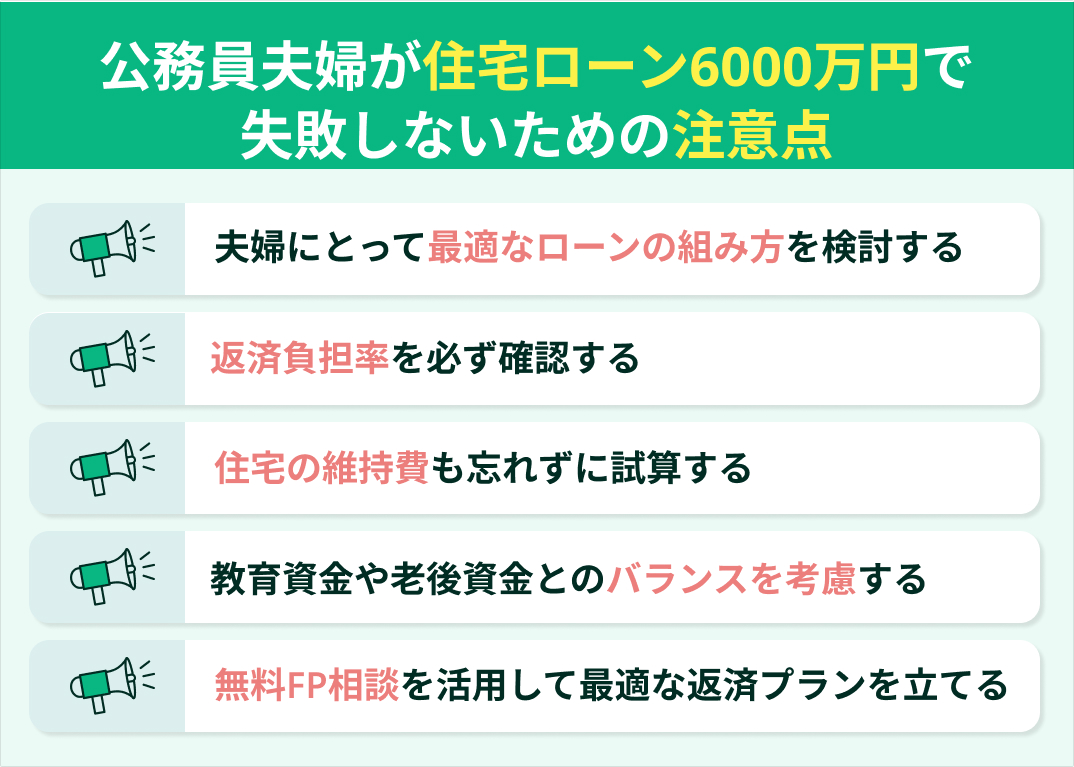
公務員夫婦は安定した収入があるため、高額な住宅ローンを組みやすい立場にあります。しかし、6000万円という大きな借入額には、それ相応のリスクと責任が伴います。「借りられる」ではなく「返せるかどうか」を軸に、慎重に計画を立てることが大切です。
ここでは、公務員夫婦が6000万円の住宅ローンで失敗しないために押さえておきたい注意点を、以下の5つの視点から解説します。
- 夫婦にとって最適なローンの組み方を検討する
- 返済負担率を必ず確認する
- 住宅の維持費も忘れずに試算する
- 教育資金や老後資金とのバランスを考慮する
- 無料FP相談を活用して最適な返済プランを立てる
将来の安心と家計の安定を両立させるために、これらのポイントをしっかり押さえておきましょう。
夫婦にとって最適なローンの組み方を検討する
共働きの公務員夫婦が6000万円の住宅ローンを組む際には、「ペアローン」か「連帯債務」かの選択が重要です。
それぞれの仕組みやメリット・デメリットを理解し、夫婦の収入バランスやライフプランに合わせて最適な方法を選びましょう。
<ペアローンと連帯債務の違いと比較表>
| 項目 | ペアローン | 連帯債務 |
|---|---|---|
| 契約本数 | 2本(夫婦それぞれ) | 1本(夫婦共同) |
| 所有権 | 夫婦それぞれの持分 | 夫婦共有 |
| 控除対象 | 夫婦それぞれ加入 | 控除が二人分(※条件あり) |
| 団信加入 | 夫婦それぞれ加入 | 夫婦連生団信も可能(フラット35など) |
| 諸費用 | 2契約分で割高 | 1契約分に抑えられる |
| 離婚時の対応 | 複雑になりやすい | 比較的シンプル |
※連帯債務型は一部の金融機関やフラット35で利用可能です。
<ライフプランと収入バランスを踏まえた選び方>
- 共働きが長期的に続く予定 → ペアローンで控除メリットを最大化
- 育休・退職など収入変動の可能性あり → 連帯債務で柔軟性を確保
- 老後の返済負担を軽減したい → フラット35+夫婦連生団信の検討も
返済負担率を必ず確認する
住宅ローンを検討する際は、返済負担率の確認が不可欠です。返済負担率とは、年収に対して年間返済額が占める割合のことで、住宅ローンだけでなく車のローン、教育ローン、カードローンなどすべての借入を合算して算出する必要があります。
例えば、住宅購入後に車のローンを追加すると、返済負担率が急上昇し、家計を圧迫するリスクがあります。
金融機関の審査では30〜35%以下が基準とされますが、理想は手取り年収の20〜25%以内に抑えること。将来的な支出や収入変動も見据え、無理のない返済計画を立てることが重要です。
住宅の維持費も忘れずに試算する
住宅購入後はローン返済だけでなく、維持費という“見えにくいコスト”が継続的に発生します。特に戸建ての場合、マンションのような管理費や修繕積立金はありませんが、自分で計画的に積み立てる必要があります。
<6000万円の戸建てを想定した年間維持費の概算(参考値)>
| 項目 | 概算費用(年間) | 備考 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 約15万~20万円 | 評価額や地域により変動。 都市計画税含む場合あり。 |
| 火災保険 | 約3万~6万円 | 補償内容・建物構造・地域によって異なる |
| 地震保険料 | 約2万~4万円 | 火災保険とセット加入、地域・構造で変動 |
| 修繕積立 | 約20万~30万円 | 外壁・屋根・水回りなど将来のメンテナンスに備える |
| その他(浄化槽・町内会費など) | 約1万~2万円 | 地域によって異なる |
合計は年間約41万~62万円(月額換算 約3.4万~5.2万円)となりそれなりの負担になることを理解しておきましょう。
教育資金や老後資金とのバランスを考慮する
住宅ローンを検討する際は、子どもの教育費や老後資金とのバランスも忘れてはなりません。特に公務員夫婦の場合、安定収入があるからこそ、将来の支出を見越した計画が重要です。
教育費は進路によって数百万円〜数千万円かかる可能性があり、大学進学時にはまとまった資金が必要になります。
また、ローン完済時の年齢が60歳を超える場合、退職後の生活資金との両立も課題になります。老後資金は「老後2000万円問題」などでも話題になったように、数千万円規模の準備が必要とされるケースもあります。
住宅ローンの返済と並行して、教育資金・老後資金をどう積み立てていくか、長期的な視点での資金設計が求められます。
無料FP相談を活用して最適な返済プランを立てる
住宅ローンや教育資金など、人生の大きな支出に向き合うとき、返済プランの設計は将来の安心に直結します。とはいえ、自分に合った返済方法を見極めるのは簡単ではありません。
そんなときこそ、無料のファイナンシャルプランナー(FP)相談を活用するのがおすすめです。中でも「マネーキャリア」の無料FP相談は、以下の点からとくにおすすめです。
・FP資格取得率100%
→すべての相談員が国家資格を保有。専門性の高いアドバイスが受けられる
・何度でも無料で相談可能
→納得いくまで何度でも相談できるため、返済プランの見直しにも柔軟に対応
・中立的な立場から提案
→特定の金融機関に偏らない提案で、ユーザー本位のプラン設計が可能
・オンライン・対面どちらも対応
→全国どこからでも相談でき、ライフスタイルに合わせた利用が可能
【まとめ】公務員夫婦の6000万円ローンは慎重な計画が必要

公務員夫婦の6000万円の住宅ローンは可能なのかということについて、 必要な世帯年収の目安、理想的な頭金、返済負担率、維持費や教育・老後資金とのバランスなど、慎重に検討すべきポイントを解説しましたがいかがでしたでしょうか。
公務員夫婦は安定した収入と雇用により、住宅ローン審査で有利とされる傾向があります。6000万円という高額ローンも、収入合算やペアローンの活用で審査に通る可能性は十分あります。
しかし、借りられる額=返せる額ではないことを忘れてはいけません。特に返済期間や完済時の年齢、将来のライフイベントを見据えた資金設計が重要です。住宅ローンは「通るか」より「続けられるか」が本質です。
マネーキャリアの無料FP相談では、家計の見える化・ライフプランの作成・返済シミュレーションなどを通じて、あなたの家庭に合った資金計画を提案してくれます。
住宅ローンに不安がある方は、まずはマネーキャリアで「返せる額」から逆算した安心の住まい選びを始めてみてはいかがでしょうか。






























