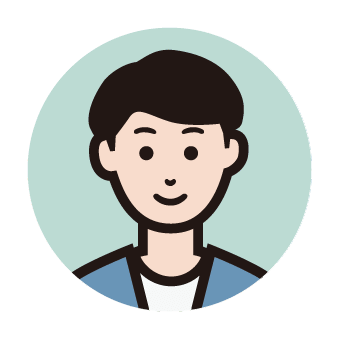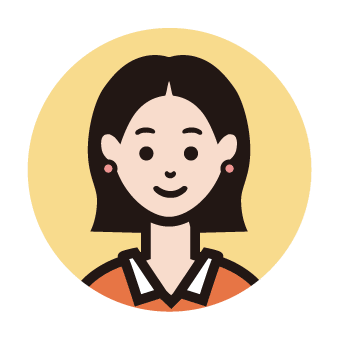「住宅ローンの5年ルール・125%ルールがない銀行を知りたい」
「住宅ローンの5年ルール・125%ルールがない場合のデメリットが心配」
とお悩みではないでしょうか。
- 結論、5年ルールや125%ルールがない銀行はソニー銀行や新生銀行があります。ただし、総返済額の増加で、将来に資金不足に陥る可能性もあるため、本当に5年ルールや125%ルールがなくても問題ないかは慎重に検討する必要があります。
内容をまとめると
- 住宅ローンの5年ルール・125%ルールがない銀行にはソニー銀行や新生銀行などがあり、金利・手数料・審査基準などを踏まえた比較が重要!
- ただし、住宅ローンの5年ルール・125%ルールには終盤の返済額増加などのデメリットがある一方、変動金利のリスクや家計負担の軽減などのメリットもあるため、判断には注意が必要
- 5年ルール・125%ルールの必要性は、収入やライフプランによっても異なるため、住宅ローン相談窓口を利用してプロのアドバイスを受けることが大切
- 住宅ローンの5年ルール・125%ルールでお悩みの方は、相談実績10万件以上・満足度98.6%のマネーキャリアのプロ(FP)に相談し、最適な借入先の選び方・返済プランのアドバイスを受けましょう!

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 住宅ローンの5年ルール・125%ルールとは?それぞれ解説!
- 5年ルールについて
- 125%ルールについて
- 住宅ローンの5年ルール・125%ルールがない銀行は?
- ソニー銀行
- 新生銀行
- PayPay銀行
- 5年ルール・125%ルールの有無で悩んでいる場合はFP無料相談で解決
- 住宅ローンの5年ルール・125%ルールが適用された際の金利上昇対策は?
- 無理のない返済ができる程度の借入額に抑えておく
- 余裕があれば繰り上げ返済をするのがおすすめ
- 住宅ローンの5年ルール・125%ルールのメリットは?
- 変動金利のリスクの減少
- 家計負担を低減できる
- 住宅ローンの5年ルール・125%ルールのデメリットは?
- 終盤に返済額が増え支払いが厳しくなるリスクがある
- 未払い利息が生じるリスクもある
- 住宅ローンの5年ルールで気を付けるべきことは?
- 住宅ローンに125%ルールが適用された場合のシミュレーション
- 住宅ローンの5年ルール・125%ルールならFP相談がおすすめ
- 住宅ローンのルールに詳しい専門家のいる相談サービス:マネーキャリア
- 住宅ローンの5年ルール・125%ルールがない銀行とは【まとめ】
住宅ローンの5年ルール・125%ルールとは?それぞれ解説!
住宅ローンの5年ルール・125%ルールは、変動金利型住宅ローンの返済額変動を抑制するための仕組みです。
これらのルールは、金利上昇時の家計への急激な負担増を防ぐ目的で設けられており、多くの金融機関で採用されているルールですが、すべての銀行で適用されているわけではありません。
以下では、それぞれのルールの詳細について解説します。
- 5年ルールについて
- 125%ルールについて
これらのルールを理解することで、変動金利型住宅ローンのリスクを適切に把握できるようになります。
5年ルールについて
5年ルールとは、変動金利型住宅ローンにおいて、金利が変動しても5年間は返済額を変更しないというルールです。
通常、変動金利は半年ごとに見直されますが、5年ルールが適用されている場合は、金利が上昇しても5年間は毎月の返済額が据え置かれます。
例えば、毎月10万円の返済をしている場合、金利が上昇しても5年間は10万円のまま返済を続けることができます。
ただし、金利上昇分の利息負担が消えるわけではなく、元金と利息の内訳が変わることになります。
金利が上昇すると利息部分が増え、元金返済部分が減少するため、元金の減り方が遅くなるという影響があります。
125%ルールについて
125%ルールとは、5年経過後に返済額を見直す際、新しい返済額は従来の返済額の125%を上限とするルールです。
例えば、従来の返済額が月10万円だった場合、金利が大幅に上昇していても、新しい返済額は最大12.5万円までに抑えられます。
このルールにより、返済額の急激な増加を防ぎ、家計への負担を軽減することができます。
ただし、125%を超える利息負担分は「未払い利息」として繰り越されるため、将来的に返済する必要があります。
住宅ローンの5年ルール・125%ルールがない銀行は?
住宅ローンの5年ルール・125%ルールがない銀行として、主にネット銀行系の金融機関が挙げられます。
例えば以下のような銀行では、5年ルール・125%ルールが採用されていません。
- ソニー銀行
- 新生銀行
- PayPay銀行
これらの銀行を選択する際は、金利変動時の影響を十分に理解しておくことが重要です。
ソニー銀行
ソニー銀行では、5年ルール・125%ルールを採用していません。
変動金利の見直しは年2回、5月1日と11月1日を基準に行われ、翌月(6月・12月)の返済日から新金利が適用されます(※)。
例えば、4月に金利が上昇した場合、5月から新しい金利に基づいた返済額での支払いが始まります。
ソニー銀行の変動金利は業界でも低水準を維持しており、金利の透明性も高いことが特徴です。
ただし、金利上昇時には返済額が即座に増加するため、家計への影響を事前に想定しておく必要があります。
新生銀行
新生銀行も5年ルール・125%ルールを採用していない銀行の一つです。
変動金利の見直しは年2回、5月1日と11月1日を基準に行われ、翌月(6月・12月)の返済日から新金利が適用されます(※)。
新生銀行は、団体信用生命保険の保障内容が充実しており、安心保障付団信やがん保障特約なども選択できます。
ただし、金利上昇時には返済額が即座に変更されるため、金利変動リスクを十分に理解した上で選択することが重要です。
PayPay銀行
PayPay銀行も5年ルール・125%ルールを適用していません。
変動金利の見直しは年2回、4月1日と10月1日を基準に行われ、6月・12月の返済日から新金利が適用されます(※)。
PayPay銀行の住宅ローンは、書類の提出や契約手続きがすべてオンラインで完結するため、手続きの利便性が高いことも魅力の一つです。
ただし、他のネット銀行と同様に、金利変動時の返済額変更が即座に反映されるため、金利上昇リスクへの備えが重要です。
5年ルール・125%ルールの有無で悩んでいる場合はFP無料相談で解決
5年ルール・125%ルールにはメリットとデメリットがあり、個人の収入状況やライフプランによって最適な選択が異なります。そのため、ルールの有無で悩んでいる場合は、FPへの相談がおすすめです。
FPに相談することで、あなたの収入の安定性やリスク許容度を踏まえて、5年ルール・125%ルールの必要性を個別にアドバイスしてもらえます。
また、銀行を選ぶ際のポイントも解説してもらえるので、住宅ローン選びがスピーディーになります。
5年ルール・125%ルールの必要性や選び方の適性は人によって異なるため、FPに相談して自分にあった住宅ローン契約を行いましょう。
住宅ローンの選択で迷ったら、マネーキャリアのFPのアドバイスを受けることで最適な判断ができます。
【Step1】マネーキャリアに無料相談する
・自分のリスク許容度に合った金利タイプの選び方がわかる!
・5年ルール・125%ルールの影響を具体的にシミュレーションできる!
【Step2】相談結果を基に最適な住宅ローンを選択・実行する
・安心して住宅購入に踏み切れる!
・将来の金利変動リスクに備えた計画を立てられる!
まずは気軽に無料相談してみませんか?
住宅ローンの5年ルール・125%ルールが適用された際の金利上昇対策は?
住宅ローンの5年ルール・125%ルールが適用された際の金利上昇対策は以下の2点です。
- 無理のない返済ができる程度の借入額に抑えておく
- 余裕があれば繰り上げ返済をするのがおすすめ
無理のない返済ができる程度の借入額に抑えておく
住宅ローンの借入額を決定する際には、無理のない返済ができる程度の借入額に抑えておくことがポイントです。
5年ルールや125%ルールを過信しすぎて、借入額を多く設定してしまうことはとても危険な状態になります。
これら2つのルールが適用されても、一時的に支払いが免除されるだけで、最終的には返済を行わなければなりません。
将来のことはどうなるかわからないものの、一括返済などのまとまった支払いを、将来に託すのは危険な行為です。
金利リスクによる返済額の増額を見越した上で返済計画を立て、無理のない返済ができる程度の借入額に抑えておくことがおすすめです。
余裕があれば繰り上げ返済をするのがおすすめ
急激な金利上昇のリスクを考慮し、繰り上げ返済をして借入元金を減らし、借入の期間を短くしておくのもひとつの方法です。
ある程度のまとまった金額を返していくことで、積極的に繰り上げ返済ができ、連動して利息も減っていきます。
繰り上げ返済には、「返済額軽減型」「期間短縮型」の2パターンがあります。
それぞれの違いはこちら。
| 返済額軽減型 | 期間短縮型 | |
|---|---|---|
| 違い | 返済期間を変えずに 毎月の返済額を引き下げる | 毎月の返済額等は変わらないが、 トータルの返済期間が短くなる |
| メリット | 毎月の固定費が下げるため 家計を安定させることができる | 当初の予定より早くローン返済が終わるため 将来の負担が減る |
金利上昇の対策としては、「期間短縮型」の繰り上げ返済が有効。
繰り上げ返済で借入期間を短くすることで、金利上昇のリスクを減らすことが期待できます。
住宅ローンの5年ルール・125%ルールのメリットは?
ここまで、5年ルールや125%ルールの、いろいろな制約を解説してきました。
5年ルールや125%ルールを適用させるためには、自身が契約する住宅ローンの種類をよく考えましょう。
では、「5年ルール」「125%ルール」にはどのようなメリットがあるのか、以下で解説していきます。
- 変動金利のリスクの減少
- 家計負担を低減できる
それぞれみていきます。
変動金利のリスクの減少
変動金利のリスク減少は、5年ルールや125%ルールを適用した際の大きなメリットです。
変動金利型はもともと金利が変動するというリスクがあり、金利が上がった場合は月々の支払額が増えてしまうのがデメリット。
そのため、変動金利に対して5年ルールや125%ルールを適用すると、変動金利のリスクを軽くすることが可能になります。
変動金利のリスクを軽くすることで、大幅にローン返済額が増えないよう微調整するのが、この2つのルールの目的です。
しかしながら、この2つのルールにはこのようなメリットと合わせてデメリットもあるため、デメリットについては後述します。
家計負担を低減できる
5年ルールや125%ルールを適用すれば、家計負担を低減できるメリットがあります。
住宅ローンとは、住宅という高額商品に融資を受けて購入し、長い期間をかけて返済していくものです。
住宅ローンを支払う期間は、ローンの返済だけでなく、生活費や教育費などもかさみ家計が大変となる時期。
このような時期に、変動金利で金利が上昇し続ければ、家計への影響は多大となるでしょう。
2つのルールを適用することで、変動金利であっても、ローンの返済額が一定額になったり返済額の極端な増額が避けられたりします。
住宅ローンを固定費として考えている人も、予想以上の大きな負担に苦しむことがないようにしてくれるのが5年ルールや125%ルールの大きなメリットです。
返済額が安定していれば、家計のやりくりも楽になり、その分貯蓄に回すなどといったことが可能となります。
住宅ローンの5年ルール・125%ルールのデメリットは?
5年ルールや125%ルールはメリットもある一方で、デメリットもあります。
2つのルールでは、金利が上がることでの支払い制限はありますが、支払い自体が免除されるわけではない点に注意が必要です。
ここでは、以下2つのデメリットについて紹介します。
- 終盤に返済額が増え支払いが厳しくなるリスクがある
- 未払い利息が生じるリスクもある
それぞれ詳しく解説していきます。
終盤に返済額が増え支払いが厳しくなるリスクがある
5年ルールと125%ルールは、終盤に返済額が増え支払いが厳しくなることがデメリットです。
元利均等返済での金額は、「元利+利息」が一定となるような調整が行われるためです。
5年ルールの適用で、金利が上がった場合には利息分を増やして元金を差し引き、返す金額が一定となるような調整が行われます。
実は、差し引かれた元金は免除されているわけではなく、融資契約が終わるころに一括返済が必要です。
これは、125%ルールも同様で、差し引かれた金額は契約が終わるころに一括での返済が求められます。
支払いが終わるころの出来事となるため、あまりイメージがつかないかもしれませんが、このようなデメリットもあることを覚えておきましょう。
未払い利息が生じるリスクもある
5年ルールや125%ルールを利用すると、未払い利息が生じるリスクがあるのもデメリットです。
未払い利息とは、返済する金額を超えてしまった利息のこと。
5年ルールで返済する金額が見直される期間、極端に金利が上がってしまうと、返済する金額が利息を超えてしまう可能性があります。
そのため、未払い利息が発生すると、返せるお金が利息だけになってしまいローン残高が減らず利息のみを払い続けることに。
5年ルールで金利が変わらなくなっているあいだは、未払い利息がたまっていき、支払い総額が増える一方となってしまいます。
このようなリスクがあることも理解した上で、これら2つのルールを適用させるかどうか検討するようにしましょう。
住宅ローンの5年ルールで気を付けるべきことは?
住宅ローンの5年ルールで気を付けるべきことは、「元金均等返済は5年ルール、125%ルールが適用外となること」です。
元金均等返済とは、元金部分を均等にして利息を加えて支払っていく方法です。
利息が支払い時期に応じて変わっていくため、2つのルールの適用対象外となります。
5年ルール・125%ルールが適用されるのは、元利均等返済方式を使用した場合。
元利均等返済方式では、金利が変わらないあいだは毎月の返す金額が一定で、支払いの計画が立てやすいのがメリットです。
デメリットとしては、元金均等返済を選択したときよりも物件自体の金額が減少するスピードが遅くなってしまうため注意が必要です。
5年ルールを適用するのかは、それぞれの家計の状況に合わせて判断するようにしましょう。
住宅ローンに125%ルールが適用された場合のシミュレーション
5年ルールと125%ルールによってどれくらいの恩恵が受けられるのでしょうか。
ここでは、以下の条件のもとで、5年ごとに月々返済額が125%に増える金利がどのくらいなのかシミュレーションしてみました。
- 借入額:3,500万円
- 借入期間:35年
- 変動金利:0.4%
- 返済方法:元利均等返済(ボーナス払いなし)
| 返済期間 | 金利(%) | 月々返済額(円) |
|---|---|---|
| 5年目 | 0.4 | 84166 |
| 6年目 | 2.0 | 84999 |
| 11年目 | 4.0 | 86666 |
| 16年目 | 6.7 | 88916 |
| 21年目 | 10.5 | 92082 |
| 26年目 | 16.1 | 96479 |
| 31年目 | 26.9 | 1057869 |
住宅ローンの5年ルール・125%ルールならFP相談がおすすめ
住宅ローンの5年ルールや125%ルールについて、悩んでいる方、迷っている方はFPに相談するのがおすすめです。
FPとはお金や保険、住宅ローンの専門家であり、相談することで日々のお金の悩みを解消することができます。
- 複雑な制度やルールを分かりやすく解説してくれる
- 個別の状況に合わせて、アドバイスをしてくれる
- 必要があれば、具体的な金額でシミュレーションをしてくれる
住宅ローンのルールに詳しい専門家のいる相談サービス:マネーキャリア

住宅ローンに関する全ての悩みにオンラインで解決できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、優秀なFPのみを厳選しています。
・保険だけではなく、資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能です。
・担当する専門家のFP資格保有率は100%であり、満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに 「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。

20代女性
住宅ローンのローン形態、借入先、金利タイプがわかりやすかったです!
住宅ローンの他にも投資信託のことまで分かりやすく教えて頂きました。こちらが質問したことにも丁寧に教えてくださり面談して良かったです!

30代女性
住宅ローンを中心としたライフプランの相談もできました!
たまたま見つけて申し込みをしたのですが、親身になって色々と相談に乗って頂きました。無理してローンを組もうとしていたのを思いとどまることができ、とても感謝しています。ありがとうございました!

40代男性
自分に最適な住宅ローンの借入額がわかりました!
住宅ローンの利用にあたり、現在の家計簿見直しを合わせて相談させてもらいました。自分で試算していて不安を覚えた部分が相談により解消でき、モヤモヤがなくなりすっきりしました。
住宅ローンの5年ルール・125%ルールがない銀行とは【まとめ】
- ソニー銀行
- 新生銀行
- PayPay銀行
- 無理のない返済ができる程度の借入額に抑えておく
- 余裕があれば繰り上げ返済をする
 【関連記事】住宅ローンの相談に関する記事
【関連記事】住宅ローンの相談に関する記事
 【関連記事】住宅ローンの借り換えに関する記事
【関連記事】住宅ローンの借り換えに関する記事
 【関連記事】住宅ローンの審査に関する記事
【関連記事】住宅ローンの審査に関する記事
 【関連記事】住宅ローンの既契約者におすすめの記事
【関連記事】住宅ローンの既契約者におすすめの記事
 【関連記事】各銀行の住宅ローンに関する口コミ
【関連記事】各銀行の住宅ローンに関する口コミ